「2024年度 医薬品評価委員会総会」を開催 今考える「Patient and Public Involvement」~私たちの活動は誰のため~
2024年11月15日に、室町三井ホール&カンファレンス(東京都中央区)で「第146回 医薬品評価委員会総会」を開催しました。医薬品評価委員会加盟会社の社員全員に開かれた総会として、会場とYouTube配信のハイブリット形式とし、オンラインでの参加を含め1,300名を超える参加者となりました。
Patient and Public Involvement(PPI)は英国で始まり、『患者や市民と共に、または患者や市民によって研究が行われること』と定義され、欧米主要各国に広まりました。国内では希少疾患やがんの患者団体等が活動を展開し、製薬企業も関連する取り組みを行っています。製薬協は2013年に「患者団体との協働に関するガイドライン」を発出し、医薬品評価委員会内でも2016年に「患者の声を活かした医薬品開発」のタスクフォースを立ち上げたことを皮切りに、現在ではさまざまな部会で関連する多くの取り組みが行われています。昨今、ドラッグ・ラグ/ロス問題を契機にPPIの重要性が再認識されています。しかし、委員会メンバーは所属部会以外の活動や全体の取り組みに触れる機会が少なく、Patient CentricityとPPIの違いについて議論する機会もありませんでした。
今回の総会では、冒頭に司会進行役の医薬品評価委員会の今枝孝行副委員長より本会の趣旨説明があり、医薬品評価委員会の中路茂委員長の開会挨拶ののち、第一部でNPO法人 愛媛がんサポートおれんじの会理事長の松本陽子氏より「共に『希望』を探すために」、東京大学医科学研究所 公共政策研究分野教授の武藤香織氏より「医薬品と患者・市民参画の重要性」とのテーマでご講演をいただき、第二部で患者団体連携推進委員会、医薬品評価委員会、臨床評価部会、ファーマコビジランス部会および、メディカルアフェアーズ部会の各取り組みを紹介しました。総括として、第三部の総合討論では、第一部、第二部からの新たな気付きを得ての今後の活動方針を議論し、最後は製薬協の石田佳之常務理事のClosing Remarkを経て4時間にわたった総会が終了しました。
第一部(特別講演)
共に「希望」を探すために
NPO法人 愛媛がんサポートおれんじの会 理事長 松本 陽子 氏
松本氏は、愛媛がん患者・家族会おれんじの会の理事長また、全国がん患者団体連合会副理事長なども務めていますが加えて自身も子宮頸がんの抗がん剤治療を経験されたという立場から、講演がありました。
講演の中で松本氏からは、製薬企業は、情報提供にあたって『何を』伝えるかを重要視しているのではないかとの問いかけがありました。『誰のために』を意識し、『どのような情報』を伝えるかが最も重要であり、情報を『読ませる』よりも『見せる』ことで読みたい気持ちに誘導する、平易な言葉で、科学的根拠に基づいた内容を伝え、患者が『わたし』の問題として考え、適切な選択をできるようにすることが求められるとの考えを示しました。
「Patientsは誰?」、「Patientsは数字として丸められるものではなく、一人ひとり異なる」とのメッセージ、読み手の事情が異なる中で正しい情報にたどり着くことの難しさ、読み手の感情にも配慮した情報の見せ方の重要性等、聴講者一人ひとりが深く考えるきっかけとなる講演でした。
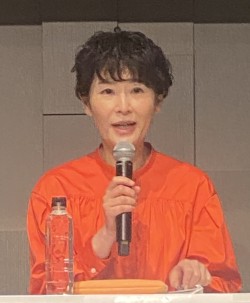
医薬品と患者・市民参画の重要性
東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授 武藤 香織 氏
武藤氏からは、学術的観点から医薬品と患者・市民参画のテーマで示唆に富んだ講演がありました。
冒頭に、患者・市民参画をどのように表現するかについての最新の知見からの説明があり、研究開発での患者・市民参画は「Patient and Public Involvement and Engagement(PPIE)」と表現するとの見解が示されました。
PPIEでは、医薬品の開発プロセスのすべての段階において患者と研究者が協力し、「貴重なご意見をありがとうございました」で終わらせることなく、「Meaningful:意味のある」議論をし、患者さんの声が医薬品開発に反映され、より良い医療サービスの提供の実現につなげることが重要である点について考えを示しました。最後に、今後も患者・市民参画の好事例を積み重ね、医薬品の開発と使用において患者の望む医療の実現を目指していくことが重要とのメッセージで講演が締めくくられました。
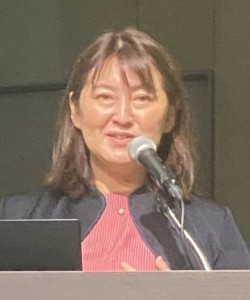
第二部(講演)製薬協の取り組み紹介
患者団体連携推進委員会のPPI推進に向けた取り組み
患者団体連携推進委員会 三澤 賢治 委員長
患者団体連携推進委員会は2012年に発足しましたが、そのベースとなる取組みは1999年にまで遡ります。現在は、患者団体と協働し「患者参加型医療」の実現を目指して、活動することを目的としています。
講演では三澤委員長より、最初に2025年度末のありたい姿や組織体制など委員会の概要についての説明がありました。続いて、ありたい姿に向けた具体的な取り組みが紹介されました。具体的には、「患者団体との協業に関するガイドライン」、「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」の策定、患者団体の意識・活動調査の実施、アドバイザリーボードの設置、患者団体セミナーの開催、ウェブサイトでの情報提供、「臨床試験にみんながアクセスしやすい社会を創る会」の運営サポート、くすりビジョナリー会議の運営サポートなど、非常に多岐にわたる活動が紹介されました。
今回の講演を通じて、患者団体と製薬企業を含むさまざまなステークホルダーによる協働が、より良い医療環境の実現に向けて重要な役割を果たすとのメッセージを述べました。
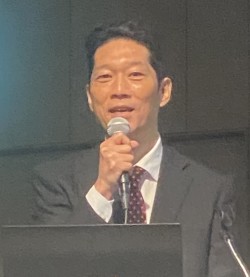
医薬品評価委員会としての取り組み
医薬品評価委員会 中路 茂 委員長
中路委員長は2024年度の活動方針・取り組みの紹介として、医薬品評価委員会でのPPI活動の概要および市民・患者での調査・アンケート結果の説明があり、結果からみる課題として、情報アクセスに関する課題(信頼できる情報にたどりつけない、情報サイトのユーザビリティが低い)、情報コンテンツに関する課題(情報量が足りない、情報が理解しにくい)があることをあげました。つづいて、規制当局の取り組みについて、創薬エコシステムへの取り組みについて、製薬協のウェブサイトについて、SNS(Social Networking Service)を用いた情報公開についての説明がありました。
最後に、これまでの調査結果から、治験情報のアクセスやコンテンツの質に課題があることが判明しており、今後も患者・市民との対話を重視し、情報の提供を改善することで、治験への参加促進と医薬品リテラシーの向上を目指すとの方針が示されました。さらに、国を挙げた創薬力強化とドラッグ・ラグ/ロス解消の取り組みにも貢献することの期待感を述べて講演を締めくくりました。
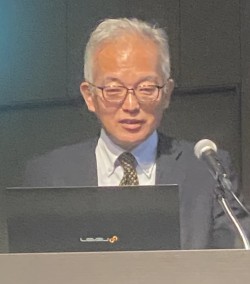
臨床評価部会の活動におけるPPI
医薬品評価委員会 臨床評価部会 松澤 寛 部会長
松澤部会長より、臨床評価部会では「ビジョン2025」を活動方針として定め、その中に患者とともに医薬品開発を進めることを掲げて取り組んでおり、それに向けてのアクションプラン、タスクフォース活動の説明がありました。製薬協医薬品評価委員会臨床評価部会加盟各社のアンケート結果によると、各企業のPPIの取り組み状況の経年変化を見たデータからは、取り組みは進んでいるもののまだ十分ではないという状況の共有がありました。具体的なアクションとして、海外でのDX(Digital Transformation)活用や患者さんに寄り添った治験のためのDCT(Decentralized Clinical Trial)、ICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use:医薬品規制調和国際会議)の新トピックE22「患者選好試験に関する一般指針」の紹介がありました。
最後に、革新的で有用性の高い医薬品をより早く患者さんや医療関係者、世界の人々にお届けするためにPPIを念頭においた活動を継続することを宣言しました。

ファーマコビジランス部会の取り組みと患者安全推進
医薬品評価委員会 ファーマコビジランス部会 宮崎 真 部会長
宮崎部会長より冒頭に、ファーマコビジランス活動の認知向上に向けての取り組みとして、学生向けや医療関係者向けの教科書の執筆活動についての紹介がありました。次に、医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan、RMP)の作成状況の説明のあと、規制で決まっている情報提供のみで患者さんへの情報は足りているのだろうかという問題提起がありました。また、患者さん、医師、薬剤師がどのように安全性情報を得ているのかの分析結果、患者ニーズと医師・薬剤師による説明実態のギャップの検討結果が示され、患者さんが直接企業の情報にアクセスしていることも念頭に、各企業が、提供している情報は患者ニーズを満たしているのか、媒体(デジタル・紙)は適切か、ITリテラシーや疾患に応じた提供のあり方になっているか見直す必要性についても触れました。

メディカルアフェアーズ部会の取り組み
医薬品評価委員会 メディカルアフェアーズ部会 青山 幸司 部会長
青山部会長より、メディカルアフェアーズ部会の活動全般と、患者中心の医療(Patient Centricity)に関する取り組みが紹介されました。製薬協医薬品評価委員会メディカルアフェアーズ部会加盟各社へのアンケート調査によると、多くの製薬企業がPatient Centricity活動に取り組んでいる一方で、実施経験の不足や社内ルールの整備不足といった課題も浮き彫りになっています。これを受けメディカルアフェアーズ部会では、「メディカルアフェアーズ部門が患者を対象とした疾患啓発活動をする場合の注意点」等を事例集にまとめました。
また、患者団体へのインタビュー結果として、情報発信の連続性や患者さんの声を反映した資料作成の重要性なども示唆ました。さらに、患者等を対象とした疾患啓発活動の検討を行っているタスクフォースの活動状況が示されました。
今後の取り組みとして、メディカルアフェアーズ部会は、患者さんが正しい情報を得られる環境を整え、納得して治療を受けられる社会の実現を目指しているとの宣言があり、締めくくりとしました。
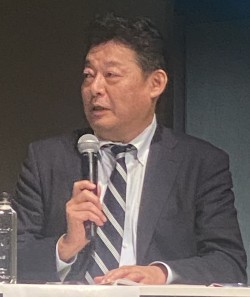
第三部(総合討論)
座長: 製薬協 森 和彦 専務理事、医薬品評価委員会 海邉 健 副委員長
パネリスト:第一部、第二部の演者から、NPO法人 愛媛がんサポートおれんじの会理事長 松本 陽子 氏、東京大学医科学研究所 公共政策研究分野教授 武藤 香織 氏、医薬品評価委員会より臨床評価部会 松澤 寛 部会長、ファーマコビジランス部会 宮崎 真 部会長、メディカルアフェアーズ部会 青山 幸司 部会長の5名
 パネルディスカッション座長
パネルディスカッション座長
製薬協の活動内容について(第二部の発表を受けて)
冒頭に、松本陽子氏と武藤香織氏より第二部の製薬協の活動についてのコメントがあり、全組織で多岐にわたりPPIに関わる活動が行われていることの驚きと、活動を評価するコメントがありました。また、このような取り組みが行われているのであれば、患者と信頼関係を構築し新しい未来が開けることの期待感を抱く一方で、活動内容が十分知られておらず、周知の方法を含めたアピール不足の課題について指摘がなされました。
用語の整理
森和彦専務理事より、「Patient Centricity」という言葉は、患者視点では「祭り上げられるものではない」等違和感を覚えるのではないかとの問題提起がありました。松本陽子氏と武藤香織氏からは、「Patient Centricity」というと、患者が医薬品開発の議論から遠ざけられているように感じる。また、患者の言っていることがすべて正しいわけではないにもかかわらず、すべての意見を取り入れなければならないような印象をうけ違和感を覚えるとコメントがありました。一方、これまで製薬会社が「Physician Center」で活動してきた歴史があり、それに対比する考え方、戒めとして「Patient Center」という気持ちを持って活動するとの意図で「Patient Centricity」を使用しているのであれば、使用することに違和感はないとの考えが示されました。そのうえで、これらの考えとPPIは別のことなので、患者・市民参画という取り組みを表現するのであれば別の言葉を使用していけばよいのではないかとの意見がありました。
今後のPPIの取り組みと医薬品評価委員会で優先すべき課題
今後のPPIの取り組みについては、「共創」や「共に作る:Co-creation」といった新しい概念を浸透させていく提案や、PPIの取り組みと医療専門家の役割のバランスについての議論がありました。
医薬品評価委員会、各部会視点でみた今後優先すべき活動として、目的と対象を明確にしたPPIの取り組みの必要性、より患者さんに寄り添った情報提供と治療選択肢の検討につながる情報提供のありかた、継続的な患者さんとの真の協働の重要性、臨床試験設計に対する患者さん視点の反映、製薬協内でのコミュニケーションや協業の促進の必要性等にも話がおよびました。
製薬企業と患者とのコミュニケーション
製薬企業と患者さんとのコミュニケーションはどうあるべきかとの問いは引き続き課題となっています。この点について、企業と患者さんの立場の違いを認識しつつ、シームレスな関係構築が重要であること、一方向の情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションが必要であることがあげられ、規制の範囲内で、より気負わずに参加できる開かれたディスカッションの場(車座での開催など)を設けることが提案されました。製薬企業が患者さんの意見を聞いて開発計画するためには、普段から製薬企業と患者さんが対話を継続していることが重要であること、さらに、患者側の薬の開発プロセスへの理解を深める必要性、患者団体とのコミュニケーションだけでなく、より広い患者層との接点を作る必要性もあるとの意見が出されました。これらの解決のための方策として、AI(Artificial Intelligence:人口知能)の活用、患者個人と製薬企業のマッチングの場の開発、常設パネルの設置、企業内の患者さんの意見の活用等の発案がなされました。
製薬企業側からの情報提供
製薬企業側からの情報提供については、冒頭にあった製薬協の活動が十分に認知されていない課題やさまざまな患者ニーズに対応するため、多様な視点からの情報提供が必要である点を踏まえた改善が必要であるとの認識が確認されました。
以上、1時間にわたる総合討論は、今後の医薬品評価委員会の活動に生かすべき多くの気づきを得て終了しました。
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子
文責:医薬品評価委員会 運営幹事 岡安 綾子

