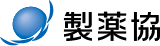くすりの情報Q&A Q5.現在使われているくすりの基礎は、いつごろ築かれたのでしょうか。
回答
近代のくすりの多くは、20世紀前半に基礎が築かれました。天然素材(植物・動物・鉱物など)に含まれる有効成分を抽出し、化学的に変化を加えたり、同じ成分を化学合成することによって、つくられています。
解説
医学の父とされる古代ギリシャのヒポクラテスは、ヤナギの皮や枝から鎮痛薬(ちんつうやく)をつくったと伝えられています。
やがて19世紀になると、その効用に注目したある学者が、カワヤナギの葉や小枝を化学的に分析した結果、サリチル酸が得られました。サリチル酸こそ、鎮痛・解熱(げねつ)作用の有効成分だったのです。
サリチル酸は、のちにリウマチの治療にも盛んに利用されましたが、同時に胃腸障害などの強い副作用が現れました。そこでサリチル酸の副作用を抑(おさ)える研究がおこなわれ、その結果、化学的に変化を加えて化学合成されたくすりが、鎮痛薬としてよく知られるアセチルサリチル酸(アスピリン)です。
近代のくすりの開発には、このように副作用を減らし、効果を高めていくような化学的な研究が寄与(きよ)しており、くすりの開発は近代化学の発展に大きな貢献を果たしてきたといえます。
同様の化学的な手法により咳(せき)や下痢(げり)を止めるコデイン(原料植物=ケシ)、痛風(つうふう)の発作(ほっさ)やベーチェット病の治療薬コルヒチン(原料植物=イヌサフラン)、瞳孔(どうこう)を広げたり、胃けいれんを抑えるアトロピン(原料植物=ハシリドコロ)、強心薬のプルプレア配糖体(原料植物=ジギタリス)、抗アレルギー作用を持ち、咳を鎮(しず)めるトラニラスト(原料植物=ナンテン)など、数多くのくすりが植物からつくられました。
19世紀末から20世紀初頭には、ヨーロッパでパスツールやコッホらによる細菌学が勃興(ぼっこう)しました。
パスツールはワクチンによる予防接種の方法を開発し、狂犬病ワクチンなどを発明しました。一方のコッホは、炭疽菌(たんそきん)や結核菌、コレラ菌を発見、その後の化学、医学、薬学の発展に大きく貢献しました。
国内では、1873年(明治6年)に、政府の援助を得て、日本最初の製薬会社「大日本製薬会社」が設立されました。
また大阪でも、薬種卸仲買商(やくしゅおろしなかがいしょう)の仲間によって1888年(明治21年)に「大阪薬品試験会社」が設立、さらに道修町(どしょうまち)の有力な薬種問屋が中心となって1897年(明治30年)には「大阪製薬株式会社」が設立されました。
当初は輸入薬が中心で、国産のくすりは事業としてはあまり奮いませんでした。しかし、1914年(大正3年)に起こった第一次世界大戦により、海外からのくすりの輸入が困難となって外国のくすりの価格が高騰(こうとう)したため、くすりの国産化の必要性が高まり、モルヒネ、アスピリン、サリチル酸などの重要なくすりの研究と製造が本格的に開始されたのです。
日本の製薬産業は、その後も紆余曲折(うよきょくせつ)を経(へ)ながら著しい発展を遂とげ、くすりの開発の基盤となる化学研究の分野において、日本は先進国である欧米のレベルに急速に追いついていきました。
図表・コラム
5|生薬標本
植物をはじめ、動物、鉱物がくすりとして収集され、管理されています。

出典:内藤記念くすり博物館蔵