トップニュース 「第13回 アジア製薬団体連携会議(APAC)」を開催 —ミッション:革新的な医薬品をアジアの人々に速やかに届ける—
2012年より開催しているアジア製薬団体連携会議(Asia Partnership Conference of Pharmaceutical Associations、APAC)は2024年で13回目を迎えました。今回は“We reaffirm the APAC’s mission and fulfill it for patients in Asia”をテーマに、4月23日にハイブリッド形式で開催しました。カンファランスとして600名を超える参加者のうち、およそ6割が海外からの参加でした。医薬品ライフサイクルにおける創薬、申請・許認可に係る規制、医薬品アクセス向上への課題解決のための5つのSessionと特別講演1題を含む盛りだくさんな構成となりました。
 APAC関係者一同
APAC関係者一同
はじめに
APACカンファランスの発表資料をAPACのウェブサイトに掲載しています。ぜひこちらもご参照ください。
APAC:https://apac-asia.com/achievements/13th_apac.html
以下、当日のプログラムに沿って報告します。
Opening Remarks要旨
製薬協の上野裕明会長はOpening Remarksとして、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの経験から多くのことを学びました。その中で重要なことは、世界が抱えるこのような問題を一国で解決することは難しく、よりいっそうの国際協力や連携が求められる時代に突入したということです。特に、アジア諸国の人々の健康に貢献するために、APACの活動が今後重要になってくると考えています。COVID-19の流行後、平時からのパンデミックへの備えの重要性の認識、一部の国における高齢化の進展、新たなモダリティの実用化、人工知能を含むIT・デジタル技術の急速な発展、医療保険の厳しい状況等、ヘルスケアと製薬業界を取り巻く環境は大きく急速に変化しています。このような環境下、製薬協はAPACのミッションである“革新的な医薬品をアジアの人々に速やかに届ける”を掲げ、その実現に向けて努力を続けています。2024年のAPACのテーマは“APACのミッションを再確認し、アジアの患者さんのためにそのミッションを果たす”です。このミッションの達成に向けた共通の目標を再確認し、各ワーキンググループにおいて、関連するトピックについて議論していきます」と挨拶しました。

製薬協 上野 裕明 会長
 IFPMA事務局長 David Reddy 氏
IFPMA事務局長 David Reddy 氏祝辞・基調講演要旨
2024年4月より、Medicines for Malaria VentureのCEOから新たに国際製薬団体連合会(IFPMA)事務局長に就任したDavid Reddy氏より祝辞がありました。Reddy氏は、“Recent developments in Japan”“Industry as a trusted partner and key enablers”“Working together for faster access”をキーワードに、APACとの今後の連携を楽しみにしていると述べました。
 PMDA理事長 藤原 康弘 氏
PMDA理事長 藤原 康弘 氏続いて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)理事長の藤原康弘氏による基調講演がありました。“Promoting Access to Better Innovative Drugs”と題し、PMDAの第5期中期計画(2024年度~2028年度)、革新的な医薬品へのアクセス改善に向けたPMDAの取り組み、PMDAのアジアにおける国際協力について話しました。医薬品のアクセス改善に向けた取り組みでは、日本のドラッグ・ロスの現状を踏まえ、厚生労働省による「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」の取り組みから、PMDAによる「小児・希少疾病用医薬品等薬事相談センター」の構想、「再生医療等製品のコンサルテーション」「薬事制度に関する海外への情報発信」について説明しました。また、アジアにおける国際協力については、アジア医薬品・医療機器トレーニングセンターの活動や、タイ・バンコクでのアジア拠点の設置等を紹介し、国際協調とリライアンスの重要性について言及しました。
RA(規制・許認可)セッション
 RAセッションの登壇者
RAセッションの登壇者
規制・許認可を取り扱うRAセッションでは、セッションチェアとしてPMDA執行役員の安田尚之氏とIFPMAのJanis Bernat氏を招待し、「国際協力を通したさらなるリライアンススキームの推進」をテーマとして採り上げました。ここで紹介するリライアンスとは、各国の医薬品規制当局間がお互いを信頼して協力しながら医薬品の承認審査を効率的かつ迅速に推進することで、世界中の人々に速やかに医薬品を届けることにつながることが期待されます。
RAセッションでは、2019年第8回において世界保健機関(WHO)が推奨するリライアンスコンセプトの紹介を採り上げてから、日本の医薬品承認をアジアの国が参照する2国間リライアンス等の事例紹介を含めた議論を推進してきました。そこで、2024年はリライアンスコンセプトをさらに発展させるため、国際協力のもと、複数の国が共同で医薬品承認審査を推進する取り組みの重要性をセッショントピックとして採択しました。アジアにおいて複数国にまたがる医薬品共同審査としては、WHOと東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国が推進するASEAN共同審査が、2017年から複数の医薬品審査の経験を積み重ねており、APACに参加するアジア各国の医薬品規制当局や製薬業界と取り組みを共有する良い機会となりました。
ASEAN共同審査推進の中心を担うWHOのMarie Valentin氏と、ASEAN共同審査コーディネーショングループ長でマレーシア当局のAzuana Ramli氏は、ASEAN共同審査の背景、実績、今後の展望等を幅広い観点から紹介しました。加えて、インドネシア当局のRia Christine Siagian氏およびフィリピン当局のJesusa Joyce N. Cirunay氏は、ASEAN共同審査を活用した自国における新薬審査・承認の具体的な事例を共有しました。
続くパネルディスカッションでは、製薬業界代表としてシンガポール製薬団体のKC Wong氏にも参加をお願いし、すべての登壇者により有意義な議論を推進しました。活発なパネルディスカッションの成果として、ASEAN共同審査による医薬品の審査と承認は多国間協力による医薬品審査の効率性を明らかに示していること、製薬業界はASEAN共同審査に自社製品を申請することで複数の国にまたがる効率的な審査のベネフィットを期待できることを、セッション参加者全体と確認することができました。また、WHOがASEAN共同審査設立・推進において大きく寄与していることも広く周知されました。改めて、われわれがアジアのリライアンス推進に取り組んできた意義につながる、とても重要なセッションとなりました。
DA(創薬連携)セッション
DA-EWGは、「アジア各国の人々のために、アジアの国々が協力して、アジア発の革新的な医薬品を創出する」というアジアにおける創薬連携の推進を目標に、(1)創薬シーズの情報共有、(2)創薬プラットフォームの構築、(3)次世代を担う研究者の育成を進めています。
2023年までは、主にアジアにおける創薬シーズの情報共有推進を目的とする取り組み(Drug Seeds Alliance Network in Asia、DSANA)と、天然物の創薬活用の推進と人材育成を目的とする取り組み(天然物創薬コンソーシアム(APAC Natural Product Drug Discovery Consortium、ANPDC))の2つの活動を進めていました。ANPDCは、2023年度をもって5年間の活動を終えましたが、日本の製薬企業2社が参加し、タイの研究機関と連携した若手人材育成と創薬スクリーニング技術移譲、その技術を使用したタイ現地での天然資源スクリーニングを実施することができました。DSANAは、これからも引き続き、アカデミア、スタートアップ企業、製薬企業を対象に、台湾-日本間の情報共有と双方向の創薬連携推進に取り組んでいきます。
DA-EWGは、2024年からマイクロバイオーム研究を採り上げることにしました。マイクロバイオームは日本や台湾でもコンソーシアムが設立される等、アジアで活発に研究が進められています。特に、腸内のマイクロバイオームは健康や病気にも影響を与えていることが明らかになり、病気の発症メカニズム解明や予防・治療法の開発、ヘルスケアへの貢献が期待されています。
APACカンファレンスのDA-EWGセッションでは、日本と台湾それぞれのマイクロバイオームコンソーシアムのリーダーである、一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム(JMBC)運営委員長の寺内淳氏とTaiwan Microbiota Consortium(TMC)PresidentのChun-Ying Wu氏が登壇し、アジアでのマイクロバイオーム研究と創薬、さらには、その将来性について紹介しました。30分という短いセッションにもかかわらず、講演後、会場参加者から数多くの質問があり、マイクロバイオーム研究への注目の高さを実感しました。
 JMBC運営委員長 寺内 淳 氏
JMBC運営委員長 寺内 淳 氏
 TMC President Chun-Ying Wu 氏
TMC President Chun-Ying Wu 氏
DA-EWGでは今後も、マイクロバイオームの創薬研究における可能性と課題に注目し、アジア各国のアカデミア、スタートアップや製薬企業のマイクロバイオーム研究とその創薬応用の推進に貢献していきたいと考えています。
e-labelingセッション
 e-labelingセッションの登壇者
e-labelingセッションの登壇者
e-labelingのセッションは、「デジタルヘルスのためのアジアe-labeling戦略 ~今、すべきこと、そして将来すべきこと~」をタイトルとして、アジア地域におけるe-labelingの取り組みの現状と将来について議論しました。
はじめに2023年に合意した2023年度の活動のコミットメントに対する進捗として、下記の3点が報告されました。
| 1) | APAC e-labeling EWGは、アジア地域のe-labelingの取り組みに貢献し、2023年までに8マーケットにおいてe-labelingのガイダンスが発出されたこと |
| 2) | 第2回APAC e-labeling規制当局ワークショップを2023年10月に開催し、11規制当局から140名以上が出席してe-labelingの進捗やベストプラクティス、課題を共有したこと |
| 3) | 日本で立ち上げたコンソーシアムは、医療情報を電子的に交換するための国際標準であるHL7 FHIRに準拠した形式のe-labelingの利用についてのパイロット試験計画を作成し、実現に向けて検討していること |
その後、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課安全使用推進室室長の大久保貴之氏から、日本の医療デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みと、患者さんへの医薬品情報提供について共有されました。マレーシア当局のAzuana Ramli氏からは、2023年4月にe-labelingのガイダンスを発出し、2026年12月31日まで任意によるe-labelingの実施を継続し、その後、再度e-labelingの実装について検討することが説明されました。台湾当局のPo-Wen Yang氏は、e-labelingのデジタル化、標準化、ペーパーレス化を推進しており、2023年末までに台湾当局のプラットフォームにおいてe-labelingのXMLの実装が完了したこと、2022年に開始したペーパーレス化のパイロットの状況、2024年にHL7 FHIRをe-labelingに導入予定であることを述べました。インドネシア当局のRita Endang氏から、2023年9月にパイロットのガイダンスを発出し、インドネシア当局のトラックアンドトレースのアプリで、2Dバーコードをスキャンし、インドネシア当局のウェブサイトからPDFとして入手できることが説明されました。韓国当局のYeonhae Han氏からは、2024年1月に薬事法を改正し、指定薬剤については電子的にラベリングが提供可能となっており、また、2022年12月にe-labelingのガイダンスを発出し、パイロット試験を進めていると報告がありました。
パネル討論では、上記5名に加え、フィリピン当局のJesusa Joyce Cirunay氏、タイ当局のWorasuda Yoongthong氏、ベトナム当局のLuong Thu Vinh氏もパネリストに加わり、今後3~5年後にe-labelingのどの分野に取り組んでいくかについて議論しました。フィリピンではコロナ禍対応としてe-labelingと同等のスマートラベリングを実施した経験があり、実装ガイドラインを2025年初頭までに発出したいとの意向が示されました。ベトナムでは、ロードマップを作成してパイロット試験を実施し、その結果を実装に活かし法改正したいとのことでした。台湾では、Ministry of Health and WelfareがHL7 FHIRを推奨しており、相互運用性の観点からe-labelingにHL7 FHIRを導入する予定であると言及がありました。一方、タイでは2024年度中にXMLへの移行を考えているが、将来的にはヘルスケアシステムと同様の国際標準を導入し、国際連携を図っていくことが重要と説明がありました。また、マレーシアからは、e-labelingの取り組みにおいては、患者さんが最も重要なステークホルダーだとコメントがありました。
最後に、下記の4点をまとめとし、セッションを締めくくりました。
| 1) | アジア地域のe-labelingへの取り組みの多くは、製薬企業が自主的に実施しており、今後はより多くの製薬企業、より多くの製品におけるe-labelingの導入を推進していくこと |
| 2) | 国際標準であるHL7 FHIRを用いた、構造化されたe-labelingの議論について、導入も視野に入れながら議論を進めること |
| 3) | 約30%程度のマーケットでしか患者さん向けのラベリングが作成されていないことから、今後は患者さん向けのe-labelingの導入推進の重要性について議論していくこと |
| 4) | 今後もe-labelingサーベイを実施し、e-labeling普及状況の推移を確認すること |
MQSセッション
 MQSセッションの登壇者
MQSセッションの登壇者
MQSセッションでは、APACのゴールであるAccess To Innovative Medicines(ATIM)を達成するため、製造・品質・サプライに関するテーマについて、協議を行っています。
2019年に発生したCOVID-19の流行により、医薬品のサプライチェーンは多大な影響を受けました。医薬品の安定供給は、薬を必要としている患者さんに対する製薬企業の責務ですが、感染症の拡大や気候変動による自然災害等、サプライチェーンが機能を失う事象の発生は今後も予想されます。有事の際にサプライチェーンを維持するための課題について、APACメンバーおよび製薬協会員会社にアンケートを実施した結果、セカンドサプライヤーの確保が最も重要であることがわかりました。そこで、MQSではセカンドサプライヤー追加手続きの迅速化をテーマとして、協議を行いました。
スピーカー/パネリストとして、マレーシア当局のNur‘Ain Shuhaila氏、タイ当局のChaiporn Pumkam氏、日本からはPMDAの奥平真一氏を招き、マレーシア、タイからはCOVID-19流行下での医薬品供給を維持するために実施した有用な事例、PMDAからはInternational Coalition of Medicines Regulatory Authorities(ICMRA)でのPQ KMSの取り組みが紹介されました。
事例紹介を受け、パネルディスカッションでは、(1)緊急時において、原材料の製造サイト変更が製剤品質に影響を与える可能性がある場合、規制手続きを迅速化するために規制当局で検討できる措置、(2)ICMRAの取り組み、(3)緊急時に安定供給を確保するための最も大きな課題と、規制当局および業界における効果的な対策に関して、パネリストから貴重な意見が述べられました。セカンドサプライヤー追加に必要なデータをリスクに基づいて判断することで、手続きを迅速化できる可能性が示唆されました。
最後に、PMDAの奥平真一氏から、まとめとして下記3点が報告され、セッションは終了しました。
| 1) | COVID-19パンデミック下での医薬品供給を確保するための有益な事例が共有された |
| 2) | 緊急事態に備えるためには、安全性と品質を確保したうえで、セカンドサプライヤー追加プロセスの迅速化が必要 |
| 3) | 提言された対策を国際調和の取り組みと連携しながら、医薬品の安定したサプライチェーンの実現に向けた検討の継続が必要である |
aUHC(アジアのUHC)セッション
 aUHCセッションの登壇者
aUHCセッションの登壇者
本セッションは、aUHC(Asia Universal Health Coverage)をテーマとして2022年より3回シリーズで企画しており、各国の社会保障制度・UHCの構築に向けたナレッジの共有を通じて、アジア各国における革新的医薬品へのアクセス改善を目的としています。
第1回の2022年は、コロナ禍によってその重要性が再認識されることとなったUHCの強靭性・持続性の重要性に関して議論され、これを実現するためには必要な財源の投入(Financing)が重要であると結論づけられました。
第2回の2023年は、Financingをテーマとして、各国・地域の異なる状況を踏まえたUHCのあり方と現状のギャップ、そのギャップを埋めるための対応策について議論され、公的保険が果たす役割やカバーする対象、財源等についての考え方が共有されました。
3回シリーズの最終回となる2024年は、「すべての医薬品を公的保険でカバーすべきか、できるのか」をディスカッションテーマとしてセッションが行われました。
今回は、Opening Presentationとして、ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー、内閣官房健康・医療戦略室政策参与の武田俊彦氏より、公的保険で保健医療サービスを受けられる重要性、また日本で問題視されているドラッグ・ラグ/ロスの問題解消に向けた検討である「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」での取り組みの紹介がありました。
それに続き、マレーシア ProtectHealth CorporationのMuhammed Anis Bin Abd Wahab氏、台湾National Health Insurance Administration(NHIA)Deputy Director GeneralのCheng-Hua Lee氏より、それぞれの地域でのUHC達成状況、保険医療財政における現状と問題点について共有されました。
その後、3名の登壇者により、公的保険の必要性と、公的保険でカバーできない場合どのような選択肢があるか、民間保険の活用の可能性に関して議論を行いました。Muhammed Anis Bin Abd Wahab氏、Cheng-Hua Lee氏の両氏から、国民からの税金で大半のヘルスケアサービスがカバーされているが、すべての医薬品が公的保険でカバーされていない現状の課題に関して話がありました。また、公的保険でカバーできない場合の選択肢としての民間保険の活用については、保険料等の課題があり、低所得者層では加入者に対する問題もあって、有効活用できる選択肢として考えるには多くの課題があると結論づけられました。そのほか、行政による費用抑制を進めると製薬・ヘルスケア業界からの投資が減少することにつながり、一般市民により良い医療を提供することができなくなる懸念も示されました。そういった中で、規制を緩和することで、製薬・ヘルスケア業界から投資をしてもらえるような取り組みも必要であるといった意見も交わされました。
セッションの最後には、医薬品をはじめ、国民により良い医療を届けるためには財源が必要であり、日本の公的保険に対する取り組みはアジア各国・地域の参考になるといった意見もあり、日本がこの分野でリードしていく重要性が示唆されました。
特別講演
これまでのaUHCセッションへの登壇でおなじみの厚生労働大臣の武見敬三氏より、“Japan’s global health commitment: Domestic health reform & UHC knowledge hub”と題し、特別講演がありました。
保険分野における4つの新しい取り組み、(1)医療DXの推進と管理・運営母体、(2)国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security、JIHS)の創設、(3)官民共同の創薬複合体による先端医薬品の開発、(4)途上国の健康医療政策を支援する「UHCナレッジハブ」の日本設置について紹介しました。カンファランス時点では公表されていない内容を含んでいたため、聴講者の関心も高く、公開不可となっていた資料の提供要請が複数からありました。
(1)では、マイナンバーカードへの保険証統一に加え、電子処方箋導入や全国規模の患者データ利用プラットフォーム、都道府県別医療機関別各種プログラムの統一、保険償還システムのグレードアップ等についてのロードマップを提示しました。
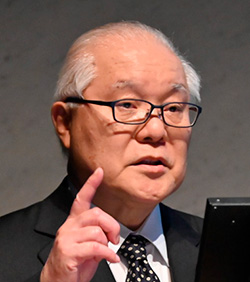
厚生労働大臣 武見 敬三 氏
(2)では、総合危機管理局を中心とした5つの部門(総合危機管理局、総合研究開発支援局、医療提供支援局、人材育成局、システム基盤整備局)を2025年4月に設置する組織運営計画を説明しました。
革新的新薬開発にはアカデミア、スタートアップ、製薬企業の連携が不可欠で、世界的にも水平分業が見られる今日において、日本におけるクラスターキャンパス導入が不十分な現状に鑑みて(3)を進めていくこと、最後に(4)として、世界銀行およびWHOと連携して低中所得国の金融当局や保健当局のUHCおよび人材育成に関する知識と経験のサポートを目的に、2025年に日本で「UHCナレッジハブ」を開設予定との説明がありました。
 製薬協 国際委員会 村上 伸夫 委員長
製薬協 国際委員会 村上 伸夫 委員長閉会にあたって
APAC運営責任者で製薬協国際委員会の村上伸夫委員長より、カンファランスのWrap-up(まとめ)がありました。
 製薬協 眞鍋 淳 副会長
製薬協 眞鍋 淳 副会長また、Closing Remarksとして、製薬協の眞鍋淳副会長が総括し、「COVID-19パンデミックを経験して、世界中が“健康”こそが社会・経済の基盤であることを認識しました。また、世界には、感染症だけでなく、まだわれわれが医薬品やワクチンを届けるべきアンメット・メディカル・ニーズは残っています。その課題解決に向け、産学官がそれぞれの強みを発揮するとともに、製薬産業は創薬イノベーションの発揮によりその責務を果たさなければならないと改めて強く意識しています。APACも世界からの期待に応え、さらに有益な提案と信頼関係の構築を進めるためのプラットフォームとして進化していくよう、皆で力を合わせていきましょう」として、第13回APACのカンファランスを締めくくりました。
(国際連携部長 八尋 勇治)

