トピックス 「CMC Strategy Forum Japan 2022」が開催
2022年12月5~6日の2日間にわたり、CASSS(California Separation Science Society)主催の「CMC※1 Strategy Forum Japan 2022」が開催されました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がいまだ収束しないこともあり、2020年、2021年と同様にオンライン開催となりましたが、日本だけでなくアジア、北米、欧州等10ヵ国から約100名の参加登録があり、活発に意見が交わされました。
-
※1CMC:Chemistry, Manufacturing and Control。医薬品製造および品質を支える統合的な概念
CMC Strategy Forum Japan開催の経緯
CMC Strategy Forumは2002年にWCBP(Well Characterized Biotechnology Pharmaceutical)シンポジウムから独立し、米国で第1回が開催された後、2007年から欧州、2012年から日本、2014年からラテンアメリカ、そして2021年から中国でも継続して開催されています。CMC Strategy Forumでは、企業、アカデミア、および規制当局の専門家がバイオ医薬品のCMCについての研究開発、製造、規制等に関する課題に関して、十分に時間をかけて議論を行い、相互理解と課題解決を促進しています。
日本でのCMC Strategy Forumは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)と製薬協で準備委員会を組織し、テーマの選定や議論の方向性を決めるだけでなく、2022年はオンラインならではの学会運営も含め、約1年をかけて準備を行ってきました。
会の開催に際し、CASSSのFellow、CMCフォーラムグローバル諮問委員会議長を務めるRoche社のWassim Nashabeh氏とPMDAレギュラトリーサイエンスセンター長の鈴木洋史氏からのwelcome commentの後、以下のテーマで議論が開始されました。
-
・Session 1:Recent Trends in the Regulation of Biopharmaceutical Products
-
・Session 2:Stability of Biopharmaceutical Products: Topics about ICH Guideline Q1/Q5C Revision
-
・Session 3:Visible Particles - Mechanism and Mitigation of the Formation and the Control Strategy
-
・Session 4:Viral Safety of Biotechnology Products - Changing the Regulatory Landscape, Modalities and Analytical Technologies
-
・Session 5:Cell & Gene Therapy Products - Showcase both Regulatory and CMC Issues via Case Studies and Recent Challenges Toward Solving Regulatory Issues in Japan
 CASSS Fellow
CASSS Fellow
CMCフォーラムグローバル諮問委員会
議長 Wassim Nashabeh 氏
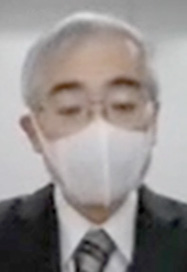 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
レギュラトリーサイエンスセンター長
鈴木 洋史 氏
Session 1:Recent Trends in the Regulation of Biopharmaceutical Products
Session 1では、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授の内田和久氏とGenentech社のCecilia Tami氏の司会のもと、各国の規制当局担当者から、バイオ医薬品を中心とした最近の薬事規制動向、COVID-19パンデミック下における緊急対応等、幅広い内容が紹介されました。
PMDA再生医療製品等審査部の岸岡康博氏からは、日本におけるバイオ医薬品承認申請の最近のトレンド、ICH Qパートの改訂状況、COVID-19パンデミックを通して得られた教訓について紹介がありました。
中国国家薬品監督管理局(National Medical Products Administration、NMPA)中国国家医薬品監督管理局医薬品審査センター(Center for Drug Evaluation、CDE)のMi Li氏からは、中国の医薬品承認申請における法律や規制の全体像、バイオ医薬品に対する行政規制、審査期間短縮に向けた取り組み、緊急時におけるワクチン審査について紹介されました。
米国食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA)生物製品評価研究センター(Center for Biologics Evaluation and Research、CBER)のIngrid Markovic氏からは、承認申請書の文書体系に関する近代化(KASA、eCTD&M4Q(R2)、PQ/CMC)について、またRobin Levis氏からは、ワクチン開発における緊急事態使用許可制度(Emergency Use Authorization、EUA)から生物学的製剤承認申請(Biologics License Application、BLA)に向けた対応について紹介がありました。
欧州医薬品庁(European Medicines Agency、EMA)のVeronika Jekerie氏からは、革新的な製造方法やモダリティへの取り組みやサポート体制、EUにおけるツールボックスガイドラインの整備、規制当局間のコラボレーション等について紹介がありました。
パネルディスカッションではCDEのWu He氏も加わり、COVID-19パンデミック下におけるバイオ医薬品の迅速な承認審査等に関する薬事的改善や規制当局間のコラボレーション、革新的製造方法やニューモダリティへの対応、承認申請資料のさらなる近代化、ICH Q12におけるEstablished Conditionの考え方の調和、Biosimilar製品のSimilarity評価に関する調和等について活発な議論が展開されました。
 パネルディスカッションの様子(Session 1)
パネルディスカッションの様子(Session 1)
Session 2:Stability of Biopharmaceutical Products: Topics about ICH Guideline Q1/Q5C Revision
Session 2では、国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部の柴田寛子氏とGenentech社のTura Camilli氏の司会のもと、安定性ガイドラインQ1/Q5C改訂に関連する幅広い内容が紹介されました。
PMDAワクチン等審査部の亀田隆氏からは、Q1/Q5C運用における現状の課題、2022年11月に署名されたコンセプトペーパーの概要、そして、改訂に向けた議論のポイントが紹介されました。
Genentech社のBoris Zimmermann氏からは、安定性に関するprior/platform knowledgeの活用や、科学およびリスクベースアプローチについて、事例紹介も踏まえながら説明がありました。
 国立医薬品食品衛生研究所
国立医薬品食品衛生研究所
生物薬品部 柴田 寛子 氏
Amgen社のAndrew Lennard氏からは、prior knowledgeを用いた安定性予測、具体的には、「like-molecules」からの安定性データのプーリング、ベイズ統計学の活用、AIによる機械学習モデル等の方法論が提示されました。
パネルディスカッションでは中外製薬の大村武史氏も加わり、ICH Q1/Q5Cの改訂における規制当局や業界の立場からの期待や解決すべきポイント、安定性モデリングによる保存期間設定におけるメリットと課題、連続生産における安定性バッチの選定等について活発な議論が展開されました。
 パネルディスカッションの様子(Session 2)
パネルディスカッションの様子(Session 2)
Session 3:Visible Particles - Mechanism and Mitigation of the Formation and the Control Strategy
Session 3では、国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部の石井明子氏とRoche社のChristof Finkler氏の司会のもと、バイオ医薬品の内因性の不溶性異物に関する幅広い内容が紹介されました。
PMDA再生医療製品等審査部の岸岡康博氏からは、日本における不溶性異物に関する規制に関する説明が行われた後、PMDAの審査においてバイオ医薬品の内因性の不溶性異物が課題となった実例について紹介がありました。
中外製薬の齋藤智氏からは、バイオ医薬品中のタンパク質が界面上のストレスにより不溶性異物発生のトリガーとなり得ることが説明され、添加剤(ポロクサマー188)の不溶性異物の低減効果やケーススタディーについて紹介がありました。
Janssen社のKlaus Wuchner氏とNovartis社のKaroline Bechtold-Peters氏からは、欧州製薬団体連合会(EFPIA)のワーキンググループが添加剤(ポリソルベート)の変性や管理戦略について製薬会社16社へアンケートを取った結果が紹介されました。また、不溶性異物に係る技術的課題が示され、薬事的課題についての提言も示されました。
 国立医薬品食品衛生研究所
国立医薬品食品衛生研究所
生物薬品部 石井 明子 氏
パネルディスカッションでは、Health CanadaのAntonia Pandelieva氏が加わり、バイオ医薬品の不溶性異物について議論が行われました。特にバイオ医薬品の内因性の不溶性異物について、その発生メカニズム、分析法および管理戦略について、当局・企業間の活発な議論が行われました。
 パネルディスカッションの様子(Session 3)
パネルディスカッションの様子(Session 3)
Session 4:Viral Safety of Biotechnology Products - Changing the Regulatory Landscape, Modalities and Analytical Technologies
Session 4では、国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部の佐藤陽治氏とNovo Nordisk社のAndrew Chang氏の司会のもと、Step 2に到達したICH Q5A(R2)ガイドライン案が紹介された後、当局、抗体医薬品や遺伝子組み換えウイルスベクター等の製品開発企業、およびウイルスクリアランス試験を担う医薬品開発業務受託機関(CRO)と多様なステークホルダーの観点から、ウイルスクリアランス戦略やウイルス安全性評価における改訂ガイドラインへの期待や課題が議論されました。
PMDAのスペシャリスト(バイオ品質担当)の櫻井陽氏からは、ICH Q5A改訂の背景や基本原則の紹介の後、新たに改訂ガイドラインの対象となる製品タイプや連続生産における留意事項、新しい試験法やPrior Knowledgeの活用といった、主な変更点および基本的な考え方について説明がありました。
中外製薬の小林祥平氏からは、開発段階に応じたモジュラーアプローチの活用やモデルウイルス選択等のウイルスクリアランス戦略について紹介がありました。また、Prior Knowledgeの活用について改訂ガイドラインへの期待や提言が示されたとともに、高機能抗体の製造や連続生産プロセスにおける取り組みについても紹介されました。
Janssen Vaccines & Prevention B.V.社のGilles Chenard氏からは、アデノウイルスベクター製造におけるプラットフォームプロセスやウイルス安全性に係る管理戦略が紹介された後、新たに改訂ガイドラインの適用対象となる遺伝子組み換えウイルスベクターおよびウイルスベクター由来製品の観点から、Prior Knowledgeの活用やウイルス管理戦略についての期待や提言が示されました。
メルク社(BioReliance)の増田宗久氏とHuixing Feng氏からは、改訂ガイドラインがウイルスクリアランス試験管理戦略へ与える影響についての解説に続き、分子生物学的なウイルス試験法の原理や仕様等の具体的な紹介がありました。
パネルディスカッションでは、Health CanadaのChristopher Storbeck氏と協和キリンの杉原努氏が加わり、聴衆から寄せられた多くの質問を端緒にして、Prior Knowledge活用への期待や解決すべき課題、次世代シーケンサー等の分子生物学分析法へ代替の考え方、連続生産におけるスケールダウンモデル活用の留意点等について、活発な議論が展開されました。
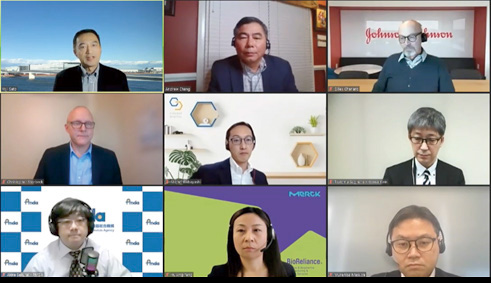 パネルディスカッションの様子(Session 4)
パネルディスカッションの様子(Session 4)
Session 5:Cell & Gene Therapy Products - Showcase both Regulatory and CMC Issues via Case Studies and Recent Challenges Toward Solving Regulatory Issues in Japan
Session 5では、国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部の佐藤陽治氏とParexel社のChristiane Niederlaender氏の司会のもと、細胞治療製品および遺伝子治療製品について開発から市販後にわたる諸課題が企業から共有され、再生医療等製品の申請資料の品質パートの記載要領、および日本における遺伝子組み換え生物(Genetically modified organism、GMO)に関する規制についてPMDAより紹介されました。
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.社のYoko Momonoi氏からは、同種細胞治療製品における製造設計と管理が複雑であり、各国の規制当局の要求が異なることから、しばしばグローバル戦略を展開するうえで課題となり、リスクベースアプローチが重要であることが紹介されました。
ノバルティスファーマの北田允男氏と花田直之氏からは、細胞・遺伝子治療製品の開発経験をもとに、開発および上市後のCMCの観点から、カルタヘナ法、海外製造品の国内試験、および上市品の変更管理における承認後変更管理実施計画書(Post-Approval Change Management Protocol、PACMP)の活用の3点を中心に課題と留意点が紹介され、課題解決に向けた提案がありました。
PMDA再生医療製品等審査部の西川淳史氏からは、再生医療等製品の申請資料、特に品質パートの構成についてガイドラインや通知がなく、申請者がそれぞれの考えで申請資料を作成しており開発者が抱える課題の一つとして浮かび上がっている現状が紹介されました。そのうえで、再生医療等製品の品質パートの申請資料の構成について、規制当局の審査官の立場から解説されました。
PMDA再生医療製品等審査部の神崎誠一氏からは、日本における遺伝子組み換え生物に関する薬事規制について解説され、近年のカルタヘナ法運用改善について紹介されました。
ファイザーR&Dの田島玄太郎氏からは、GMOに関する規制、特に環境影響評価の日米欧の違いや審査プロセスの特徴が解説され、日本のさらなる規制の改善に向けた提案がされました。
パネルディスカッションでは、アストラゼネカの近藤涼氏とHealth CanadaのLeslie Nash氏が加わり、再生医療等製品の開発および市販後に関する課題解決に向けた前向きな議論が行われ、産官が議論を継続することが重要であるとの認識で一致しました。聴衆からも多くの質問が挙がり、再生医療等製品における規制に関する興味の高さがうかがえました。
 パネルディスカッションの様子(Session 5)
パネルディスカッションの様子(Session 5)
最後に
オンラインでも各セッションの発表後に行われるパネルディスカッションを充実した内容にすべく、今回の「CMC Strategy Forum Japan 2022」では、チャットを用いた即時質問、“いいね”機能を用いた質問への賛同機能等、運営にも工夫を凝らしたオンライン学会となりました。5つのセッション終了後、製薬協LSOCリードを務める中外製薬の久保寺美典氏から、本フォーラムの総括が実施され、閉会となりました。
このグローバル会議が、今後も日本で継続的に開催され、バイオ医薬品の研究開発の促進とCMC領域の活性化の一助になるよう、製薬協として支援を続けていきたいと考えています。今後ともみなさんのご支援をよろしくお願いいたします。
次回の「CMC Strategy Forum Japan 2023」は、2023年12月4~5日の開催を予定しています。
 中外製薬 久保寺 美典 氏
中外製薬 久保寺 美典 氏
(バイオ医薬品委員会 上田 徳仁、篠崎 真、杉原 努、久保寺 美典、中村 奈央、野々山 輝)

