「第15回 レギュラトリーサイエンス学会学術大会」開催される 品質保証とレギュラトリーサイエンス
2025年9月5日~6日に、学術総合センター(東京都千代田区)にて、「品質保証とレギュラトリーサイエンス」をテーマに「第15回 レギュラトリーサイエンス学会学術大会」が開催されました。
はじめに
レギュラトリーサイエンス学会(RS学会)は、医療現場、大学・研究機関、産業界や規制当局の関係者が、対等の立場で一堂に会して、医薬品・医療機器等のレギュラトリーサイエンスに関する研究成果や考えを公開討議し、その学術の進歩と普及を図るという設立理念のもと、2010年8月にレギュラトリーサイエンス学会が設立されました。本学会は設立から15年を迎え、レギュラトリーサイエンスの概念は広く浸透しつつあります。
2025年は9月5日~6日の2日間にわたり、「品質保証とレギュラトリーサイエンス」をテーマとして、各セクションで活発な議論が行われました。
本学術大会は、大会長講演、特別講演(3題)、シンポジウム(15題)、一般演題(口演19題、ポスター52題)で構成されました。
シンポジウム5
審査報告書に対する現状の利活用とその課題、今後の理想を考える
座長:製薬協 薬事委員会 柏谷 祐司 委員長
はじめに、厚生労働省医政局研究開発政策課治験推進室長の荒木康弘氏より、「AI時代の審査報告書の構成に向けた挑戦」と題した講演が行われました。講演では、近年の申請件数の増加傾向や、特定の疾患領域・時期に承認申請が集中するという独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が抱える課題に触れ、AIを活用した審査報告書作成の効率化に向けた検討が進められていることが説明されました。検討では3種類の生成AIを用いて生成物の質を評価し、それぞれの性能差が確認されたこと、さらに今後は市販のAIサービスの実力評価や実際の導入時にその検討結果が活用される可能性があることも紹介されました。今後の展望としては、需要の高い臨床項の作成支援を念頭に、非公開資料であるCTD Module 5での活用環境の整備、AI利活用における運用ルールの策定や予算確保の必要性が述べられました。
次に、東京薬科大学薬学部の益山光一氏より、「審査報告書に関する本学での教育と今後の理想」と題した講演が行われました。講演では、薬学部生への講義において、医薬品の理解をより深めるために審査報告書を有効に活用していることが紹介されました。そのうえで、現行の審査報告書では論点や結論が不明瞭な場合があるため、「審査報告(2)」の結論を冒頭に書くことで内容の明確化が図られ、医療関係者にも審査報告書がより浸透しやすくなるのではないかとの提案がありました。また、審査報告書の英語版にも言及があり、日本の審査のポイントを海外に迅速に発信するためには、「審査報告(2)」のみを速やかに英訳することが有効であるとの提案も示されました。

続いて、製薬協薬事委員会の村田宰子委員より、「製薬協の立場から考える審査報告書の課題と今後の方向性について」と題した講演が行われました。講演では、製薬協薬事委員会加盟会社を対象に実施した審査報告書に関するアンケート結果の詳細と、そこから明らかになった課題が紹介されました。それを踏まえ、今後は多様なユーザーニーズに応える柔軟な報告書構成の検討、概要と詳細データのバランス調整、作成の効率化、さらに海外申請や薬価算定など他用途への活用方法の整備に対する期待が述べられました。
さらに、欧州製薬団体連合会(EFPIA)の加藤卓也氏より、「より良い審査報告書を目指して—審査報告書における医薬品の革新性評価に関する考察と外資系企業視点からの審査報告書の活用への提言」と題した講演が行われました。EFPIA内で実施されたアンケート結果に基づき、日本の審査報告書が外資系企業の日本法人や海外からどのように見られているか、また審査報告書の英語版の活用実態などが紹介されました。さらに、審査報告書における開発品の革新性に関する記載について、具体的な事例を交えながら、従来以上に科学的な内容の記載が求められるとの期待が示されました。
パネルディスカッションでは、承認審査は承認拒否事由に照らして薬としての妥当性を評価するものである一方で、20年以上変わっていない現在の審査報告書のあり方にとらわれず、日本の患者のため、また日本でドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスを防ぐためにも、革新性に関する記載の必要性など、今後目指すべき審査報告書の姿について議論を深めていく必要があるという意見で一致しました。また、Reliance pathwayにおいて審査報告書を有効に活用してもらう観点からも、英訳しやすい記載とするなどの工夫が可能ではないかという意見も出されました。そのうえで、審査報告書に対する各ユーザーからの多様な要望をPMDAに反映してもらうためには、業界側で要望を反映した審査報告書のひな形を作成し、提示していくことが近道であるとの考えが示されました。最後に、今後も米国研究製薬工業協会(PhRMA)、EFPIAを含む新薬3団体が検討を重ねるとともに、行政やアカデミアなどのステークホルダーとも意見交換を行いながら、より良い審査報告書の実現に向けて取り組んでいくことが宣言され、活発なディスカッションのうちに締めくくられました。
シンポジウム7
GMP調査制度の改正とその先へ
座長:厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 監視指導室長 山本 剛 氏
製薬協 薬事委員会 柏谷 祐司 委員長
シンポジウム7では、業界団体、PMDA、地方庁そしてアカデミアからの演者による、今般の薬機法改正のさらに先のGMP調査制度についての発表に続き、パネルディスカッションが行われました。
はじめに、日本製薬団体連合会(日薬連)品質委員会委員長の小野誠氏より「GMP調査における区分適合性調査の利用について」と題し、日薬連が製造業者に対して行ったアンケート調査の結果についての発表が行われました。現状制度では多くの製造業者が本制度を利用してないことが示され、各社が考える課題が、改正薬機法の実装において解消されることへの期待が述べられました。

次に、PMDA医薬品品質管理部主任専門員の樋泉美月氏より「GMP調査制度の合理化と国際協働」について、現在PMDAが取り組んでいる国際協働活動について、医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム(PIC/S)加盟継続の再評価の経験ならびに今後のGMP調査について紹介されました。今後のGMP調査ではハイリスク製造所を検知する仕組みや監視指導を強化する仕組みが求められ、今回の法改正は国際協働への第一歩となるであろうとの展望が示されました。
次に、茨城県保健医療部医療局薬務課課長の花塚寿美氏より「茨城県におけるGMP調査について」と題し、地方庁としての調査権者の実態として、都道府県の調査対象の範囲の多様性(無菌、漢方、一般用や原薬など)のため幅広い知識が必要である一方、公務員としての業務の多様性、人事異動が多いこと等を具体的事例として示したうえで、GMP調査員の教育の難しさについて説明がありました。
次に、熊本保健科学大学品質保証・精度管理学行動講座 特命教授の蛭田修氏より、「医薬品製造所におけるDX化の進展とGMP調査」と題し、医薬品製造所における電子化・デジタルトランスフォーメーション(DX)化に伴う、品質保証やデータインテグリティのあり方についての解説と、電子化された製造所においては製造設備からの信号から、生データの定義そして、意志判断に至る流れを一連のシステムとして保証することが重要であり、GMP調査においては、それらをシステムとして説明することが重要になることが説明されました。
次に、製薬協薬事委員会薬事制度部会の藤川誠委員より「製薬協が行った『GMP踏査制度の改正とその先へ』アンケート調査結果に関する考察について」と題し、日米欧での調査の実態についての紹介がありました。日本は調査日数が短くばらつきが少ないが、欧米特に米国では自国製造所の調査日数が長い場合があること、調査対象に応じた専門性を有する調査員が調査を行っていること、Relianceを活用した調査の重複を避けることが期待されている実態を示しました。
パネルディスカッションでは、各演者に薬事委員会薬事制度部会の中山能雄委員を加えて、国際協働や国際整合を目指したGMP調査制度の先の姿について議論が行われました。
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子
一般演題<ポスター>
ポスター発表は、製薬協薬事委員会から以下の8つのテーマについて発表を行いました。
P-1 山本 善一(製薬協 薬事委員会 申請薬事部会)
新医薬品・新再生医療等製品の審査状況に関するアンケート2025
製薬協薬事委員会申請薬事部会の山本善一委員らから、「新医薬品・新再生医療等製品の審査状況に関するアンケート2025」をテーマに、2024年に承認された品目の審査プロセスの現状を評価し、効率化や改善策を提案する目的で、製薬協薬事委員会の加盟会社66社を対象として2025年1月に行われたアンケート調査の結果を紹介しました。
通常審査品目の申請から承認までの期間は中央値11.0ヵ月、優先審査品目では8.4ヵ月でした。初回面談以外に審査チームとの面談を実施した品目は44%で、前回の46%と同程度でした。電子データの提出割合は9割を超え、前回の81%からさらに上昇しました。また、審査の満足度としては、「コミュニケーションは良好」、「丁寧で柔軟な対応」等のポジティブな意見が多く見受けられた一方、専門協議資料搬入・eCTDライフサイクル更新の廃止、部会報告品のCTD修正要求の見直し等の「効率化」、製造販売後調査の議論のタイミングの前倒し等の「より早期の段階での議論・対応」によるさらなる改善を期待すると考察を述べました。
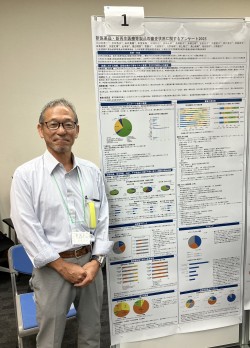
P-4 新宅 恭平(製薬協 薬事委員会 申請薬事部会)
日本製薬工業協会薬事委員会加盟会社における開発プロジェクトの現況~グローバル開発実施状況からの考察~
製薬協薬事委員会申請薬事部会の新宅恭平委員らから、「日本製薬工業協会薬事委員会加盟会社における開発プロジェクトの現況」をテーマに、製薬協薬事委員会加盟会社を対象に、2025年時点の開発プロジェクト状況を調査した結果を紹介しました。
プロジェクト数は前年比増加し、国際共同治験の割合が8割超の高水準となりました。日本人P1試験のスキップは通知の影響で増加傾向にあり、安全性確保策も多様化しています。希少疾病や小児開発では依然として国内治験が重視され、承認申請時に日本人データの提出が求められる傾向が続く傾向でした。創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(通称:あり方検討会)後に発出された新通知の活用は限定的で、今後の制度運用と企業対応に期待されます。
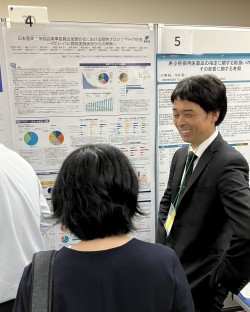
P-8 中西 顕伸(製薬協 薬事委員会 薬事制度部会)
2月10日通知改正(日本版変更手続きガイドライン)を見据えた欧米変更ガイドライン/ガイダンスの比較検討について
製薬協薬事委員会薬事制度部会の中西顕伸委員らから、2月10日通知改正(日本版変更手続きガイドライン)を見据えた、「2月10日通知改正(日本版変更手続きガイドライン)を見据えた欧米変更ガイドライン/ガイダンスの比較検討について」をテーマに、 欧米の変更ガイドラインの比較検討結果と、日本版変更手続きガイドラインに対するアンケート意見 を紹介しました。
欧州では、変更内容に対する条件と変更カテゴリーが記載されている一方で、米国では変更カテゴリーの概念と、カテゴリーごとの事例が示されており、分類や着眼点に違いがあることが明らかになりました。日本版ガイドラインに向けては、変更手続きの基本的な考え方や判断基準を示す概念の提示、ガイドラインに示された変更事例を機械的に参照して判断するのではなく、変更の背景やリスク、製品特性などを踏まえた柔軟な運用が可能な制度設計が重要とされました。
今回の欧米の変更ガイドラインの比較検討結果は、日本の薬事制度の国際整合性を踏まえた変更手続きガイドラインの検討における礎となり、グローバル基準に沿った高品質な医薬品の安定供給に貢献することが期待されます。
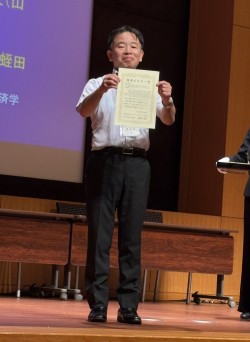
本発表は、第15回優秀ポスター賞を受賞しました。
P-9 高村 千香(製薬協 薬事委員会 薬事制度部会)
原薬等登録原簿(マスターファイル)制度に関する製造販売業者の立場での課題
製薬協薬事委員会薬事制度部会の髙村千香委員らからは、「原薬等登録原簿(マスターファイル)制度に関する製造販売業者の立場での課題」をテーマに、 マスターファイル(MF)制度導入から約20年を迎えたことを機に、製造販売業者の視点から制度の課題を明らかにするため、薬事制度部会加盟会社を対象に実施したアンケート調査について紹介しました。
多くの製造販売業者がMF制度の運用に煩雑さを感じており、特に審査の進捗が見えにくいことや、内容が開示されない中で責任を問われることに課題を感じていることが明らかになりました。また、変更管理や情報伝達の不十分さも指摘され、実業務に影響を及ぼしている実態が浮き彫りとなりました。
MF制度の改善に向けては、記載事項の簡素化、MF登録者による単独審査の導入、変更連絡の明確化、提出資料の簡略化、海外制度との連携など、具体的な要望が多数挙げられました。自由記述では、実務上の柔軟な対応や情報公開の必要性についても意見が寄せられました。
本調査を通じて、MF制度の見直しに向けた議論の必要性が改めて示されました。

P-11 一原 さやか(製薬協 薬事委員会 申請薬事部会)
日本における申請ラグの現状調査に関するアンケート
製薬協薬事委員会申請薬事部会の一原さやか委員らから、「日本における申請ラグの現状調査に関するアンケート」をテーマに、2022~2023年度に承認された新医薬品の申請ラグ実態を把握するために実施されたアンケート調査の結果について紹介しました。
新有効成分含有医薬品では「同時申請」が51.8%と最多で、国際共同治験への参加や同時申請が行える社内体制の整備が主因として挙げられました。小児適応医薬品でも「同時申請」や「日本先行」が増加傾向にあり、あり方検討会の議論に基づく日本の制度改善が寄与していることが示唆されました。第Ⅲ相国際共同治験への日本の参加は申請ラグ短縮に有効であり、今後の国際連携強化が期待されます。
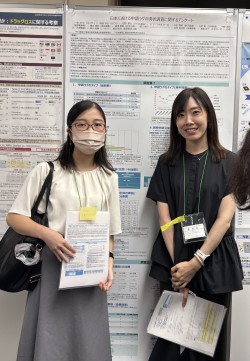
P-13 岡本 卓子(製薬協 薬事委員会 申請薬事部会)
医薬品医療機器総合機構が行う対面助言の現状及び企業の現状認識に係るアンケート
製薬協薬事委員会申請薬事部会の岡本卓子委員らから、「医薬品医療機器総合機構が行う対面助言の現状及び企業の現状認識に係るアンケート」をテーマに、2023年10月~2024年9月(先駆け総合評価相談及び事前評価相談は2022年10月~2024年9月)に実施された対面助言に関するアンケート調査の結果について紹介しました。
アンケート調査では、調査期間中に350件の対面助言が実施され、企業側の満足度は高水準を維持していました。一方、約3割の企業が問題点を指摘し、柔軟な見解や代替案の提示を求める声も多くありました。事前面談は相談資料の充実や相互理解に有効とされ、PMDAとの丁寧なコミュニケーションが重要とされました。また、事前評価相談の活用には、早期承認などの明確なメリット提示が求められていることが示唆されました。
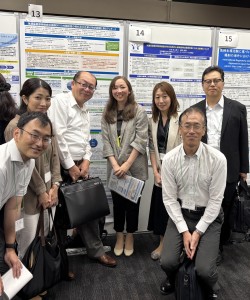
P-25 樽井 行弘(製薬協 薬事委員会 薬事制度部会)
薬制薬事担当者における教育方法の実態と課題について
製薬協薬事委員会薬事制度部会の樽井行弘委員らからは、「薬制薬事担当者における教育方法の実態と課題について」をテーマに、 薬事制度部会加盟会社を対象にした薬制薬事担当者の教育・育成方法の現状把握と課題についてのアンケート結果およびその結果をもとに行った討論から導き出された結果について紹介しました。
薬制薬事担当者に、1.必要とされる能力とその教育方法、2.教育の課題、3.業界活動の活用について考察を行い、必要とされる能力はコミュニケーション能力や法規制の理解など多岐にわたることがわかりました。また、教育方法はOJTを中心とした実践的な教育が重要視されていること、教育のための時間や教育ができる人員の不足が課題となっていることが明らかになりました。これらの課題に対し、情報共有の仕組み作りや業務効率化、さらには業界活動の積極的な活用が必要との提案を行い、特に、若手社員の育成に焦点をあてた取り組みや、業界全体での知識・経験の共有が重要視されているため、業界としても能力の習得や向上を目的とした場の機会を作ることも有用であるとの考えを示しました。

P-34 藤川 誠(製薬協 薬事委員会 薬事制度部会)
GMP適合性調査制度(基準確認証を中心に)の医薬品医療機器制度部会で合意された見直しを踏まえたアンケート報告— 製造販売業者の立場からの考察 —
製薬協薬事委員会薬事制度部会の藤川誠委員らからは、「GMP適合性調査制度(基準確認証を中心に)の医薬品医療機器制度部会で合意された見直しを踏まえたアンケート報告— 製造販売業者の立場からの考察 —」をテーマに、 薬事制度部会加盟会社を対象に2025年3月から5月に行った表題のアンケート調査結果を紹介しました。
厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会)で合意されたGMP調査制度の見直しにより、製造販売業者の自社の製造所に基準確認証を取得することは多少増加することが見込まれる結果であり、また、製造業者および製造販売業者にメリットが得られる制度運用が必要であることも明らかになったことから、基準確認証の取得促進または改善の要望を具体的に示しました。さらに、GMP調査を合理化・効率化するためには基準確認証の適用範囲(承認前調査等)の拡大が必要と考えることも示し、長期的な視点で、製造所のGMP管理の強化および安定供給課題の解決に繋がる「承認前調査も含む全てのGMP調査をリスクベースによる製造所単位の調査(原則実地調査)」への法改正・制度設計を継続的に議論する必要があることを示しました。
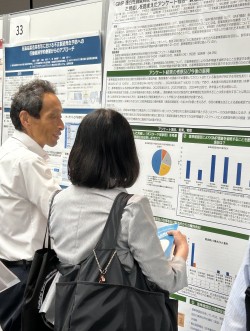
次回の「第16回 レギュラトリーサイエンス学会学術大会」は、2026年9月4日~5日に開催予定です。
(薬事委員会 小林 正次、中山 能雄、中野 恭嗣、杉原 正)

