「第14回 レギュラトリーサイエンス学会学術大会」開催 医療の未来を開くレギュラトリーサイエンス
2024年9月13日~14日に、一橋大学一橋講堂(東京都千代田区)にて、「医療の未来を開くレギュラトリーサイエンス」をテーマに「第14回 レギュラトリーサイエンス学会学術大会」が開催されました。
はじめに
レギュラトリーサイエンス学会(RS学会)は、医療現場、大学・研究機関、産業界や規制当局の関係者が、対等の立場で一堂に会して、医薬品・医療機器等のレギュラトリーサイエンスに関する研究成果や考えを公開討議し、その学術の進歩と普及を図るという設立理念のもと、2010年8月に設立されました。本学会は設立から14年を迎え、レギュラトリーサイエンスの概念は広く浸透しつつあり、製薬協も薬事に関連する制度やその運用のあり方について、アカデミアや規制当局である厚生労働省、総合機構と議論する目的で、毎年シンポジウムを企画提案、運営をサポートしたり、ポスター発表するなど、積極的に参加しています。
2024年は9月13日~14日の2日間にわたり、「医療の未来を開くレギュラトリーサイエンス」をテーマとして、各セクションで活発な議論が行われました。
本学術大会は、大会長講演、特別講演(3題)、大会長企画シンポジウム(1題)、シンポジウム(12題)、一般演題(口演15題、ポスター29題)で構成されました。
シンポジウム4
『創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会』での検討内容を受けての今後の課題
座長:日本製薬工業協会 森 和彦 専務理事
はじめに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ワクチン等審査部長の松倉 裕二氏より、「『創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会』を受けた今後の課題と取組み」として、検討会が開催された背景、各検討内容の概要が説明され、2024年4月に報告書として公表されたことが説明されました。また内閣官房を司令塔とした「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」の中間とりまとめを踏まえた政策目標と工程表が策定され、ドラッグ・ラグ/ロスの解消を政府としても推進していくことが紹介されました。
次に、製薬協薬事委員会の柏谷 祐司委員長より、「『創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会』での検討内容を受けての今後の課題」として、検討会で議論されたトピックのうち、小児、オーファン、国際共同参画前の日本人P1などの項目について、業界側から見た検討会の結果と今後の課題について紹介がありました。柏谷委員長から、検討会で向かうべき方向性はつけられたので、今後はそれが適切に運用されているのか、PDCAサイクルを回していくつもりであるとの見解を示しました。

次に、アキュリスファーマ株式会社薬事兼開発戦略部の竹内 真一郎氏より、「薬事規制検討会での検討を受けての実装と課題 施策に対する課題と期待(ベンチャー視点)」として、スタートアップ企業の中で、海外製品を国内導入する企業としての立場で検討会に対する意見が述べられました。スタートアップ企業が海外製品を導入する際に、売上予測、開発戦略およびその費用、市販後の活動などについて、その蓋然性を投資家に説明する必要があるため、通知等に明確に記載をすることが重要であると主張されました。今後、ラグロスを起こさないことと既にラグロスになっている品目の対応の両方を検討していく必要があり、収益の増加、市販後の負荷、安全供給リスクの軽減などが課題になるとの見解を示されました。
次に、ボストン コンサルティング グループ ジャパンの柳本 岳史氏より、「薬事規制改革の未来像:『創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会』からの考察」として、検討会が成功した理由として、有識者検討会、政府の骨太の方針における創薬力強化宣言、安定供給やラグロスの問題が生じて、社会からの注目が集まったことが挙げられると紹介されました。また今後、新規モダリティの新薬がさらにラグロスとなる可能性があり、早期に対応が必要であるとの見解を示されました。
パネルディスカッションにおいては、検討会を受けて発出された通知を会社側、行政側の双方が適切に運用できているのかの検証が必要との意見がありました。また日本の国際的な立ち位置を意識して、今後どのように最適化していくことができるのか考える必要があるとの意見もありました。本検討会で議論されたことの続きは薬機法改正を検討している医薬品医療機器制度部会で議論が継続されており、今後は将来を見据えた視点を持ちながら必要な際に議論をしていくことが重要であると締めくくりました。

シンポジウム10
Global Standardのリスクベース型アプローチによる品質に係る承認事項変更手続き制度を達成するために
座長:厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長 中井 清人 氏
製薬協薬事委員会 柏谷 祐司 委員長
はじめに、国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部の石井 明子氏より、「医薬品の品質に関する承認事項とその変更管理の在り方について一薬事規制検討会での議論に基づく今後の方向性一」として、医薬品の製造販売承認書における承認事項、製造販売承認申請書記載事項に関する指針(平成17年2月10日、薬食審査発第0210001号)、令和5年度「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」に触れながら、承認事項とその変更管理のあり方に関する、これまでの経緯の概略と薬事規制検討会での議論について紹介されました。
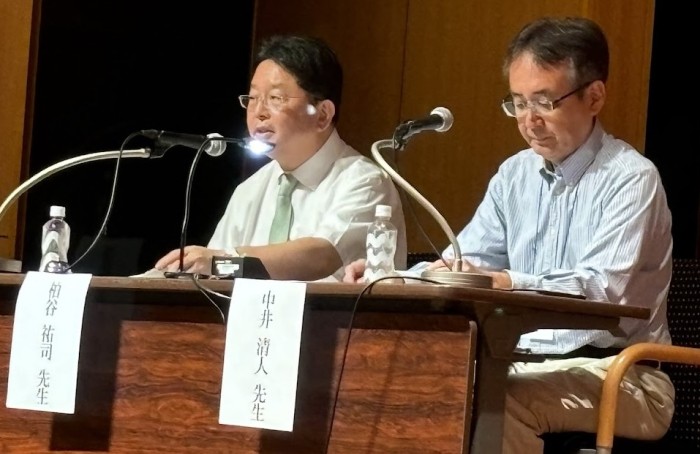
次に、製薬協薬事委員会薬事制度部会の中山 能雄委員より、「製薬協が行った『承認事項及び変更手続きに関する実態調査』の結果について」として、ICH Q12ガイドラインに規定されているEstablished Conditionsの欧米における実際の利用状況、「リスクベースの変更」に対する製薬協加盟各社の意識、ならびに、欧米の企業(外資系企業の親会社や内資系企業の提携先等)の視点での日本に特徴的な制度に対する認識についてのアンケート調査結果が発表されました。また、高品質な医薬品を安定的に継続的に供給できる最適な制度の実現の必要性を述べました。
次に、米国研究製薬工業協会(PhRMA)の高須賀 正博氏から、「PhRMAの考える品質に係る承認事項の記載および変更管理の在り方」として、日米欧における承認事項、変更管理、変更カテゴリの違いについて紹介されました。製造販売承認申請書記載事項に関する指針(平成17年2月10日、薬食審査発第0210001号)は承認事項ECではないものも含まれており課題と考えられること、変更のカテゴリとしては事前承認、届出中リスク、届出低リスク、報告不要の4つが必要と考えられること、承認事項としては表形式が国際的にも理解されやすくよいと考えられること、ICH Q12に調和するのがよいと考えるとの発表がなされました。
次に、欧州製薬団体連合会(EFPIA Japan)技術委員会品質部会部会長の尾崎 恭代氏より、「欧州外資系企業(EFPIA)から見た日本での変更管理について」として、EUにおけるVariation、EUのVariation事例、日本と欧州におけるGMP調査の違い、リスクベースの変更制度について発表がありました。日本では承認時に変更カテゴリを設定するのに対してEUでは変更時に変更カテゴリを決定すること、GMP調査については日本では品目が調査対象であるのに対してEUでは製造所が調査対象であることなど違いを発表されました。EFPIAの考える「リスクベースの変更制度」として、知識・経験を有する企業が変更に係るリスク評価を行い、変更を実施することとの意見が述べられました。
次に、沢井製薬株式会社研究開発本部開発部の小澤 良樹氏より後発医薬品企業の立場から、「リスクベースで考える変更管理のあり方と目指すべき方向性」として、リスクの見える化により、規制当局とのコミュニケーション強化によるギャップを低減した上で、変更の事前合意を得ることが望ましいこと、リスクの見える化はより製品への理解を深め、迅速かつ適切な変更管理にもつながることが述べられました。先発医薬品を中心に変更手続き制度がグローバルで統一される方向性は管理・運用などの面で望ましい一方、後発医薬品を中心に海外市場がターゲットになっていない医薬品などは異なる運用を行うなど、リスクベースの変更管理という同じゴールでも、アプローチは1つではなく複数あり得るとの意見が示されました。
次に、製薬協薬事委員会薬事制度部会の山内 園子委員より、「製薬協が考えるリスクベース型の承認事項変更手続き制度とは?」として、新規承認時点で各パラメータについて将来の手続きカテゴリ(一部変更承認申請又は軽微変更届出)を決定する(以下、 日本型リスクベースアプローチ)制度と変更起案時に品質に与える影響や変更リスクに相応する手続きカテゴリをガイドラインの例示を指標として選択する(以下、欧米型リスクベースアプローチ)制度についての説明の後、それぞれのPros and Consについて発表がありました。国際整合性を必要とするグローバルに展開している品目および国内向けを対象としている品目で違いがあることについて言及し、各品目が必要とする薬事制度を選択できる「二階建て」の制度や製薬協が考える製造方法欄における記載例についても提案がありました。
最後に、PMDAジェネリック医薬品等審査部長の高木 和則氏より、現在、検討されている中等度変更、年次報告制度、リスク評価と変更管理、製品切替え時期設定一変、製造販売承認申請書記載事項に関する指針(平成17年2月10日、薬食審査発第0210001号)の課題について発表がなされました。実生産における実績・知識を踏まえた変更カテゴリの設定や申請書記載指針の課題認識について言及され、薬事制度については海外の制度を導入するのではなく、海外と調和する制度がよいと述べられました。

一般演題<ポスター>
ポスター発表は、製薬協薬事委員会から以下の3つのテーマについて発表が行われました。
P-1 関 恵美子(日本製薬工業協会 薬事委員会 申請薬事部会)
日本製薬工業協会薬事委員会加盟会社における開発プロジェクトの現況~グローバル開発実施状況からの考察~
製薬協薬事委員会申請薬事部会の関 恵美子委員らから、「日本製薬工業協会薬事委員会加盟会社における開発プロジェクトの現況~グローバル開発実施状況からの考察~」をテーマに、2011年から毎年実施されている日本の開発プロジェクトおよび国際共同治験のアンケート調査に基づき、2024年の傾向と経年変化、より効率的なグローバル開発ストラテジーについての検討が紹介されました。
2024年の調査では、製薬協薬事委員会加盟会社66社から回答を得ました。開発プロジェクト数は1106に達し、国際共同治験の割合も81%に増加しました。抗悪性腫瘍薬が主要な開発領域でした。グローバル開発品目は全体の92%を占めました。
アンケートの実施時期から、2023年年12月25日に発出された「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方」に基づく活用事例はまだ少ないと推察されましたが、日本人被験者の安全性が日本人PI試験実施の判断基準となっている可能性が示唆されました。希少疾病や小児開発に関する状況は例年と変わらず、欧米と日本での開発実施割合に異なる傾向はみられませんでした。今後、ドラッグ・ロス解消のための通知発出を踏まえ、開発環境の改善への期待を示しました。
本発表は、第14回優秀ポスター賞を受賞しました。
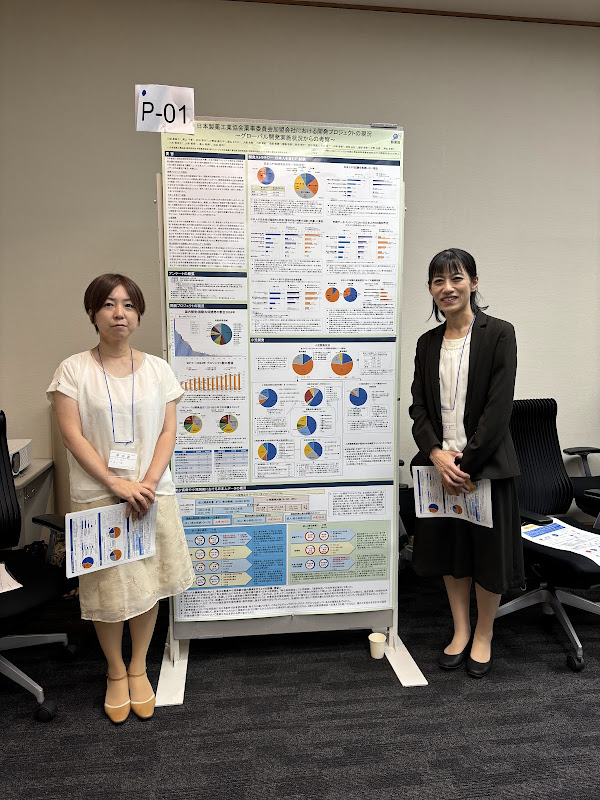
P-4 山本 善一(日本製薬工業協会 薬事委員会 申請薬事部会)
新医薬品の審査状況に関するアンケート2024
製薬協薬事委員会申請薬事部会の山本 善一委員らから、「新医薬品の審査状況に関するアンケート2024」をテーマに、2023年に承認された新医薬品の審査プロセスの現状を評価し、効率化や改善策を提案する目的で、製薬協薬事委員会参加64社を対象として、2024年1月に行われたアンケート調査の結果が紹介されました。
通常審査品目の承認までの期間は中央値11.2ヵ月、通常審査品目以外は8.3ヵ月でした。初回面談以外を実施した品目は46%で、前回の35%から増加しました。電子データ提出割合は81%で、前回の71%から上昇しました。また、審査報告書の確認時間が不足しているとの回答が急増しました。リモート調査については柔軟な対応が評価されつつも、調査日程調整の連携不足などの改善要望が挙がりました。また、申請電子データの負担軽減や審査報告書の内容確認の時間確保が求める意見がありました。審査プロセスについて、完全電子化等の効率化や専門協議での議論の透明性の向上、適合性調査の見直しなどにより、さらなる改善を期待することが示されました。
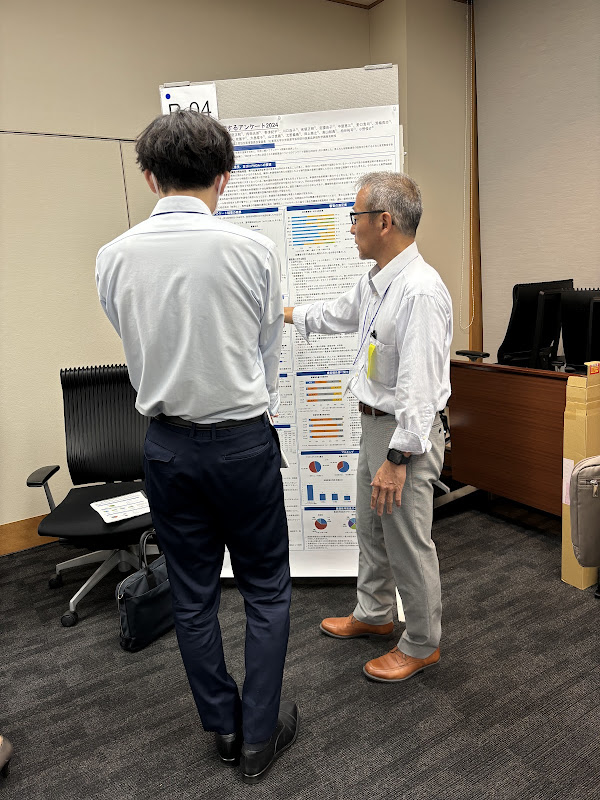
P-21 藤川 誠(日本製薬工業協会 薬事委員会 薬事制度部会)
基準確認証制度拡大と更なるGMP適合性調査制度の合理化について —製造販売業者の立場からの考察—
製薬協薬事委員会薬事制度部会の藤川 誠委員らからは、「基準確認証制度拡大と更なるGMP適合性調査制度の合理化について —製造販売業者の立場からの考察—」をテーマに、2021年8月改正薬機法施行において導入された基準確認証制度について、製薬協薬事委員会薬事制度部会加盟会社を対象に2023年11月に行ったアンケート調査結果を2023年のRS学会で報告した2022年アンケート調査結果と比較しながら紹介しました。本制度は導入から約3年経過するも利用の進展が見られず、製造販売業者の立場からは本制度利用のメリットが見出せないことから、次期薬機法改正において基準確認証の適用範囲を拡大し(承認前/新薬初回定期/輸出用GMP)、GMP調査を合理化・効率化するとともに、将来的にはさらなる製造所単位のリスクベースによるGMP調査を目指し、実地調査の頻度の増加および製造所のGMP管理強化を両立できる制度設計を検討する必要があるとの考えを示しました。
本発表は、第14回優秀ポスター賞を受賞しました。
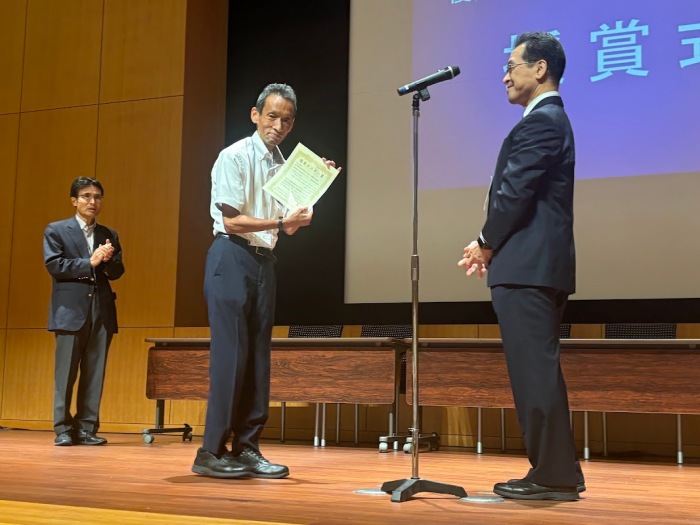
最後に
2023年度に開催された「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」において、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス問題の解消、小児医薬品開発の促進、医薬品の製造方法に係る薬事審査等のあり方、薬事制度におけるリアルワールドデータの活用のあり方等について検討がなされました。2024年度からは医薬品医療機器制度部会において次期制度改正を見据えた議論、検討が進められています。
2024年の学術大会では、「薬事規制のあり方に関する検討会」での検討内容がシンポジウムで取り上げられ、さまざまな立場から数多くの積極的な議論が行われました。これらを通じて、今後、レギュラトリーサイエンスの推進と産学官間のさらなる連携がいっそう進むと思われ、レギュラトリーサイエンスがさらに発展し、本学会の活動がますます活発になっていくことが期待されます。
(薬事委員会 竹内 豊、田上 雅之、清水目 梢、中西 顕伸)

