「ドイツ研究開発型製薬工業協会(vfa)との定期会合」を開催
2025年01月10日
製薬協国際委員会欧米部会では、欧米の政府・製薬団体と協調し、国際的課題の解決を図る活動の一環として、欧州の製薬団体との定期会合を毎年実施しています。2024年のドイツのvfaとの定期会合は、10月7日に対面とオンラインのハイブリット形式にて開催されました。会の後半には、定期会合では初めてvfaとフリーディスカッションを実施した後、在独日本大使館を訪問し書記官との面談も行われました。
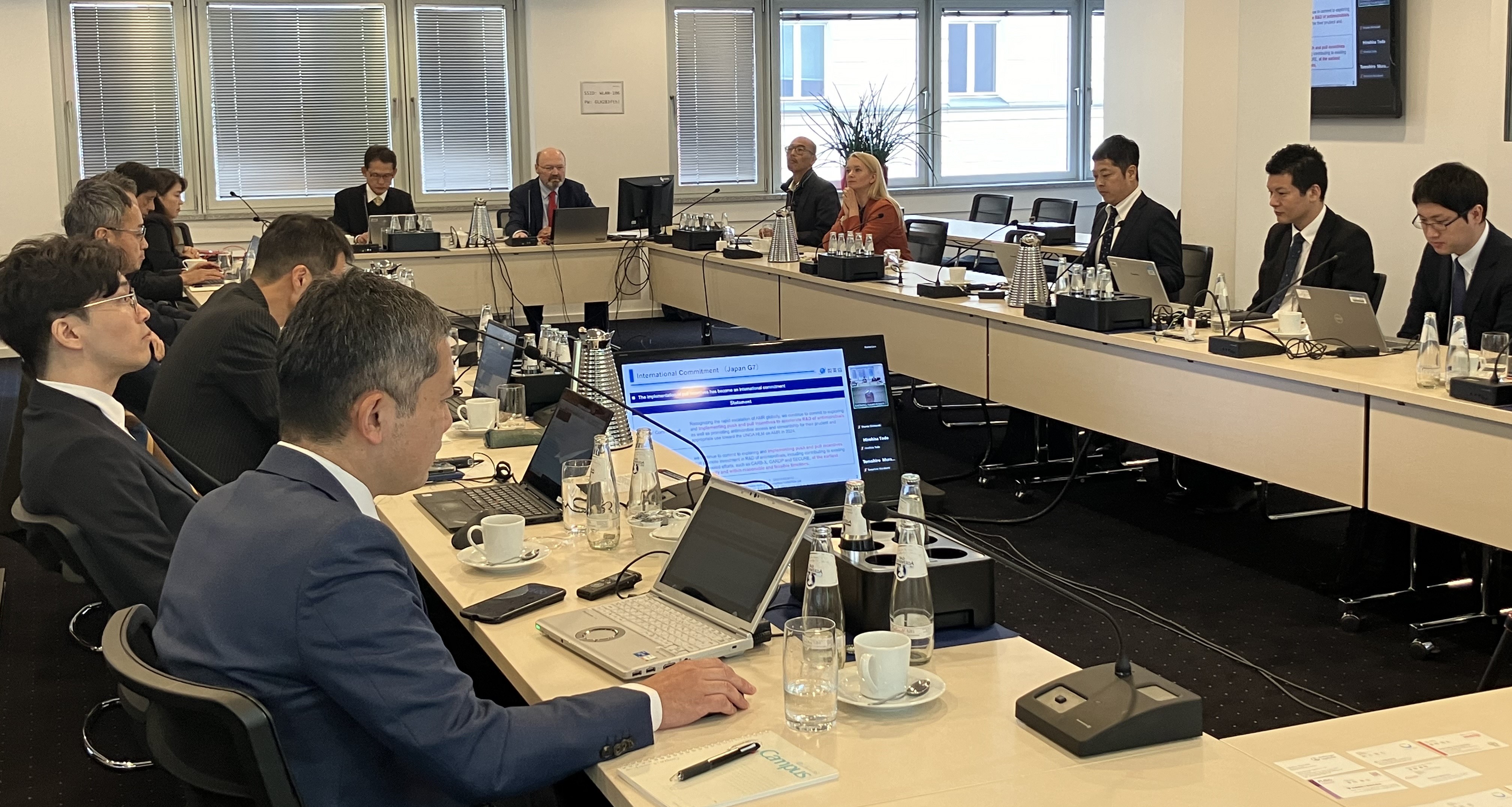 写真・現地会場の様子
写真・現地会場の様子
今回は双方合わせて現地で17名参加し、オンラインからも日本製薬団体連合会(日薬連)含めて多数参加し、活発な意見交換が行われました。
会合の概要を以下のとおり報告します。
はじめに
冒頭、vfaのInternational AffairsのSenior ManagerであるHarald Zimmer氏の挨拶から会がスタートしました。本会合はドイツと日本の密接な協力関係および友好の証であり、有益なディスカッションができることを期待しているとのコメントが述べられました。
Pricing & Reimbursement, HTA:GKV-FinStG updates, impact on EU-HTA and Medical Research Act(MFG)
Manager Reimbursement Policy, vfa Eike Melchior 氏
Harald Zimmer氏より、2022年11月に制定されたGKV- FinStG(公的医療保険中央連合会財政安定化法)の革新的な医薬品の供給および生産拠点に与える影響に関するvfaによる調査結果が共有され、イノベーションとドイツのビジネス環境に悪影響を及ぼしている兆しがあることが報告されました。一方で、ドイツ保健省による調査では、影響を評価するには時期尚早とし継続的な評価が行われることが報告されました。また、2024年7月に可決したMedizinforschungsgesetz, MFG(医療研究法)の改正について概説しました。MFGは製薬産業の研究・生産拠点としてのドイツの魅力を再び向上することを目的に改正されたとされていますが、業界にとってはポジティブな改正だけではないことから具体的な施行に向け継続的な議論の必要性を言及しました。
Updates on expensive drugs and drug pricing system reform in Japan
日本製薬団体連合会 保険薬価研究委員会 草開 義隆 氏
草開氏より、日本における2024年度薬価制度改革、創薬力を強化する政府の取り組み、高額な医薬品の取り扱いについて説明があり、2023年4月に製薬協は欧州製薬団体連合会(EFPIA)や米国研究製薬工業協会(PhRMA)と共に、2024年度薬価制度改革に向けた共同声明を公表したことや、2024年7月に政府が公表した創薬力を強化するための3つの戦略目標について紹介がありました。ディスカッションでは、コストベースとバリューベースによる薬価設定についてドイツ・日本の双方立場から意見交換され、また高額医薬品の取り扱いに関するルールが、ドラッグ・ロスやドラッグ・ラグの問題を引き起こす可能性について議論されました。
Digital Health:DigiG/GDNG updates, actual usage of DiGA, industrial interest on the development of DiGA
vfa
vfaより、2023年にドイツ議会を通過した医療のデジタル化の加速に関する法律(DigiG)およびヘルスデータの利活用に関する法律(GDNG)について概要の説明がありました。またデジタルヘルスアプリ(DiGA)市場の最近の進展について紹介がありました。ディスカッションでは、DiGAの承認数は増える一方で有用性に懐疑的な指摘がある背景について質問があり、医療現場では比較的若手の医師が処方する傾向にあることや、行政側では疾病金庫が短期的なコストの発生を懸念しており長期的な視点で疑問があることが共有されました。
AMR countermeasures:
製薬協 国際委員会 グローバルヘルス部会 有吉 祐亮 委員
Senior Manager International Affairs, vfaHarald Zimmer 氏
日本とドイツの抗菌薬インセンティブ制度について、有吉委員、Harald Zimmer氏よりそれぞれ発表が行われました。有吉委員からは日本の抗菌薬確保支援事業(Antimicrobial Securement Support Program)について、抗菌薬の選定方法、助成金の計算方法、選定企業の対応が紹介されました。質疑では販売予測の作成者に関する質問があり、厚生労働省が予測を作成することを回答しました。Harald Zimmer氏からはReserve antibioticsに対する病院での保険償還とTEEs、Advocacyと活動団体について発表がありました。質疑では、BEAM Alliance、DNAMR、AMR R&D Hubなどの活動団体について共有がありました。
Stable Supply:ALBVVG updates
Manager Reimbursement Policy, vfa Eike Melchior 氏
Eike Melchior氏より、後発品不足を防ぎ供給を改善するための法律(ALBVVG)の概要について説明がありました。この法律は小児用、抗生剤、後発品の供給必須医薬品の供給を強化することを目的とされており、たとえば小児用や必須医薬品では価格設定が緩和されていることや、後発品の在庫義務を課していること等が紹介されました。
Stable Supply:Japan status updates
日本製薬団体連合会 保険薬価研究委員会 渡部 尚大 氏
主に日本における医薬品の供給不安の現状および原因、安定供給に向けた取り組み、関連する薬価のルール、市場撤退について説明がありました。2024年度より試行的に導入された安定供給への取り組みに応じた後発品メーカーの分類と薬価算定についても、概要や評価基準が共有されました。
ディスカッションでは、市場撤退における課題や採算が合わない場合の対応策についての質問があり、不採算品再算定の制度を紹介したうえで、撤退基準の緩和や不採算品再算定の適用条件に関して業界からの働きかけを行っていることを回答しました。
Discussion:Future collaboration between vfa and JPMA
定期会合としては初めてディスカッションの時間を設け、今後両団体でどのように連携していくのが良いか検討する場となりました。コミュニケーションの頻度を増やす、目的に沿って開催するなど活発な意見交換ができ、今後も緊密に連携していくことで一致しました。
終わりに
vfaのHarald Zimmer氏より、興味深く有益なディスカッションであったとのコメントとともに、会合の開催に携わった方々への謝意が述べられました。
製薬協国際委員会の中垣寿副委員長は、多くの国が限られた予算の中で医療費を賄うのと同時にイノベーションを推進しようとしている中、両団体で共通の目的を持ち、その発展をしっかりとモニタリングしながら、今後もコラボレーションを継続していくことが重要であると述べました。
 集合写真
集合写真
(国際委員会 欧米部会 欧州グループ ドイツフランスチーム)

