「BioJapan 2025」開催・参加報告 開会式ならびに基調講演、バイオ医薬品セミナーについて
「BioJapan 2025」が2025年10月8日(水)~10日(金)の3日間、パシフィコ横浜にて開催されました。例年同様、「再生医療JAPAN2025」および「healthTECH JAPAN 2025」も併催され、2025年は過去最高の22,167人が来場したほか、展示会への出展組織数も多数にのぼり、パートナリングにおいても過去最多の25,498件の面談が実施されました。また2024年同様、非常に多くの海外からの参加者が、会場を活気付けました。製薬協も主催団体の一つとして参加したほか、会員会社の方々からも多数の発表を実施。この他、多くの会社・団体等がアライアンスブースを出展し、アカデミアやベンチャー等と面談するなど、活発な情報交換と交流が行われました。
開会式ならびに基調講演
主催者を代表してBioJapan組織委員会会長の吉田 稔氏による挨拶の後、経済産業省 商務・サービス審議官の南 亮氏、厚生労働省 大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官の森 真弘氏、文部科学省 大臣官房審議官(研究振興局および高等教育政策連携担当)の坂下 鈴鹿氏、神奈川県知事の黒岩 祐治氏による来賓祝辞がありました。その後、基調講演として「富士フィルム バイオCDMO事業の展開」(富士フィルムホールディングス(株)代表取締役社長・CEO 後藤 禎一氏)、「The Future of Global Biomedical Research: Inserm’s Strategic Vision and International Collaboration Opportunities(Chairman and chief Executive Officer Inserm Prof. Didier Samuel)および「生命科学とテクノロジーの融合が拓く未来:東京科学大学の挑戦」(東京科学大学 学長 田中 雄二郎氏)の3つの講演がありました。
 開会式の様子
開会式の様子
バイオ医薬品委員会セミナー(主催者セミナー)
バイオ医薬品製造人材の確保に向けた取り組みと国内エンジニアリング業界への期待
製薬協 バイオ医薬品委員会は、BioJapanにおいてこれまで複数回にわたり「人材」をテーマにセミナーを継続的に開催してきましたが、2025年度はこれまでの製薬業界主催のセミナー題材としてはあまり前例のない「バイオ医薬品製造に関わるエンジニアリング人材」をテーマにセッションを開催しました。
国内におけるバイオ医薬品製造拠点の整備が加速する中、即戦力となるバイオ製造人材の確保と次代を担う人材育成が課題視されており、一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター(以下、BCRET)の設立・拡張や、産学官連携による専門人材育成が進められています。さらに、2025年度からは製薬会社の実生産設備を用いたCDMO※1の人材育成というチャレンジングな活動も開始されています。しかしながら、製造人材だけでなく、製法開発、QA/QC、薬事など幅広い分野のCMC※2に関わる専門人材の確保も必要です。加えて、生産設備のオートメーション化、DX推進、GMPへの要求事項の高度化などにより、医薬品製造やGMPを理解したエンジニアリング人材やデジタル人材の確保も課題となっています。
こうした環境変化を踏まえ、本セミナーでは、製薬協および製薬会社が取り組む製造人材の確保・育成状況を共有するとともに、議題提案として製薬企業からエンジ人材不足に起因する課題感を共有。続いてエンジニアリング業界から産業全体における医薬品製造設備投資に関する定量解析・半導体業界との比較・考察、「ユーザーエンジニア(ユーザーの視点を持ち、医薬品製造やGMPを理解したエンジニア)」の育成の重要性、医薬エンジニアリング業界と製薬ユーザーの一層の連携の重要性が語られました。
※1 CDMO:Contract Development and Manufacturing Organization
※2 CMC:Chemistry, Manufacturing and Control
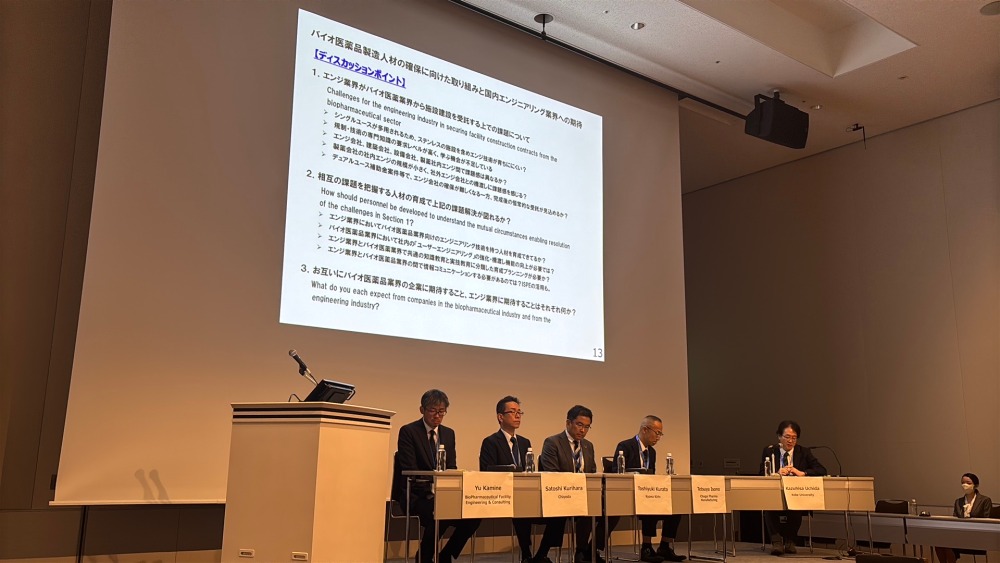 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子
セミナーのイントロダクション
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授、BCRET 専務理事 内田和久氏
内田氏より本セッション設定の経緯として、バイオ人材育成の要望が高まった背景、経済産業省、厚生労働省が主導する活動項目、またBCRETが主導する人材育成ニーズに関する定量調査が進んでいることが説明されました。さらに、BCRETによるニューモダリティ※3も含む座学・実技のコース設定や、製薬会社の実機を用いたCDMO人材育成が開始されたことなど、さまざま取り組み内容が紹介されました。この他、エンジニアリング業界と製薬業界のシームレスな連携の重要性を論じてきた経緯から本セッション開催に至った趣旨の説明も行われました。
※3 ニューモダリティ:ADC、Bispecific抗体、細胞医療、遺伝子治療、核酸医薬など
各演者による講演内容
1) 中外製薬工業が取り組むバイオ製造人材の育成およびエンジニアリング人材の課題
中外製薬工業株式会社 生産技術本部 バイオ担当 シニアプロフェッショナル 磯野哲也氏磯野氏からは、自社のCDMO人材育成の取り組みとして、基礎教育後に浮間、宇都宮拠点における複数回の実生産活動の作業経験を行うプログラム、さらにMSAT/QA/QCとの技術的協議やメンターサポート体制が紹介されました。社内人材育成の課題としては、責任者クラスの教育について、構築済みの画一的な体系化教育のみでは達成が難しく、逸脱/査察対応の適宜判断の能力を高めるなどのさまざまなプログラムが大切と説明しました。キーワードは「『挑戦』の経験」であり、マインドと支援環境が必須要件となります。
エンジニアリング分野の課題としては、新卒学生の製薬会社のエンジニアリングに対する関心不足、キャリア採用の難しさ、英語力の高さが求められることを挙げました。人口減少に伴う就労人口の減少や働き方改革によるキャパシティ縮小も踏まえ、供給能力が限られているという前提での工夫、平準化、設備仕様や業務手順の標準化の重要性も指摘しました。
2) 協和キリンの人材育成・エンジニアリングの取り組み
協和キリン株式会社 常務執行役員 CSCO 兼 Global Manufacturing Head 藏夛敏之氏藏夛氏からは、製薬協バイオ医薬品委員会として取り組んできたCDMO人材育成支援の概要と、協和キリンの支援活動が紹介されました。協和キリンの社内人材育成については、継続的なキャリア採用の結果、教育が急務となっていること、さらにはグローバルに活躍する人材育成のために社内に人材開発室&ナレッジセンターを設置した成果が共有されました。同センターの特徴としては、ミミック設備を用いた実技訓練やノウハウ伝承が挙げられます。また、米国に新バイオ医薬品工場を建設中であり、日本国内とのヒトと技術の交流、循環による研鑽のアプローチが進められている旨も説明しました。
また、継続的な大型投資により修繕費も増加しており、維持のために社内エンジニアリング部門の増員に取り組んでいる現状が共有されました。エンジニアリングの課題としては、納期問題、モダリティ拡大に伴う要求仕様の高度化、老朽化対策の重要性が指摘され、熟練工不足や資材高騰、半導体・データセンター向けの工事との競合などが原因として挙げられました。
最後に、製薬会社の協業パートナーであるエンジニアリング業界への期待として、設計から保全までの一貫対応、未然防止支援、パートナーシップ構築、ノウハウ共有の重要性が示されました。
3) データから推察する医薬品業界の状況
千代田化工建設株式会社 ライフサイエンスプロジェクト部 部長 栗原令氏栗原氏からは、医薬品業界の状況を示すデータとその考察が示されました。建設業界の受注高はこの10年間で12兆円から18兆円に拡大し、その中でも製造業向けの国内建設工事受注高は全体の約20%を占めており、建設工事全体の影響を受けやすいことが推察されました直面する課題としては、深刻な就業者数減少と高齢化、働き方改革による就労上限規制の厳格化、資材高騰による経営圧迫が挙げられました。医薬品製造業の設備投資もこの5年で約4,000億円から6,000億円へと1.5倍に拡大しましたが、全産業に占める割合は2.5~5%程度にとどまり、全産業の市況が医薬品設備投資にも影響していると考えられます。
医薬品産業の政府関連予算は厚生労働省、経済産業省の予算情報から抽出すると約1兆1,600億円です。これに対し、クリーンエリア設置や高品質な用水利用・求められる高い品質管理という観点で比較可能と考えられる半導体産業は5兆7,000億円となっており、両者には約5倍の差があります。類似性を考慮すると、半導体産業の積極投資は医薬品業界の建設工事全体に加え、オペレーター確保などの人材面にも影響を及ぼす可能性があると推察されます。
これらの状況を踏まえ、栗原氏は「個社での解決は難しい」とした上で、業界の垣根を超えて連携するとともに、卓越した技術を国内維持し、その魅力を発信することが重要である旨を強調しました。
4) バイオ医薬品製造のユーザーエンジニアの育成の必要性と生産効率の向上
Biopharmaceutical Facility Engineering & Consulting CEO 上根祐氏上根氏からは、ユーザー視点を根底に据え、バイオ医薬品製造施設や設備の建設から立ち上げ、保全に長年携わった経験をもとに、ユーザーとエンジニアリング業界間のみならず、ユーザー社内においてエンジニアリングの橋渡し役、パイプ役となる「ユーザーエンジニア」の必要性と価値について説明がありました。「ユーザーエンジニア」とは、GMPやプロセス、ユーザー側の「勘所」を理解し、ユーザー視点を持つエンジニアを意味します。
拡大するバイオ医薬品業界において、ユーザー負荷が高まる中、ユーザーエンジニアを大事に育てることが有効な解決策として注目されています。その育成にあたっては、GMPやプロセスの学習、プロジェクトマネジメントスキルに加え、高いコミュニケーション力が重要です。その中でも特に、「製造体験による知識の定着と肌感覚の経験」の大切さを強調しました。
さらに、教育の仕組みが広く構築され魅力ある業界になること、エンジニアだけではなくユーザー側も他部門を学ぶことなどのポイントを、トラブル実例とその影響も交えて説明しました。ユーザーエンジニアの存在は、ユーザーも気が付かない付加価値の発見や設備設計の簡素化などの効果も期待できます。最後に育成ツールとして「デジタルツイン」活用のヒントを示しました。
パネルディスカッション
最後のパネルディスカッションでは、以下のテーマについて議論しました。
🔹 エンジニアリング業界がバイオ医薬品業界から施設建設を受託する上での課題
🔹 相互の課題を把握する人材の育成で上記の課題解決が図れるか
🔹 バイオ医薬品業界の企業とエンジニアリング業界が相互に期待することは何か
課題として、要求仕様の変化に対する相互理解不足、仕様の過剰化やそれに伴うメンテナンス負荷の増加、施主ごとに異なる関わり方、シングルユース設備の普及によりエンジニアリング知識がなくても建屋建設が可能となる状況などが指摘されました。標準化や変化に応じた情報共有の重要性が論じられるとともに、ユーザー側もエンジニアリングを学ぶことにより効率化が期待できるとの提案もありました。
また、エンジニアリング人材およびユーザーエンジニアの確保・育成の重要性が強調され、製造とエンジニアリングの能動的交流や施工アプローチの改善による納期短縮、業界全体の医薬品設備投資に対する不安感についてオープンな議論の重要性が論じられました。エンジニアリングに携わる者同士の一体感醸成や、ユーザーとエンジニアリングの協議の場として国際製薬技術協会(ISPE)などの団体への期待も挙げられました。
展示ブース
2025年も研究開発委員会およびバイオ医薬品委員会の合同タスクフォースを設置し、製薬協展示ブースの企画・準備を進めてきました。展示ブースでは、両委員会の活動内容をポスター、資料、投影映像を通じて紹介しました。また、2025年の新たな取り組みとしては、スランプラリーの実施、広報委員会および宮柱明日香会長チームとの連携が挙げられます。製薬協のほか、富山くすりコンソーシアム、福岡バイオコミュニティ、大阪バイオ・ヘッドクオーター(中之島クロス含む)、糖鎖生命コア研究所(iGCORE)および沖縄科学技術大学院大学(OIST)のバイオ関連5団体の展示ブースを訪問した方には記念品を贈呈したスタンプラリーには、200名を超える参加がありました。また、宮柱会長による複数回の製薬協ブース訪問、広報委員会との連携により3日間を通して適時X投稿を行ったことにより、アドボカシー活動のさらなる効果や集客にも繋がったと考えています。
 製薬協ブースの様子
製薬協ブースの様子
次回の「BioJapan 2026」は2026年10月7日(水)〜9日(金)、パシフィコ横浜にて開催される予定です。
(バイオ医薬品委員会 政策実務委員長 中川 泰志郎、薬事・バイオ医薬品部長 塚田 純子)

