「CMC Strategy Forum Japan 2024」開催
2024年12月9~10日の2日間にわたり、CASSS(California Separation Science Society)主催の「CMC※ Strategy Forum Japan 2024」が東京マリオットホテル(東京都品川区)にて開催されました。日本だけでなくアジア、北米、欧州等9ヵ国から約100名の参加登録があり、非常に活発な意見交換が行われました。
-
※CMC:Chemistry, Manufacturing and Control。医薬品製造および品質を支える統合的な概念
CMC Strategy Forum Japan開催の経緯
CMC Strategy Forumは2002年にWCBP(Well Characterized Biotechnology Pharmaceutical)シンポジウムから独立し、米国で第1回が開催された後、2007年から欧州、2012年から日本、2014年からラテンアメリカ、そして2021年から中国でも継続して開催されています。CMC Strategy Forumでは、企業、アカデミア、および規制当局の専門家がバイオ医薬品のCMCについての研究開発、製造、規制等に関する課題に関して、十分に時間をかけて議論を行い、相互理解と課題解決を促進しています。
日本でのCMC Strategy Forumは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)と製薬協で準備委員会を組織し、テーマの選定や議論の方向性を決めるだけでなく、約1年をかけて準備を行ってきました。
会の開催に際し、CASSSのFellow、CMCフォーラムグローバル諮問委員会議長を務めるGenentech社のWassim Nashabeh氏とPMDA審査センター長兼RSセンター長の鈴木洋史氏からのWelcome and Introductory Commentsの後、以下のテーマで議論が開始されました。
 Genentech社 Wassim Nashabeh 氏
Genentech社 Wassim Nashabeh 氏
-
Session 1
Recent Trends in the Regulation of Biopharmaceutical Products
-
Session 2
CTD Quality part of Biopharmaceutical Products: Topics about ICH Guideline M4Q Revision and Structured Application
-
Session 3
Expectation for ICH Q6 Revision: Case Study of Commercial Specification Setting
-
Session 4
Key Strategies and Harmonization Efforts on Raw Material Managements of Cell Therapies -What for CAR-T
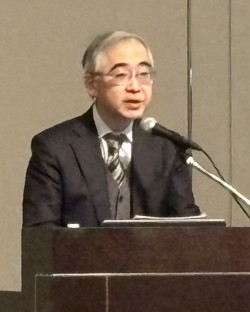 PMDA審査センター長兼RSセンター長
PMDA審査センター長兼RSセンター長
鈴木 洋史 氏
Session 1 – Recent Trend in the Regulation of Biopharmaceutical Products.
座長:PMDA再生医療製品等審査部 岸岡 康博 氏
Novo Nordisk社 Andrew Chang 氏
Session1では、バイオ医薬品および再生医療等製品を中心とした最新の薬事規制動向、国際協働審査の事例、新しい技術に対するガイダンスの説明等、幅広い内容が紹介されました。
PMDA再生医療製品等審査部 櫻井 陽 氏
日本におけるバイオ医薬品関連の薬事規制のアップデートとして、「中程度変更事項に係る変更手続きの導入の施行について」と「製造方法等の一部変更に係る承認後の製品切替え時期について」の通知について説明しした。また、今後医薬品になる可能性のある最新技術にから、マイクロバイオーム、エクソソームを含む細胞外小胞(EV)を利用した製剤、標的指向性を有するin vivo遺伝子治療用製品について説明しました。
米国食品医薬品局(FDA)医薬品評価研究センター(CDER) Stelios Tsinontides 氏
薬事規制当局国際連携組織(ICMRA)共同審査および共同調査のパイロットプログラムの背景、これまでに実施した共同審査および共同査察のフィードバックについて説明しました。
FDA 生物製品評価研究センター(CBER) Ingrid Markovic 氏
承認後変更管理実施計画書(PACMP)の米国での利用状況、2024年9月に発出されたプラットフォーム技術に関するドラフトガイダンス、CDPR Program、細胞・遺伝子治療における国際的な規制の収斂(CoGenT Global)のパイロットプログラムについて説明しました。
欧州医薬品庁(EMA) Brian Dooley 氏
CMCエリアでの2025年から2027年の3カ年計画(mRNAワクチンの品質・ファージセラピー等に関するガイダンス作成、市販後変更管理カテゴリーの見直しに係るガイダンス、ICMRA等外部組織との共同)について説明しました。
中国国家医薬品監督管理局医薬品審査センター(CDE) Dongchen Jia 氏
現在改訂が進んでいるICH Q6ガイドラインを中国に導入する際の考慮点を中心とした説明しました。
シンガポール保健科学庁(HSA) Subin Sankarankutty 氏
シンガポールの最新薬事行政の動向、シンガポールが参画している国際共同審査(ACCESS、 Orbis、HAS-NPRA work sharing、Asean共同審査)の状況、ICHおよびASEANガイドラインの導入状況について説明しました。
マレーシア国家医薬品規制庁(NPRA) Prasad Narayanan 氏
マレーシアの最新薬事行政の動向、マレーシアが参画しているASEAN 共同審査の状況について説明しました。
パネルディスカッション
パイロットプログラムとして実施している各種国際共同審査を今後実装するために考慮すべき点、期待すること等について活発な議論が行われました。
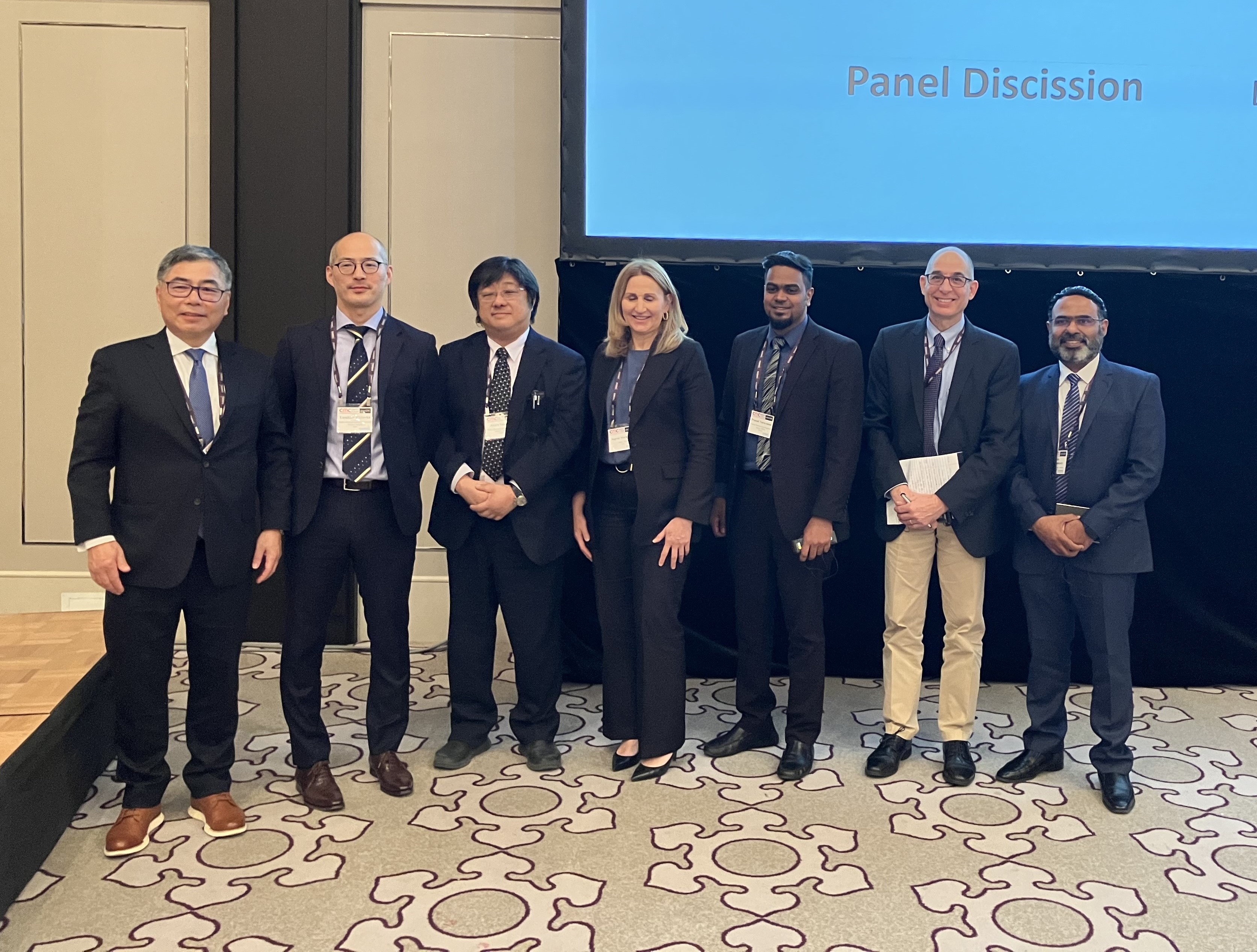 Session 1 集合写真
Session 1 集合写真
Session 2 - CTD Quality part of Biopharmaceutical Products: Topics about ICH Guideline M4Q Revision and Structured Application
座長:FDA CBER Ingrid Markovic 氏
アッヴィ合同会社 小島 孝夫 氏
コモン・テクニカル・ドキュメント(CTD)においてCMC情報が含まれる品質セクション(Module 2.3およびModule 3)は、ICHガイドラインM4Q (R1)により調和された構造・形式が2002年に導入されてから約20年が経過し、ガイドライン改訂のためのコンセプトペーパーが2021年に発表されました。コンセプトペーパーではガイドライン改訂の原動力として、近代の品質ガイドラインICH Q8-Q14やその他の関連するガイドラインとの整合、複雑な製品や技術(ADC、ワクチン、再生医療製品や連続生産技術など)のサポート、そしてデジタルツールの活用が挙げられています。Session 2では、FDA CBERのIngrid Markovic氏およびアッヴィ合同会社の小島 孝夫氏を座長とし、ガイドライン改訂に向けたICH M4Q(R2) EWGでの議論の最新状況および製薬企業からのICH M4Q(R2)への期待について紹介がありました。

PMDA再生医療製品等審査部 岸岡 康弘 氏
ガイドライン改訂の背景とICH M4Q(R2)の目的、EWGの現在の考え、そして今後の展望について解説しました。ICH M4Q(R2)では従来のICH M4Q(R1)からScopeを新モダリティへ広げ、さらに新しいICHガイドラインに示されている概念ついても取り込まれる見込みであること、そしてICH M4Q(R2)はDigitalizationに向けた役割も担っていることを示しました。また、Core Quality Information (CQI) およびDevelopment Summary and Justification (DSJ) といった現在EWGにて検討されている新しい概念について例とともに説明し、さらにCTD M3及びM2.3の基本構成としてのDescription, Manufacture, Control, Storage (DMCS) モデルについて解説しました。
バイエル薬品株式会社 大塚 裕司 氏
ICH M4Q(R2)の利点、製薬企業のミッションを踏まえたICH M4Q(R2)への期待、そして製薬企業としてのICH M4Q(R2)に関する考慮事項について説明しました。製薬企業からICH M4Q(R2)に期待する点として、①CMC申請資料のGlobalでの統一、②重要な点にフォーカスしたリスクベースでの資料作成、③承認後の変更管理の効率化、④新モダリティおよび新技術への対応、の4点についてそれぞれ製薬企業のミッションに照らし合わせて考察しました。
パネルディスカッション
Novo Nordisk Inc. のAndrew Chang氏、FDA CDERのStelios Tsinontides氏およびAmgen (Europe) GmbHのStephan Roenninger氏が加わり、ICMRAのような共同審査へのICH M4Q(R2)の貢献、ECなどのICH Q12におけるコンセプトとICH M4Q(R2)との調和、ICH M4Q(R2)がカバーするモダリティ等が活発に議論されました。
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子
Session3 – Expectation for ICH Q6 Revision: Case Study of Commercial Specification Setting.
座長:国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)生物薬品部長 石井 明子 氏
Novo Nordisk社 Andrew Chang 氏
医薬品の規格および試験方法の設定に関するICH Q6ガイドラインは、発行から20年以上が経過し、製造技術や分析技術の進歩、モダリティの多様化、新たなICH品質ガイドラインとの整合性などを背景に、ICH Q6A(R1) EWGで改訂が議論されています。Session 3では、国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部長の石井 明子氏とNovo Nordisk社のAndrew Chang氏の司会のもと、ICH Q6改訂の背景や目的、取り組む課題が紹介され、分析バリデーション/分析法の開発ガイドラインであるICH Q2/Q14との関連や、バイオ医薬品の事例をふまえた現状の課題と改訂ガイドラインへの期待が議論されました。
ICH Q6(R1) EWG Regulatory Chair/US-FDA CBER Ingrid Markovic 氏
ICH Q6改訂の背景や目的の他、科学およびリスクに基づく規格設定の考え方が国際的に調和されることによる承認審査の効率化やグローバル開発の促進、高品質で安全かつ有効な医薬品への患者アクセスの加速といったガイドライン改訂によって期待される効果を示しました。また、ICH Q8-Q14ガイドラインとの整合性や、Prior Knowledge、科学およびリスクに基づく規格設定およびライフサイクルマネジメントにおける考慮事項などのガイドライン改訂に向けて取り組む課題や方針についても説明しました。
中国食品医薬品検定研究院(NIFDC) Yu Chanfei 氏
抗体医薬品を例に中国薬局方などの公定法の要求事項や、バッチデータと工程能力に基づく規格設定アプローチを紹介しました。また、製品および工程に対する理解と臨床との関連に基づく規格設定の重要性を説明し、改訂ガイドラインへの期待を示しました。
国立医薬品食品衛生研究所 (NIHS) 柴田 寛子 氏
分析法の開発とライフサイクルマネジメントの観点からICH Q6とICH Q2(R2)/Q14ガイドラインの関係について解説しました。特に、ICH Q14で示された目標分析プロファイル(ATP)は、分析法の使用目的や分析法バラメータが満たすべき性能基準などから構成されており、重要品質特性(CQA)と関連するATP等によって分析法の頑健性や管理戦略に対する体系的な理解が深まり、管理戦略の一環としての規格および試験法についても医薬品ライフサイクルマネジメントにおける柔軟性が向上することが期待されると述べました。
中外製薬株式会社 水口 久美 氏
抗体医薬品を例にQbD手法を用いた管理戦略構築アプローチを紹介した他、規格設定における考慮事項と商用生産における問題事例を対比させる形で事例を紹介し、複数の製造サイトにおいて分析法の性能基準を合わせることや、限られたバッチデータに基づく規格設定の難しさを示しました。また、改訂ICH Q1/Q5Cとの整合性やPrior Knowledgeを活用した規格設定アプローチの例示、科学とリスクに基づく規格設定の考え方についての国際的調和の重要性など、改訂Q6(R1)ガイドラインへの期待を示しました。
ICH Q6(R1) EWG 製薬協トピックリーダー/旭化成ファーマ株式会社 山口 貴宏 氏
Q6改訂の背景の他、現行のQ6Bガイドラインにおける規格設定の課題とガイドライン改訂によって期待される効果をケーススタディ方式で説明しました。商用生産では開発中の限られた製造実績に比べてばらつきがより大きくなることが想定される一方で、承認取得後に規格幅を広げることは簡単ではありません。ばらつきの小さい開発中のバッチデータに基づき、狭い規格幅を設定することによってロット不良や製造管理コスト増大のリスクが高まるケースや、当局との交渉によって地域ごとに承認規格が異なるために供給管理が複雑になるケースが考えられる一方で、臨床との関連に基づく適切な規格値が受容されることにより、継続的なプロセス改善への柔軟性向上やグローバル市場における医薬品の安定供給と患者アクセスの向上が期待されることを示しました。また、科学とリスクに基づく管理戦略構築やその一環としての規格設定の考え方、医薬品ライフサイクルマネジメントを通じた製造技術や分析法の継続的な改善の促進、モダリティの多様化への対応などのQ6(R1)ガイドライン改訂に向けて取り組む課題についても紹介しました。
パネルディスカッション
ICH Cell and Gene Therapy Discussion GroupのラポーターであるGenentech社のKathleen Francissen氏とPMDAの白幡 祐貴子氏、協和キリン株式会社の土田 大介氏が加わり、Key Questionsや聴衆から寄せられた質問を端緒にして、薬局方の国際調和の可能性や臨床に関連した規格設定および規格を拡げる場合の考え方といったQ6(R1)改訂ガイドラインへの期待や、再生医療等製品における規格設定の難しさ、より進んだ開発アプローチ(ICH Q8-Q14)に基づく分析法や管理戦略に対する体系的な理解と規格のライフサイクルマネジメント、試行的導入された中等度変更事項の変更管理における位置づけなどについて活発な議論が展開されました。
 Session 3 集合写真
Session 3 集合写真
Session4 – Key Strategies and Harmonization Efforts on Raw Material Managements of Cell Therapies -What for CAR-T
座長:国立医薬品食品衛生研究所(NIHS) 再生・細胞医療製品部長 安田 智氏
Genentech社 Kathleen Francissen 氏
近年、細胞および遺伝子治療用製品におけるグローバル開発や上市件数が増加しており、こうした先端的医療用製品分野(Advanced Therapy Medicinal Products、ATMP)の開発要件を明確にするうえで、科学的根拠に基づいた規制の枠組みの国際調和の重要性が増しています。
Session 4では、NIHS再生・細胞医療製品部長の安田 智氏とGenentech社のKathleen Francissen氏の司会のもと、まず4名の演者がCAR-T製品の開発を例に、特に原材料および出発物質である白血球アフェレーシスの管理に焦点をあて、関連規制およびその相違に対処するアプローチについて規制当局または産業の視点から口頭発表を行いました。続くパネルディスカッションでは、新たに1名のパネリストを加えて意見交換および議論の深掘りされました。
ICH Cell and Gene Therapy Discussion Group ラポーター/ Genentech社 Kathleen Francissen 氏
ATMP開発における課題の技術的な議論の場として2023年10月に設立された、ICH Cell and Gene Therapies Discussion Group(ICH CGT DG、以下DG)のラポーターでもあるKathleen Francissen氏より、DGの活動概要およびその目標とする成果物に対する進捗が紹介されました。DGでは、既存のICHガイドラインをATMP開発への適用を鑑みた観点でレビューしながら、調和が必要とされる領域の特定を進めており、最終的には、特に調和を必要とする領域の優先づけを行った包括的なロードマップを作成し、既存のICHガイドラインの改訂もしくは新しいガイドラインの開発に関する勧告を行う計画としています。なお、同DGの活動範囲には、自家および同種CAR-T細胞などのex vivo細胞療法、ならびにin vivoウイルスベクターベースの遺伝子治療法の両方が含まれます。
米国食品医薬品局(FDA)生物製品評価研究センター(CBER) Ingrid Markovic 氏
US-FDAが2024年1月に発行したCAR-T細胞製品のCMC、非臨床および臨床開発に関するガイダンス(Considerations for Development of CAR-T Cell Products)をもとにお話しがありました。本ガイダンスでは製品ライフサイクル中に起きる、出発物質のドナー間のばらつきを考慮した同等性評価に関する推奨事項が含まれており、講演においても、同じ出発原料の1つのバッチを2つに分け、一方を旧プロセス、もう一方を新プロセスで処理し、得られた薬剤バッチを比較するSplit studyの活用が推奨されました。なお、その際、評価はペア統計テスト(paired statistical tests)で行うことが肝要とされます。
PMDA再生医療製品等審査部 西川 淳史 氏
典型的なCAR-T製品の製造プロセスを例に、生物由来原料基準を中心とした国内規制に基づく原材料の品質管理要件や適用される範囲(一次原料・二次原料の考え方など)について詳しい解説がありました。なお、同発表では、既存製品に汎用されるウイルスベクターを介した遺伝子導入を用いた場合だけではなく、ウイルスベクターを使用しない、piggy-BAC法による遺伝子導入やゲノム編集技術を用いたCAR-T製品に係る原材料の管理にも触れました。
A-SEEDS社 柳生 茂希 氏
同社が開発するpiggy-BAC法を用いたCAR-T製品における最新の知見を紹介し、CAR-T療法における品質管理や安全性評価の重要性を示しました。特に、T細胞の構成が最終製品の薬効と長期的な効果に与える影響について詳細なデータが提示され、臨床的な観点も交えて、原材料細胞の品質管理と製品特性および製造工程の最適化の重要性について示唆しました。また、最新の文献を引用しながら、CAR-T療法における二次がん発症の事例についても言及し、原材料細胞の特性やベクターの挿入部位、コピー数などの基準に基づきCAR-T製品の薬効や長期的な安全性を評価するうえでの課題を提示しました。
パネルディスカッション
ブリストル・マイヤーズ スクイブ社の宮武 佑樹氏も加わり、聴衆からの質問とKey questionsを中心に、グローバル開発におけるドナー適格性評価の検査項目や試験方法に関する各国規制要件の違いとその対応、CAR-T療法における二次がん発症リスクの評価や原材料管理を含めた品質管理および製造管理における考慮事項、CMC開発の初期から臨床を想定し適切な原材料を選定することの重要性、出発材料の特性評価や製造プロセスの一貫性を担保するための考え方、製品ごとに多様なアフェレーシスの手順などを採り上げました。関連して、他家製品の開発を想定した原材料細胞の供給体制、出発原料採取、品質管理、およびそれらを用いた製品の同等性・同質性の評価といった再生医療等製品開発に関する基準や規制要件の国際的調和への期待などについて活発な意見交換が行われました。
 Session 4 集合写真
Session 4 集合写真
終わりに
今回のフォーラムは2024年に引き続き対面にて開催され、各セッションのパネルディスカッションでは非常に活発な議論が交わされていました。また、フォーラム中に設定されていたNetworking ReceptionやNetworking Breakでは、国内外の産学官からの参加者がコミュニケーションを取ることができる非常に良い機会となっており、本フォーラムならではの良さを十分感じとることができました。
4つのセッション終了後、CASSS Board of DirectorsのVice PresidentであるJamie Moore氏から、本フォーラムの総括が実施され、閉会となりました。
このグローバル会議が、今後も日本で継続的に開催され、バイオ医薬品の研究開発の促進とCMC領域の活性化の一助になるよう、製薬協として支援を続けていきたいと考えています。今後ともみなさんのご支援をよろしくお願いいたします。
次回の「CMC Strategy Forum Japan 2025」は、2025年12月8~9日の開催を予定しています。
(バイオ医薬品委員会 柴田 瑞世、中村 奈央、吉松 美佳、鈴木 智香子、伊藤 宏昭)

