患者団体連携推進委員会 「第1回 患者団体アドバイザリーボード」を開催
第1回患者団体アドバイザリーボード(2017年6月28日):新任アドバイザーを交え製薬業界への期待や要望等を意見交換
1.「『病気』と『くすり』の情報に関するアンケート」結果報告について
患者団体連携推進委員会の喜島智香子委員長による挨拶の後、製薬協患者団体連携推進委員会 ビジョン2025対応タスクフォース(以下、TF)の高本昌弥リーダーから、「『病気』と『くすり』の情報に関するアンケート」結果報告について紹介が行われました。
「『病気』と『くすり』の情報に関するアンケート」は、「製薬協 産業ビジョン2025」に掲げた「患者参加型医療」の実現に向けた検討を進めるにあたって、患者自身やサポートする家族における、「病気」と「くすり」の情報にかかわる現状とご要望、さらに「製薬会社のくすり相談窓口」や「治験」に対するご意見等を把握することを目的として2017年2月1日~28日に郵送およびインターネットで実施しました。結果として対象とした全国の患者団体の会員やその家族、関係者の方々から391件(うち有効回答数375件)の回答をいただきました。
アンケート結果から、「患者さんの背景」について、375名の回答者のうち、患者さん自身が78.7%、ご家族が20%の回答であったこと、4分の3以上が難病・希少疾患の患者さんであったこと等が紹介されました。
「病気と治療に関する情報」や「くすりの情報」について、情報の入手先は医師、患者団体、インターネットであり、その情報に約7割の方が満足されているという結果でした。言い換えれば、約3割の方が満足していないということでもあり、医師からの説明が不十分であるという不満、インターネットの情報はなにを信頼して良いかわからない、また公的機関からのさらなる情報提供が求められているという結果でした。
また「製薬会社のくすり相談窓口」の認識とその利用実態については、利用された方はわずか4%でしたが、このアンケートを通してその存在を知った方の62.7%はぜひ今後利用したいとのことであり、「製薬会社のくすり相談窓口」への期待が感じられました。主なご意見・ご要望として、「製薬会社のくすり相談窓口」の存在を知らない、存在を広報してほしい、電話をするのに勇気がいる、相談の仕方がわからない、丁寧な対応でわかりやすく説明してほしい等が挙げられました。以上のことから、「製薬会社のくすり相談窓口」の業務について、なにを情報提供できるのかを明示しながら広報していく必要性が示唆されました。
「治験」の情報については、いずれの項目についても高い関心をおもちであることが理解できました。「治験」に関しては、医薬品評価委員会臨床評価部会より報告と提案がありました。
このアンケートまたは製薬協や製薬企業に対する主なご意見・ご要望として、良い薬を早く開発してほしいという声を多くいただきました。製薬協加盟会社の使命として革新的な医薬品の開発は製薬会社における原点と認識するとともに、このアンケートを実施させていただき、患者さんのニーズやご意見が再確認できたということは大変良かったと考えており、患者参加型医療を目指すうえで、各関係者や各委員会に対する目線合わせのためにも大事なアンケート結果になりました。
2.医薬品評価委員会からの提案について
続いて製薬協医薬品評価委員会臨床評価部会の神山和彦推進委員より「歩み寄りの第一歩~患者さんの声を活かした医薬品開発~」と題して報告と提案がありました。
医薬品評価委員会は医薬品の開発における課題について検討している委員会であり、2016年度からPatient Centricityの TFを立ち上げ、臨床試験について患者さんの声を取り込んだ医薬品開発を行っていきたいという考えで活動しています。TFが2016年度に行った「『病気』と『くすり』の情報に関するアンケート」の治験関連部分では、治験に関する情報が公的なウェブサイトに掲載されていることへの認知、治験に参加した場合、結果を知りたいか否か、治験に関する患者さんの意見を反映させる取り組みへの参加意向、医薬品開発プロセスに対する興味等をアンケートしました。
結果として、治験や医薬品開発に関して関心が高く、情報を具体的に知りたいと希望されている一方、公開情報が十分に認識されていない、治験や医薬品開発への参加の機会がかなり限定的である等の結果が挙げられ、もっと患者さんの声を反映させることを検討すべきと結論付けられました。
企業が患者さんと直接接触することがはばかられるという認識が根強くあるものの、今後はReal Life Experienceを取り込んでいくことが重要と考えられており、すでに海外では先行した事例がいくつか出てきています。最終的には双方にとってWin-Winになる関係が重要であり、早期の段階から患者さんの声を取り込んでいくことが重要と考えられています。
TFでは、双方のWin-Winを考える際、製薬業界側が考える「患者さんのWin」ではなく、実際に患者さんのニーズに合っているか、ずれているか、そうした観点でのご意見をぜひ患者団体のみなさんからおうかがいしたい旨の要請が提起されました(表2)。
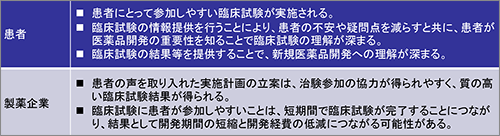 表2 患者、製薬企業それぞれのWin
表2 患者、製薬企業それぞれのWin
アドバイザーからのコメント
- Winを実現するための課題とは具体的になんだと定義しているのか?
- AMEDでも医師主導の臨床研究について患者さんの参加を募っていくことを検討しているが、単に話を聞くだけでなく一緒にこう改善したいというステップを考えるべき。
- 患者さんのニーズと医師のニーズが同じとは限らないので、患者さんのニーズを知っていただくこともWinに入るのではないかと思う。
- 治験に関連する情報となると、個々の患者さんレベルでは言葉すらわからないことがある。特に横文字がまったく通じていないという状況等に鑑み、どのように対応したら良いか考えていくことも重要である。
- 子供の病気の薬の開発についても、患者さんの声を取り入れて進めてほしい。
3.団体の「活動内容、製薬業界への期待・要望等」について
(1)一般社団法人 全国がん患者団体連合会 理事長 天野 慎介 氏(新任アドバイザー)
一般社団法人全国がん患者団体連合会(以下、全がん連)理事長の天野慎介氏より、全がん連設立前の活動から設立に至る経緯も含めて、ご自身の活動についてご紹介をいただきました。
私自身は悪性リンパ腫を2000年に発症し、悪性リンパ腫の患者団体である「一般社団法人 グループ・ネクサス・ジャパン」の活動に加わり、その後、 全がん連理事長に2015年に就任しました。がん対策については2000年以降、未承認薬使用問題(いわゆるドラッグラグ問題)や、 均てん化の問題が患者団体から指摘されるようになり、2006年がん対策基本法の設立に結び付きましたが、たくさんの患者さんや家族の方が声を挙げたことが成立につながったと考えています。
私も2009~2012年にがん対策推進協議会の委員を務めました。5名の患者委員とともに最初に取り組んだのが、経済的負担の軽減の問題でした。当時は外来診療には患者立替が必要で、第2期患者委員が連名で外来診療における高額療養費限度額認定の適用を願い出て2012年度から適用されました。今の高額ながん治療薬の登場を考えると、これが認定されなければ患者さんは相当な負担を強いられることになっていたと思います。そのほか、ドラッグラグについても第1期から問題意識をもっており、特に適応外薬の問題については当時同協議会で適応外薬問題に対する対応を要望しましたが、それが今の拡大治験につながっていると考えています。
がん患者さんの活動は地方でも活発に行われています。私も沖縄県がん診療連携協議会の委員を務めており、がん診療連携拠点病院の問題にも携わりました。沖縄県は離島が多い地理的な問題、またがんで入院治療していた患者さんの経済的問題等が大きな課題になっています。私たちも乳房温存を希望する離島の患者さんのために県との協定のもと2013年から金銭的支援を行ってきました。
一口にがんといってもさまざまな病態、治療があるので、それぞれのがん種により患者会があり、地域の実情も異なります。患者会はそれぞれの実情に沿った声を挙げることになりますが、がんにおいての共通するテーマや医療費の問題についてはバラバラに声を挙げても届かないとの思いがありました。たまたま2016年に第2期医療計画が終了するタイミングがあり、また国会でもがん対策基本法改正が超党派議連で話し合われていたこともあり、がんの患者会の連合組織を作る必要があるのではないかとの思いが募り、全がん連が発足したという経緯です。
最初の活動として、日本難病・疾病団体協議会(JPA)と協働で要望活動を行いました。当初は連合会で要望書を出していましたが、JPAから示唆をいただきJPAとともに記者会見を行いました。われわれは当初から要望活動、政策提言活動を中心にしようとねらったわけではなかったのですが、結果として要望活動が中心になっています。
がん対策基本法の改正にあたっては、国政の重要なテーマになっておらず、成立が見通せない状況のなか、個別質問書を送る等して、なんとか2016年12月にギリギリ成立したという経緯がありました。この改正がん対策基本法には、社会全体でがん患者さんを支えるべきとの趣旨の文言を入れていただいています。また、希少がんや難治性がんについては支援が少ないため、希少がん、難治性がん支援に関する文言も入れていただきました。さらに院内がん登録については可視化をしていかなければならないということで、学会等と協働して患者さんに対してわかりやすい情報を提供するプロジェクトも今後行っていく予定です。
また、学会との連携ということでは日本緩和医療学会とシンポジウムを共催したり、厚生労働省の「がんゲノム医療推進コンソーシアム」についても患者団体として加わっています。がん患者さんについては、リスクの高いがんであると保険加入を断られる等いろいろな問題あり、これらの問題についても提言を行っています。
最後に、治験情報に関しては、患者さんが日本医薬情報センター(JAPIC)の臨床試験情報にたどり着くのは至難の業であり、必要な情報を得るのが難しいという問題を指摘しておきたいと思います。

(2)認定NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML 理事長 山口 育子 氏(新任アドバイザー)
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(以下、COML)理事長の山口育子氏より団体の活動紹介と製薬業界への期待・要望等をお話しいただきました。
COMLは1990年より活動をスタートいたしました。その当時はがん患者にがんであることを伝えることはタブーで、当事者である自分のことを知るのにとても努力が必要な時代でした。患者さんが「この薬は何ですか」と聞くと「あなたに必要な白い錠剤」と回答され、「どうせ素人が聞いてもわからないのだから知らなくとも良い」という風潮で、患者さんの立場で活動をすると、「なにか厳しい要求をするのでは」と構えられてしまう時代でした。
そこで、そのような受け身でお任せの患者さんに「それで良いのですか」と問いかけることからCOMLの活動は始まりました。患者さん自身が「いのちの主人公」、「からだの責任者」として「賢い患者になりましょう」と呼びかけ、「患者さんと医師は対立ではなくともに協働しよう」という考えで活動を行いました。医師にお任せするだけでなく、患者さんも「自分にできる努力とはなにかということを考えよう」、「積極的に治療に参加し課題解決のために提言できる患者市民になろう」という思いで活動を行っています。
具体的な活動の1つ目は、電話相談です。COMLでは医療者ではないスタッフが対応にあたっていますが、相談件数が今までに、約5万8000件寄せられています。「入院治療から通院治療へとシフトするようになり不安を感じている」といった本音を聞き出してアドバイスします。最近では精神疾患患者さんが増えている現状があり、それらの方々の思いを受け止めて気持ちに寄り添うような活動を行っています。電話相談の1件あたりの平均時間は40分以上、ときに1時間半を超えることもあります。COMLは設立以来大阪で活動を行っていますが、相談の電話は全国から寄せられています。
2つ目は、1991年1月から始めた患者塾という活動です。話題提供も行いますがメインになるのは参加者の意見交換で、グループディスカッションを中心に行ってきました。最近はお金をかけてでも話すために出向く方が減ってきています。インターネットで簡単に情報が取得できる時代であることが理由だと考えます。それでも答えのないテーマや医療費の話はどこにも載っていないので、逆に参加者が増える傾向にあります。
3つ目は、SP(模擬患者)活動で、これは1992年から始めました。医学部、歯学部、薬学部で医療面接を含めた客観的臨床能力試験が義務化されており、医療面接の相手役として医学教育に参画しています。POST-CC-OSCE(臨床実習終了後オスキー)が2020年より開始されることに対応するため、2017年度からトライアルが始まっています。
病院探検隊の活動も行っています。病院の改善に利用者である患者さんの視点を活かしてもらおうと1994年から始めた活動で、実際の病院の見学、受診を通じてその病院のもつ課題を伝える活動です。最近では慶應義塾大学病院や千葉大学病院等大きな病院からも声がかかるようになりました。
さらに、患者さんのコミュニケーション力を高め、自ら気づくこと、問題点に気づけるワークショップも2001年から行っています。独自開発のプログラムで、最近では医療者の方も含めて参加できるよう「患者と医療者のコミュニケーション講座」として行っています。
これとは別に、「医者にかかる10箇条」という小冊子を1997年に厚生省からの依頼で素案を作る形で作成しました。共同通信の記事配信もあり4万冊印刷したところ全国から大反響があり3ヵ月で在庫切れになりました。また2014年には子どもの『いのちとからだの10か条』も3万冊を無料配布しました。
他に、患者市民の医療への参画のために「医療をささえる市民養成講座」も行っています。COML創始者である辻本好子の「医療をささえる市民を増やす必要がある」という思いから、個人的な問題だった医療の問題から社会への視野を含めた課題に気づける市民の育成を目的にしています。今後は各種医療関係会議への一般委員養成講座、バンク化構想を始める予定です。
最後に製薬企業への要望ですが、医薬品のマイナス情報・リスクが正しい形で伝わっていないと感じています。副作用への過剰な心配等くすりの不安を解消することは重要と考えます。また患者さんの情報へのリテラシーを高めることも重要です。具体的に求めることとしては、製薬企業には、どのようなことができてどのようなことができないのかを明確にしたうえで、くすりの情報に関して、できることを具体的に伝えていく努力をしていただきたいと思います。
今後は患者情報室での情報提供活動を積極的に行っていきたいと思います。たとえば製薬企業の冊子やパンフレットは一番人気ですので、切らさないように補充するよう留意しています。一方、製薬企業にも、冊子やパンフレットを患者さんの目につく手に取りやすい場所に置く等の活動を、業界全体を挙げて取り組んでいただきたいと思います。

4.患者団体セミナーのテーマに関する意見交換
製薬協で毎年開催している患者団体セミナーのテーマについて、アドバイザーの方々にご意見をうかがいました。冒頭、喜島委員長より、患者団体セミナーTFではテーマとして、第1部はがん患者の就学就労、希少疾患の患者さんの治験リクルーティング等、第2部はビッグデータ、リアル・ワールド・データ(RWD)の活用、iPS細胞、ゲノム診療、新規医療技術、医療でのAI活用等を候補と考えていることについて説明があり、意見交換に入りました。
アドバイザーからのコメント
- iPS細胞、ゲノム診療についての情報は患者からの問い合わせが多く、ここ数年で急速に変化している情報である。また医療政策のトピックスについての要望もある。
- 特定疾患だけでなく俯瞰した意見が言える方が求められているので、広範囲にわたって学べる場がほしい。
- 患者家族からの意見等が反映できる場が少ない状況がある。
- 就学や就労に関しては相談としては増えている案件であるが、製薬協がこの問題を採り上げるのは難しいのではと考える。
-
がんの領域では、患者団体のリーダーとして知らないといけない内容、法整備が進んでいる制度等を採り上げてほしい。
- いろんな委員会や行政に対して意見をきちんと言えるリーダーを育成していく必要があると考えている。こうしたリーダー育成に関する話題を採り上げてほしい。
- 個人情報保護法案等のような患者団体としても知っておかないと対応できないようなテーマを含めてほしい。
閉会挨拶
最後に製薬協の田中徳雄常務理事より閉会挨拶がありました。
「今回から新たに2名が加わり5名の皆さんにアドバイザーをお願いしてますが、良いスタートを切ることができたと思います。この委員会は患者さんのご意見をお聞きしながら活動することが重要と考えています。これから2年間、どうかよろしくお願い申し上げます」と締めくくり、「第1回 患者団体アドバイザリーボード」は閉会しました。
患者団体連携推進委員会 本山 聡平

