「欧州製薬団体連合会(EFPIA)との定期会合」を開催
2025年03月07日
製薬協国際委員会欧米部会では、欧米の政府・製薬団体と協調し、国際的課題の解決を図る活動の一環として、欧州の製薬団体との定期会合を毎年実施しています。2024年度のEFPIAとの定期会合は、1月27日にオンライン形式にて開催されました。今回は双方合わせて約30名が参加し、活発な意見交換が行われました。以下、会合の概要を報告します。
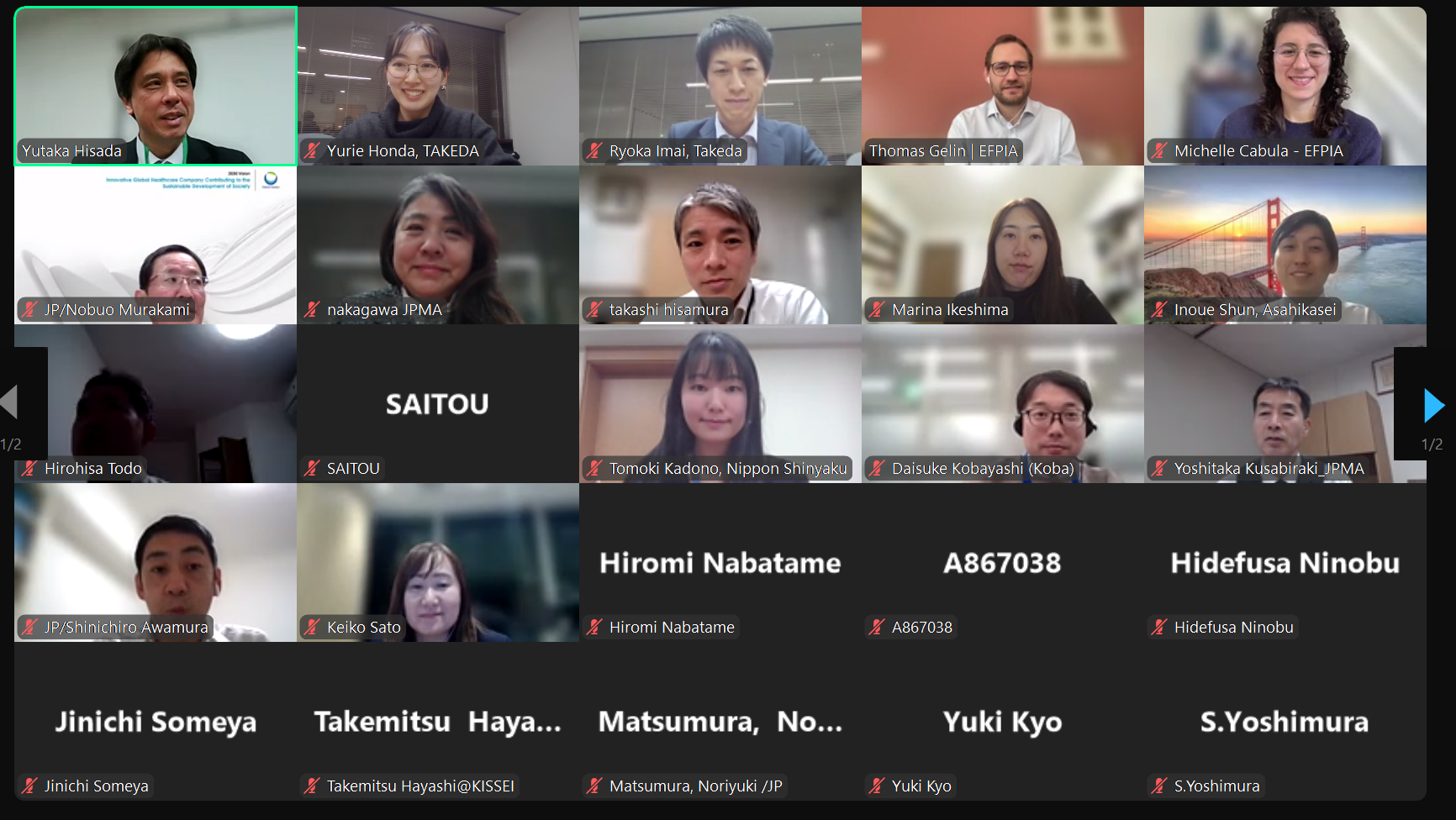 オンライン会合の様子
オンライン会合の様子
はじめに
冒頭、EFPIAのExecutive Director であるThomas Gelin氏の挨拶から会がスタートしました。本会合は日本と欧州の協力関係の重要性を示すものであり、情報交換を通じて2025年に向けた連携強化の方法を模索したいとのコメントが述べられました。製薬協の中川祥子常務理事からも、長年にわたりEFPIAと製薬協が協力関係を築いてきており、本会合にて率直な意見交換が出来ることを期待するとのコメントが述べられました。
Policy landscape after EU election - impact on the healthcare industry and EFPIA’s advocacy strategy & Update on the revision of the EU pharmaceutical legislation(RDP and access)and EFPIA 2025 advocacy strategy
EFPIA, Public Affairs, Martina D’Amore 氏
Martina D'Amore氏より、2024年のEUにおける政治情勢の変化と欧州一般医薬品規制改正の現状が紹介されました。
質疑応答では、EFPIAのアドボカシー活動について、EU加盟国各国や英国・米国などEU域外とも連携していることや、西欧と東欧の医療アクセスにおける格差を理解するため、データ収集と分析に基づいた活動を実施していることなどが議論されました。
Urban Wastewater Treatment Directive(UWWTD)
EFPIA, Public Affairs, Athina Giannoutsou 氏
Athina Giannoutsou氏より、EUの都市排水処理指令(Urban Wastewater Treatment Directive)に関する説明が行われました。本指令は、環境保護と市民の健康向上を目的としており、EU全域での排水処理レベルの向上を義務付けるものであり、2028年以降は製薬業界および化粧品業界に対して生産数量に応じた汚染負担金の支払いが求められること等が紹介されました。
質疑応答では、今後の各EU加盟国での国内法への反映方法や医薬品・化粧品業界のみが財政負担を負う点等に関する質問があり、EU加盟国ごとに多少の柔軟性はあるものの、基本的な内容は統一される見込みであること、医薬品業界への影響により企業の競争力低下等の懸念があることなどが言及されました。
Update on Japan pricing and reimbursement environment
製薬協 産業政策委員会 産業振興部会 草開 義隆 部会長
草開義隆部会長より、2024年度の薬価制度改革の概要の紹介とともに、この改革により革新的医薬品を評価しイノベーションを促進する方向へ政策がシフトしたことが説明されました。これらはEFPIAやPhRMA(米国研究製薬工業協会)と協力して行った、積極的なロビー活動により得られた業界活動の成果であることも共有されました。
また、2025年の中間年改定に対する業界提案および政府による改定方針についても概説がありました。ディスカッションでは、今後の薬価制度改革に向けたアドボカシー活動等について意見交換が行われました。
Safety of supply:Progress of Critical Medicine Alliance/Act
EFPIA, Economic and Social Affairs, Pablo Tovar 氏
Pablo Tover氏より、安定供給の話題として、欧州のCritical Medicines Act(重要医薬品法)およびCritical Medicines Alliance(以下、アライアンス)を通じたEFPIAの活動が紹介されました。
欧州ではパンデミックを経て、医薬品の供給不安がEUおよび各国レベルで重要な保健政策課題となっており、重要な医薬品の安定供給およびサプライチェーンの脆弱性に対処することを目的とした重要医薬品法の制定が見込まれていること、当該法案に関し包括的な議論を行う場としてアライアンスが発足しており、EFPIAも含め議論を進めていること等が説明されました。質疑応答では米国の政治動向を踏まえた欧州への影響や、今後の展望についての質問と意見交換が行われました。
European Collaboration on Health Technology Assessment
EFPIA, Market Access, Mihai Rotaru氏
Mihai Rotaru氏より、2025年から運用が開始されるEU共同医療技術評価(HTA)の概要について説明がありました。欧州では、HTAに関して共通の枠組みがありませんでしたが、EU共同HTA導入により共同臨床評価(JCA:Joint Clinical Assessment)が実施されることとなり、EU各国におけるHTAの臨床評価が合理化されること等が紹介されました。また、臨床試験の計画段階で、欧州医薬品庁(EMA) だけでなく HTA 機関からも科学的アドバイスを求める機会が与えられることから、臨床開発計画をより適切に設計できるようになることが期待される一方で、各国において共同臨床評価レポートをどのように活用するのか決まっていないこと等について言及しました。
Discussions on the collaboration between EFPIA and JPMA
日本と欧州、それぞれにおけるこれまでの活動の成果について共有し、今後両団体でどのように連携していくのが良いかの議論が行われました。連携の例として、日本ではEFPIA・PhRMA・製薬協の3団体のジョイントステートメントを出していることを受け、欧州においても欧州政府へのステートメントや書簡を両団体合同で提出する可能性についても言及しました。
終わりに
EFPIAのExecutive Director であるThomas Gelin氏より、有意義な意見交換ができたことへの謝意とともに、今後も連携を強化し、実際に取り組みにつなげていくことへの期待が述べられました。
また、製薬協国際委員会の村上伸夫委員長より、今後の業界全体の発展に向けて、EFPIAと製薬協の協力を強化し、より良い未来を築いていきたいとのコメントが述べられました。
(国際委員会 欧米部会 欧州グループ EUチームリーダー 井上 峻)

