英国製薬工業協会(ABPI)との定期会合を開催
2024年12月25日
製薬協国際委員会欧米部会では、欧米の政府・製薬団体と協調し、国際的課題の解決を図る活動の一環として、欧州の製薬団体との定期会合を毎年実施しています。2024年の英国製薬工業協会(ABPI)との定期会合は10月11日に対面(+オンライン)にて、製薬協の眞鍋淳副会長も交えて開催されました。
前日には科学・研究・イノベーション省のPatrick Vallance大臣 との面会、日英間の友好関係の強化を主な目的として組織された団体であるJapan Society主催のレセプションと議会ツアー、11日の午後には在英大使館との面談も行われました。Vallance氏との面会では、日英の強いIP保護の姿勢とイノベーション創出のパートナーであること、イノベーションの結果として医薬品の患者アクセスが重要であることなどを確認し、眞鍋副会長から英国における日系企業のビジネス上の課題と新政府への期待をまとめたposition paperを手交しました。
今回は双方合わせて現地で23名、加えてオンラインからも日本製薬団体連合会(日薬連)と製薬協の複数委員会 から多数参加し、活発な意見交換が行われました。
以下、会合の概要を報告します。
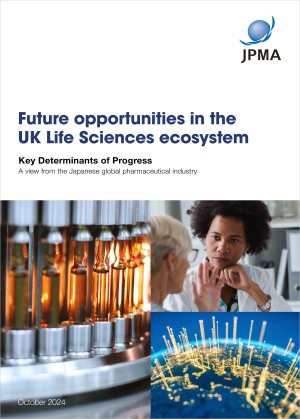
はじめに
冒頭、ABPI Executive Director International Policy & UK CompetitivenessのClair Machin氏より、歓迎の言葉と、日英はIP保護をはじめとする多くの立場をともにし、互いに学びを共有し合う建設的で重要な関係として今後も関係を深めていきたい旨の挨拶がありました。眞鍋副会長からは、日英はIP堅持の立場でイノベーションが推進される環境にある中、英国は商業環境には課題があるものの患者連携が進んでおり、新政府の方針も学びながら協力し合っていきたい旨の挨拶がありました。
ABPIからは新政府のライフサイエンス政策と患者連携の最新動向について発表がありました。
日本からは、日薬連より薬価償還の最新動向や創薬力強化、ドラッグ・ラグ/ロス解消などの政府の取り組み、および患者団体連携推進委員会より患者連携の最新動向について紹介しました。
Update on Japan pricing and reimbursement environment(JPMA)
日本製薬団体連合会 保険薬価研究委員会 田代 泰之 氏
田代氏より日本における薬価制度の最新動向や創薬エコシステムサミットをはじめとする創薬力強化、ドラッグ・ラグ/ロス解消などの政府の取り組みが紹介されました。はじめに薬価制度について、まずは日本の製薬業界を取り巻く環境として、国内外の環境変化によるサプライチェーンの見直しと再構築、安定供給問題やドラッグ・ラグ/ロスの問題について紹介しました。2024年度の薬価制度改革において、政府はイノベーションの適切な評価と創薬力強化を重視しており、業界のアクションとして(1)革新的新薬の特許期間中の薬価の維持、(2)薬価収載の際のイノベーションの適切な評価、(3)薬価再算定ルールに対する異議、などが挙げられました。概して日本の2024年の薬価制度改革は、全体としてポジティブであったとまとめました。
続いて創薬力強化への取り組みについて、2024年の7月に政府からコミットメントが出されたこと、それに対して製薬協が「新薬を患者さんに迅速に届けること」「世界の主要な創薬の拠点の一つとなること」「投資とイノベーションの循環が持続する社会システムを構築すること」といった取り組みを行っていることを紹介しました。
質疑応答では、制度改革にあたっての当局との交渉の可否やイノベーション評価の状況、予防医療への取り組み、安定供給への対応などについてABPIより質問がありました。日本においては、企業は従業員に健康診断を受けさせる義務があるほか、国民の健康に対する意識が高く、英国と比較すると検査へのアクセスが良いと紹介しました。また、安定供給の問題について、在庫の可視化が進んでいないことや、原薬の海外への依存が主な原因であると述べました。
New UK Government priorities for Life Sciences(ABPI)
Colette Goldrick, Executive Director Corporate Affairs & Strategy
Colette Goldrick氏より、新政権の体制の紹介、5つのミッションとそれらへの見解、治験環境改善を含む国民保健サービス(National Health Service、NHS)改革、経済成長の柱とする新政府ライフサイエンス政策における前政権のLife Science Visionの実行や疾病予防対策重視など、優先事項の紹介がありました。

質疑応答では、英国における治験環境や特定の疾患における治療開始までの待機期間の課題、英国国立医療技術評価機構(NICE)における医療技術評価に対する業界の受け止めなどについて意見交換を行いました。NHSにおける新薬使用への躊躇や、地域によるNHSでの新薬をはじめとする医療アクセスの不平等が、医療関係者の深刻な人材不足によりコロナの影響から回復しきれていないことが述べられました。また、NHSの医薬品の財源について、業界との協定で売上金の一部が返却される協定があるものの、それが直ぐには新薬の処方に直結されない背景などが紹介されました。
Patient Engagement – ABPI’s recent activities(ABPI)
Amit Aggarwal, Executive Director Medical Affairs and Strategic Partnerships およびゲストスピーカーNicola Perrin, Chief Executive AMRC(Association of Medical Research Charities)
ゲストスピーカーであるAMRC のNicola氏より、患者団体(英国ではより広義にCharity Organizations)の立場から、ご自身の団体の役割や患者団体の立場として、企業その他のステークホルダーとの協働に関する知見が共有されました。AMRCは、英国での医療研究に資金投資を行う団体を統括する団体として、資金だけでなく患者さんの声も反映させる、いわば両者の橋渡し的な存在を担っています。
産業界の代表であるABPIとの連携の中で、患者さんのために何が必要か、という観点では業界と患者団体との間で同じ考えを共有しており、ともに協力することでより力強い声を発信していけるだろうとの前向きなコメントがありました。
ABPIのAmit Aggarwal氏からは、患者さん・国民の医療への参画についてのABPIの取り組みについて紹介がありました。Patient Advisory Councilの設置により、ABPIのリーダーシップの意思決定に患者さんの声を反映させていることや、20年ほど前から存在する患者団体フォーラム(ABPIメンバー企業や多数の患者団体が参加する団体)では、情報共有などにおいて協力し合うことに関するベストプラクティスを共有しているとの説明がありました。ABPIも加入しているPatient Information Forumは、“信頼に値する医療情報を発信している団体に付与される認定制度”の管理・運用を行っており、ABPIは認定ステータスを連続して付与されていることの紹介などがありました。
またABPI独自でも、団体規模にかかわらず、患者団体が資金提供に関する透明性を保つためのガイダンスを発信するほか、製薬企業と患者団体が協働しやすくするためのサポートを積極的に行っていることが紹介されました。
質疑応答では、日本でも製薬協あるいは個社として、より対等な関係性・体制のもと協働を進めていくにはどうすべきか、といった点について、患者参画は非常に重要な観点であるが、「これを実施したからOK」ということではなく、実際のアウトカムを重視し、成果や実装を注視していくことが必要であるとのコメントがありました。
また、企業と患者団体の協働における透明性の確保については、まずは患者団体の独立性を尊重し促進することと、そのうえで創薬・治験・医療技術評価・薬価償還といったプロセスの中で、より早い段階から患者団体の関与を促進すること自体が、相互の利益相反を避けることになるのではとの示唆がありました。英国でも患者団体の規模や性質は異なり、コロナ禍では国民の中でも医療格差が顕著になりました。現在の傾向としてダイバーシティとインクルーシブネス、そしてリーチアウトという3点が重視され、可能な限りすべての患者団体・患者さんの声を聞き、汲み上げていこうという動きがあるとの現況も共有されました。
Update on Japan Patient Engagement(JPMA)
製薬協 患者団体連携推進委員会 三澤 賢治 委員長
三澤氏より、製薬協の患者団体連携推進委員会の組織体制、スコープ、最近の活動について紹介しました。PPI(患者・市民参画)に関する各ステークホルダーの活動概要のまとめ資料等により委員会メンバーのケイパビリティを向上させる取り組みや、「創る会(臨床試験にみんながアクセスしやすい社会を創る会)」「くすりビジョナリー会議」といった場への参画により、患者団体をはじめとする各ステークホルダーとの相互理解と協働を進めていることを共有しました。
製薬協からの発表に対しては、ABPIの活動との整合性や共通点に感銘を受けたといったコメントや、使用しているフレーズ・表現が非常に的確であるといった感想がありました。
終わりに
ABPI Clair Machin氏からは、活発な議論への感謝が述べられ、議論により理解が深まったことへの感謝の言葉がありました。製薬協国際委員会の中垣寿副委員長からは、英国新政府のライフサイエンス政策や患者連携について意見交換への感謝の言葉とともに、今後の政府への期待と、両団体の益々の活発な交流への期待が述べられました。
各セッションにおいて活発な意見交換がなされ相互に理解が深まるとともに、今回は眞鍋副会長の同行により、政府関係者との面談と製薬協の立場を伝えるposition paperの手交の機会を得るなど、密度濃く非常に有意義な訪英となりました。また、これらの活動の準備に際して不可欠であった、英国における日本のライフサイエンス業界団体であるJPG(Japanese Pharmaceutical Group)にこの場を借りて感謝いたします。今後益々の関係深化に努めて参ります。
次回は2025年度に開催の予定です。
(国際委員会 欧米部会 欧州グループ 英国チーム)

