「2024年度 製品情報概要管理責任者・実務責任者研修会」を開催
2025年3月25日に「2024年度 製品情報概要管理責任者・実務責任者研修会」を開催しました。当日は、会員会社の製品情報概要管理責任者・実務責任者をはじめ、各社で資材審査を担当している方を中心に、約550名の参加がありました。以下、本研修会の概要について報告します。
 会場の様子
会場の様子
プログラム
| 司会 | 製薬協 製品情報概要審査会 井上 智浩 委員 |
|---|---|
| (1)開会挨拶 | 製薬協 製品情報概要審査会 近藤 充弘 委員長 |
| (2)広告規制と作成要領について | 製薬協 製品情報概要審査会 木村 正彦 委員 |
| (3)作成要領に関するご質問から | 製薬協 製品情報概要審査会 今 洋一郎 委員
同 横山 民代 委員 同 三宮 健一郎 委員 |
| (4)特別講演「医療関係者から見た情報提供のあり方について | 特別講演司会:製薬協 製品情報概要審査会 荻原 香奈恵 委員
演者:慶應義塾大学病院 医薬品情報担当 中田 英夫 氏 |
| (5)閉会挨拶 | 製薬協 石田 佳之 常務理事 |
(1)開会挨拶
製薬協 製品情報概要審査会 近藤 充弘 委員長
はじめに、会員会社の皆さんが医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領(以下、作成要領)を遵守し、徹底していただいていることに対する感謝の意が表明されました。
本研修会で取り上げているテーマの重要性に関して述べ、監視事業等の変化を理解し、変化を前向きに捉え、医薬品情報を正確かつ適切に医療関係者に提供することの重要性で締めくくられました。

(2)広告規制と作成要領について
製薬協 製品情報概要審査会 木村 正彦 委員
作成要領の背景には、法規制として、薬機法、医薬品等適正広告基準、販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協の自主基準として製薬協コード・オブ・プラクティスがあり、資材作成にあたっては、作成要領はもちろんのこと、これらの法規制および自主基準を充分に理解しておくことの重要性が説明されました。また作成要領の理解にあたっては、作成要領のe-learning2023年版をご活用いただくよう、再紹介がありました。
プロモーション資材・広告の監視の眼は厳しくなっており、製薬協による審査は、製造販売承認後3か月間を目安として作成された、「製品情報概要」と「広告」という限定された資材を対象としています。そのため、会員各社がこれらの法規制および自主基準、作成要領を理解し、社内審査を徹底いただくことが最も重要であることが紹介されました。

最後に、医療用医薬品製品情報概要管理責任者および実務責任者は、各責務を理解いただき、各社のプロモーション資材を引き続き適切に作成するよう依頼しました。
(3)作成要領に関するご質問から
有効性(統計)について
製薬協 製品情報概要審査会 今 洋一郎 委員
本セッションでは、会員会社の皆さんから質問いただいた下記テーマについて、製薬協審査会で審査する際の見解を紹介しました。
-
名目上のp値
- 名目上のp値を根拠とした際の表現について
- 名目上のp値の記載は、臨床成績における規定であること
- 検証の枠組みに含まれる「第1種の過誤を考慮した解析のp値」について -
検定手順
- 検定の手順の終了の記載の必要性について
- 具体的な事例の紹介

有効性(その他)について
製薬協 製品情報概要審査会 横山 民代 委員
本セッションでは、会員会社の皆さんから質問いただいた下記テーマについて、製薬協審査会で審査する際の見解を紹介しました。
-
サブグループ解析
- 「一貫していた」の記載について
-
参考情報
- 「評価指標や評価スコアの定義が明確・一般化されたもの」の考え方について
- 日常活動性、QOLの下位尺度の参考情報の取り扱いについて -
Limitation
- Limitationの記載の対象となる試験について
- 「目立つように記載」することの設定背景について

安全性について
製薬協 製品情報概要審査会 三宮 健一郎 委員
本セッションでは、会員会社の皆さんから質問いただいた下記テーマについて、製薬協審査会で審査する際の見解を紹介しました。
-
安全性
- 「安全性の強調・保証」となる表現例について
- 二重盲検期と継続投与期(延長期)がある臨床比較試験で、当該薬へ切り替える試験デザインの
継続投与期(延長期)のみを紹介する場合においての安全性結果の記載例について
- 表のみでの記載事例について
- 「人年法」での記載事例について
- 副作用(又は有害事象)の事象名が多い場合の記載事例について

(4)特別講演
医療関係者から見た情報提供のあり方について
慶應義塾大学病院 医薬品情報担当 中田 英夫 氏
講演では、薬剤師業務の変化、「医薬品情報室」の業務の現状、そして、製薬企業からの情報提供の重要性について以下が述べられました。
- 薬剤師業務の変化については、医薬品情報の対応が医薬品情報室担当者だけでなく、すべての薬剤師に求められるようになり、病棟薬剤師も積極的に医薬品の相談や情報提供を行うようになっていること。
- 「医薬品情報室」の業務に関しては、病棟における医薬品情報の提供の主体が病棟薬剤師に移行しつつある中で、医薬品情報室は院内の情報センターとして、幅広い医薬品情報を収集・評価・管理し、病棟薬剤師と連携しながら情報を発出する役割を担っていること。また、より専門的な相談にも応じることが求められていること。

- 製薬企業の方へのお願いとしては、剤型変更に関する情報提供の必要性や、添付文書では情報が限定的で不足することがあるため、現場では審査報告書も活用していること。
最後に、医薬品情報は「取り扱うこと自体」が目的ではなく、それを使いこなして「医療の質の向上と効率化に寄与すること」が目的であり、「患者へのアウトカムを意識した業務につなげる」ための手段であること。適正使用のための「必要十分な情報提供」や、特にどのような方にどのような注意が必要なのかという情報が重要であると締めくくられました。
(5)閉会挨拶
製薬協 石田 佳之 常務理事
製薬企業は、医療関係者に医薬品を適切に使っていただくよう、医薬品情報を医療関係者へ正しく伝えることが大切です。本日の研修会では、前半がどのように(プロモーション資材を)作るか、後半がどのように(医薬品情報を)届けるか、という内容でした。医薬品情報に関わるみなさんは、作ることと届けることをセットで考えて、医療関係者にプロモーション資材と共に医薬品情報は本当に正しく届いているか、また、適切に医療関係者に活用されているか、見届けつつ活動してほしいと述べ、引き続きの会員各社の理解と協力を求めたうえで、会を締めくくりました。
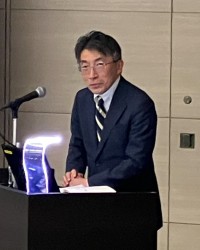
(製品情報概要審査会 竹内 裕恵、菅 えみ)

