「2024年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」を開催
製薬協コード・コンプライアンス推進委員会は、2025年3月17日、「2024年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」をオンライン形式にて開催しました。本会には、会員会社から、コンプライアンス管理責任者、コンプライアンス実務担当者を含む159名/69社が出席し、表1のプログラムに沿って実施しました。以下、本会の概要を報告します。
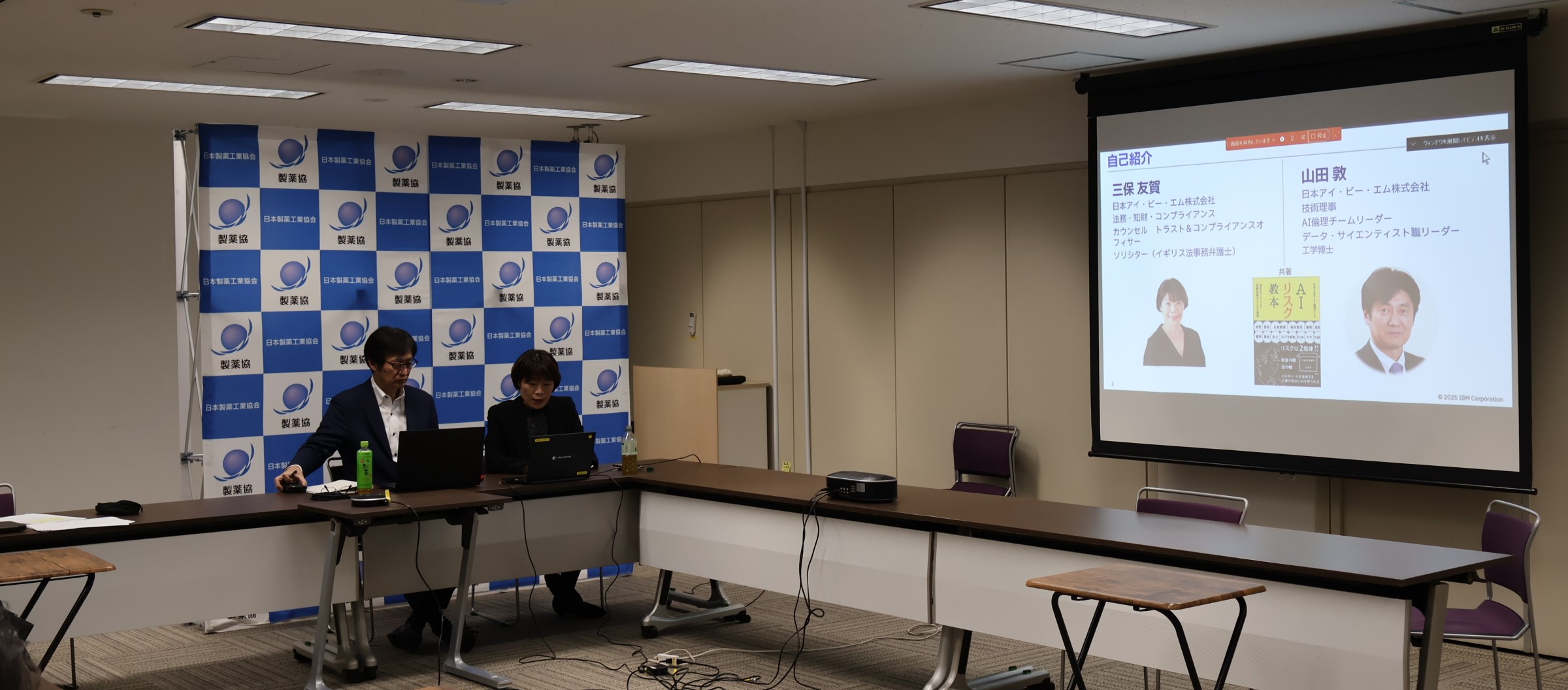 会議の様子
会議の様子
表1.「2024年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」プログラム
| 司会: | 製薬協コード・コンプライアンス推進委員会 玉田 隆司 実務委員 |
|---|---|
| (1)開会挨拶 | 同 平田 千佳 委員長 |
| (2)世界の製薬業界におけるBusiness Ethicsの取り組みと
製薬協コード・コンプライアンス推進委員会の貢献 |
同 松村 豪 実務委員長 |
| (3)グローバル化とコンプライアンス | 武田薬品工業株式会社
ジャパンファーマビジネスユニット エシックス&コンプライアンス アソシエートディレクター 谷口 香織 氏 |
| (4)特別講演
「AIガバナンス -信頼できるAIの活用に向けて-」 |
日本アイ・ビー・エム株式会社
コンサルティング事業本部 技術理事 山田 敦 氏 法務・知財・コンプライアンス カウンセル、トラスト&コンプライアンスオフィサー 三保 友賀 氏 |
| (5)閉会挨拶 | 製薬協 石田 佳之 常務理事 |
開会挨拶
製薬協コード・コンプライアンス推進委員会 平田 千佳 委員長
本会を開催するにあたり、製薬協コード・コンプライアンス推進委員会の平田千佳委員長は、グローバル展開の際の悩みである「グローバルスタンダードとは何か?」や「どこから手を付けるべきか?」について、松村豪実務委員長によるグローバルに展開する企業の企業倫理を巡る議論の紹介や、武田薬品の谷口香織氏によるグローバル化とコンプライアンスへの取り組みに関する紹介を会員会社のみなさんの参考にしていただきたいと述べました。
また、製薬業界はグローバルで見ても、AIのベネフィットを大きく受けている業界の1つであり、一方で患者さんの個人情報など非常に機微性の高いデータを扱っており、国内製薬企業は、グローバルの製薬企業が先に進めているAI技術の利用にさまざまな面で追いついていないのではないかとの見解を示しました。グローバルに展開するAIとデータの利用の実態とのギャップを埋めるために、どこに機会を求め、同時にリスク面をどう担保するか、日本アイ・ビー・エムの山田敦氏および三保友賀氏によるAIガバナンスに関する特別講演からヒントを得ていただくことを期待しました。

世界の製薬業界におけるBusiness Ethicsの取り組みと製薬協コード・コンプライアンス推進委員会の貢献
製薬協コード・コンプライアンス推進委員会 松村 豪 実務委員長
はじめに、国際製薬団体連合会(IFPMA)について紹介があり、全世界で53の製薬団体および38の製薬企業がIFPMAに加盟しており、製薬協、欧州製薬団体連合会(EFPIA)、および米国研究製薬工業協会(PhRMA)がIFPMA加盟の主要3団体と呼ばれている旨を説明しました。
続いて、製薬協のIFPMAへの関わりについて、次のように紹介しました。
- IFPMAにはエシックスおよびビジネスインテグリティに関する会議体として、Chief Ethics & Compliance Officer Round Table(CECORT)とEthics & Business Integrity Committee(eBIC)の2つが存在している。
- CECORTには、各会員団体・企業の倫理・コンプライアンスの最高責任者が参加し、エシックスおよびビジネスインテグリティの優先事項や戦略について議論している。一方のeBICは、CECORTの決定事項を実行に移す役割を果たしている。製薬協コード・コンプライアンス推進委員会はeBICに参加し、活動を行っている。

さらに、製薬協のアジア太平洋経済協力(APEC)への関わりとして、IFPMAとAPECは、世界の医薬品、医療機器市場のビジネス倫理の基礎を築くために強力なタッグを組んでいること、APECが注力しているメキシコシティー原則の浸透およびコンセンサスフレームワークの設立と運用促進への製薬協の取り組みについて紹介しました。
最後にその他の活動として、2024年11月に開催された「Ethics & Business Integrity Day in South Africa」において、松村実務委員長がトレーナーの一員として、南アフリカのヘルスケア関係者に対しIFPMAコードに関するワークショップを実施したこと、また、石田佳之常務理事、平田委員長をはじめとする製薬協のAPEC参加者が、2023年および2024年に各APEC開催国の日本大使館を訪問し、製薬協のAPECに対する貢献を共有したこと、さらに、2023年にはPhRMAを訪問し、ビジネスエシックス分野の相互協力について議論したことを紹介しました。
グローバル化とコンプライアンス
武田薬品工業株式会社
ジャパンファーマビジネスユニット エシックス&コンプライアンス
アソシエートディレクター 谷口 香織 氏
はじめに、武田薬品のグローバル展開は、1951年の北中米、アジアを皮切りとした海外市場への本格参入から始まり、2019年のシャイアー社買収が大きな転機となったことが紹介されました。
次に、グローバル化を進めるうえでのコンプライアンス強化の取り組みについて、以下のように紹介しました。
タケダの従業員は、タケダイズムという共通の価値観を道しるべとしながら、「P-T-R-B」(Patient-Trust-Reputation-Business)を日々の行動指針としています。

- 第一に、患者さんにとって正しいことか?
- 第二に、人々との信頼関係の構築につながるか?
- 第三に、タケダの社会的評価を高めることができるか?
- 最後に、持続可能な事業の発展の役に立つか?
上記の4つの質問を、自らに順番に問いかけ、すべてについて「Yes」となったら実施するという決定をしています。毎年、創業記念日である6月12日前後には、「Values day」と題した、タケダの企業理念を振り返り、言語化するイベントを開催しており、Values dayは、企業理念をさまざまな国の従業員と同じ認識を持つこと、および日本タケダにとっては過去の過ちを忘れないことを目的としています。
さらに、「タケダ・コンプライアンスプログラム」について、以下のように紹介しました。
タケダは、Culture & Values等の8つの項目を順番にサイクルとして回すことで、継続的な改善を促しています。このサイクルを回すうえで重要となるのが、グローバルポリシー等の社内規定です。最高位のポリシーであるコード・オブ・コンダクトを土台として、医療関係者や患者さんとの交流に関するグローバルポリシー、利益相反ポリシー、贈収賄腐敗行為禁止ポリシー等の個別のポリシーがあります。特に、贈収賄腐敗行為禁止ポリシーは、グローバルで事業を行うにあたっては、最も重要なポリシーに位置付けられています。
最後に、日々進化するテクノロジーへの対応について、以下のように紹介しました。
先般、テクノロジーは驚くべき速度で進化し、AIは各社の業務に欠かせないものとなっています。この数年で生成AIが登場し、各分野での利用が始まり、生産性の向上、コスト削減やクリエイティブ作業のサポート等で多くの価値を享受している反面、新たなリスクも生み出しています。リスクの多様化、複雑化が進み、AIガバナンスの構築を検討している企業も多いと思われますが、タケダにおいても、AIの利活用を推進するとともに、ガバナンス構築にも取り組んでいます。また、タケダの存在意義や価値観を創造するうえで、AIの活用やヘルスデータの活用により生じる重要課題に対する見解を述べるポジションペーパーをウェブサイトに公表しています。タケダは、テクノロジーの利活用の推進やガバナンスの構築を、グローバルチームと日本チームとの連携で進めています。グローバルチームは、全世界に共通するハイレベルな社内ルールの作成・発出を行い、日本チームは、日本の法規制に関する補足情報を追加し、翻訳した上で、日本国内の従業員に発信し、トレーニングを行っています。
特別講演 「AIガバナンス -信頼できるAIの活用に向けて-」
日本アイ・ビー・エム株式会社
コンサルティング事業本部 技術理事 山田 敦 氏
法務・知財・コンプライアンス カウンセル、 トラスト&コンプライアンスオフィサー 三保 友賀 氏
AIガバナンスについて、お二人の掛け合いによりわかりやすい解説がありました。以下に要点をまとめます。
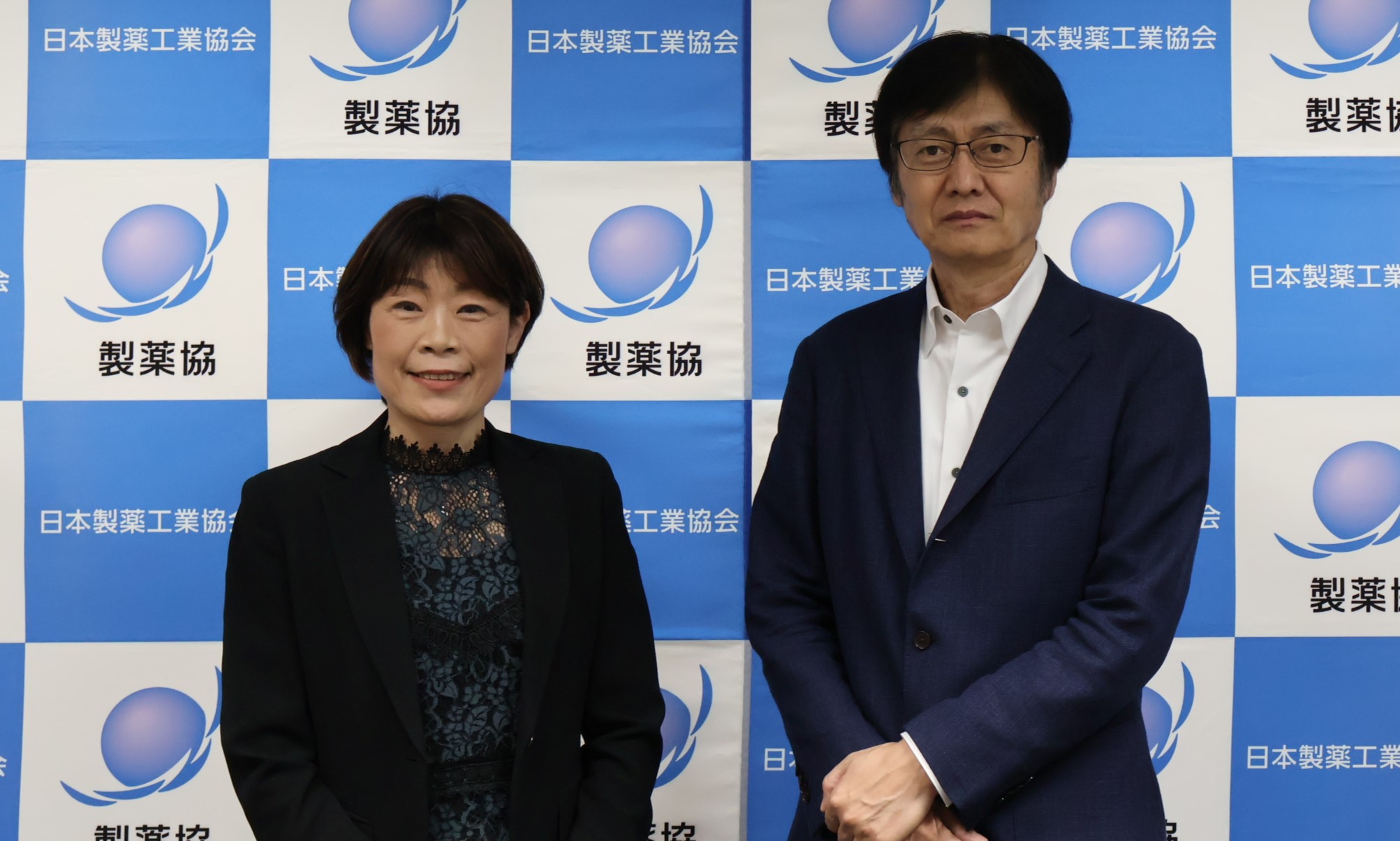
- これまでのAIは、用途毎に時間を掛けて膨大なデータを準備する必要がありましたが、近年のAIは基礎的な知識をすでに学んでおり、その上に特有の知識を教えると、用途毎のAIとしてすぐに使えるようになります。最近のAIの進化の背景には、計算能力の向上、ビッグデータの蓄積、新しいニューラルネットワーク構造の3つの要素があります。
- 2024年の春に公表された医療業界における生成AIの活用実態調査や全業界における米国と日本との比較調査が紹介されました。
- AIガバナンスの定義は一つではありませんが、AIの活用を進めるために組織が持つべき仕組み(人、技術、プロセス)です。それらはAI活用を制御するブレーキではなく、前進させるためのガードレールの役割になります。モノづくりの手法に従い、構想、要件定義、設計・実装、テストを繰り返して構築します。もちろん既存のリスク管理フレームワークに組み込むこともできます。
- IBMでは、AIに関する原則とそれを支える基本特性を制定して社内外に公表しています。それが社員の共通言語となり、何をすべきか何をしてはいけないか、つまり取れるリスクと避けるべきリスクが明確になります。
- また、そうした原則を実践につなげているのがAI倫理委員会という組織で、技術と法律のツートップがリードしています。AIガバナンスに携わる組織は、多様性のある組織横断的な人から構成されることが重要です。異なる専門性、経験、知見または倫理観で建設的な議論ができる場であることが必要であるからです。
- 個々のAIプロジェクトについては、AI倫理委員会のリスク審査を受けるプロセスがあり、日本のプロジェクトの1次評価を日本のAI倫理部門担当者が担当します。リスクの高いプロジェクトについては、最終判断をグローバルのAI倫理委員会(またはそのPMO)が担っています。
- AIを含む技術の進化のスピードは指数関数的です。今のうちに正しい知識を身に着けておくことで劇的な変化の波をチャンスに変えることができます。我々一人ひとりがリテラシーを向上させることは必須となり、また、社員の教育に力を注ぐべきです。
- 社員研修で活用してほしいのが、デザイン思考ワークショップの手法です。仮想事例を使い、関係者を整理、不利益を感じる人の目線でリスクを洗い出し、対策を考えるプロセスを通して、専門家でなくてもリスクを洗い出すことができ、自分事として腹落ちさせることができます。
日本アイ・ビー・エム株式会社 三保 友賀
メールアドレス:tomoka.miho@ibm.com
閉会挨拶
製薬協 石田 佳之 常務理事
石田常務理事は挨拶の冒頭で、コンプライアンス管理責任者、コンプライアンス実務担当者の本会への参加に対して謝意を表すとともに、松村実務委員長、谷口氏、山田氏、三保氏に謝辞を述べました。
次に、特別講演について、「AIは非生物のエージェント(行為主体)であると脅威を感じる人がいる一方で、若いビジネスマンがChatGPTやCopilotを使って業務効率を上げている状況もある。本日は、AIを活用して新しいアイディアを実行するうえでのガバナンスや倫理的なチェックの方法をご紹介いただいた。最近は、先に進んでいるテクノロジーをどう倫理でブレーキを掛けるかというこれまでの価値観が崩れ始めている。AIをコントロールする倫理観は変わりうるが、それをコンプライアンス担当者や管理部門がどう捉えるかが今後の宿題となっている。」と述べました。
最後に、「本日ご講演いただいたAIガバナンスの実務的な話を踏まえて、会員会社のみなさんはAIをどんどん社業に活用したり、上手にコントロールしたりすることに精進していただきたい。」と締めくくり、本会は終了しました。
https://cms.jpma.mlce.cloud/WebRelease2/img.-.ja_1730856824@@@k-hozon.gif
(コード・コンプライアンス推進委員会 実務委員 増田 直幸)


