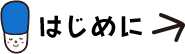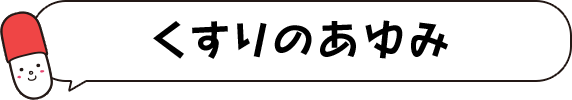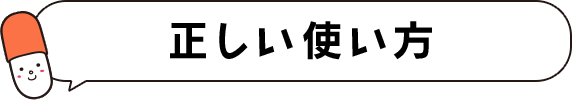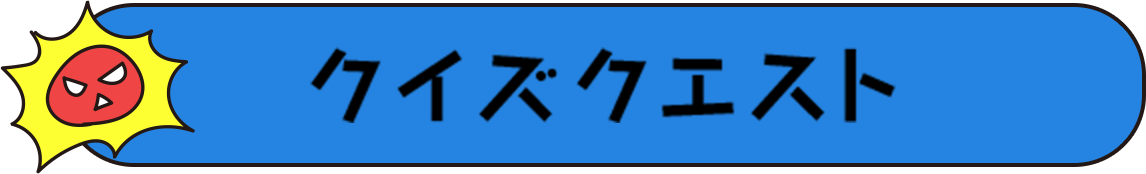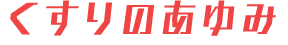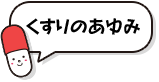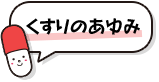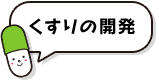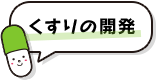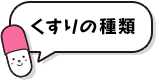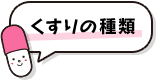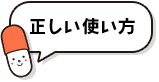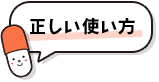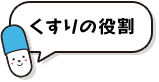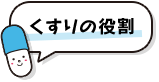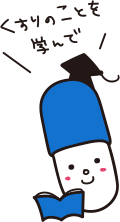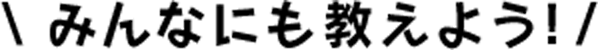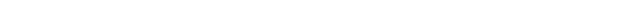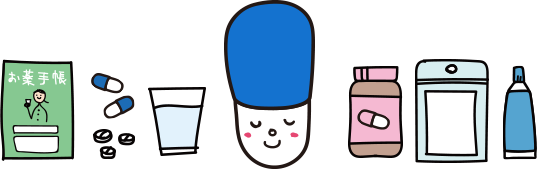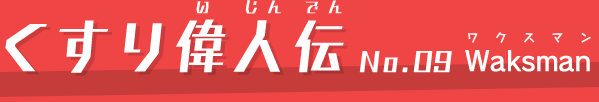
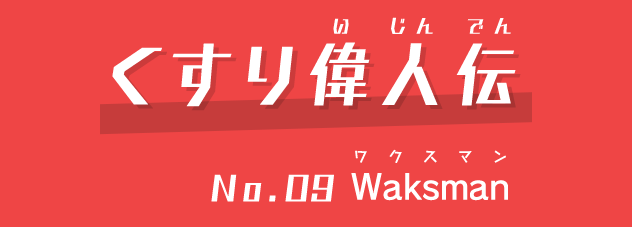
結核(けっかく)をたおす力を持つ微生物(びせいぶつ)を土の中から発見したアメリカの微生物学者。

放線菌という微生物(びせいぶつ)から結核(けっかく)を治すくすりを発見
1943年、ワクスマンは結核(けっかく)を治すくすり「ストレプトマイシン」の発見に成功しました。ストレプトマイシンは、放線菌というカビに似た微生物(びせいぶつ) からつくられます。
当時、結核(けっかく)のくすりとして「ペニシリン」がすでに開発されていましたが、ワクスマンはもっと強力な効(き)き目を持つくすりの研究に取り組んでいたのです。
長年の研究のすえに発見されたストレプトマイシンは、ひじょうに強い効(き)き目がありました。その力で世界中の多くの結核患者(けっかくかんじゃ)は救われたのです。


アブラハム・
ワクスマン
(Selman Abrahambr
Waksman)
1888~1973
アメリカ、微生物学者
(びせいぶつがくしゃ)
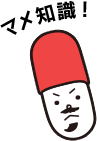

ワクスマンが発見したストレプトマイシンも、放線菌によってつくられた抗生物質(こうせいぶっしつ)の1つです。放線菌は、実は「抗生物質(こうせいぶっしつ)」の宝箱(たからばこ)で、今では抗生物質(こうせいぶっしつ)の7~8割(わり)が放線菌からつくられています。

放線菌とは、主に土の中に住んでいる 微生物(びせいぶつ)のことです。
ワクスマンは、学生のときレポートを書くために、大学の農場で、いろいろな深さの土を集めて細菌(さいきん)やカビを調べていました。すると土の中に細菌(さいきん)
でもカビでもない微生物 (びせいぶつ)がいることに気づいたのです。それが放線菌でした。
放線菌がいる土では、他の細菌(さいきん)の数は減ります。このことから、放線菌には他の細菌(さいきん)などをたおす力があると考えたワクスマンは、放線菌を研究し、結核(けっかく)に効く抗生物質(こうせいぶっしつ)・ストレプトマイシンを発見しました。
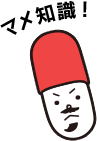

そのあと、ワクスマンはストレプトマイシンの開発などによって得たお金で、ワクスマン微生物学(びせいぶつがく)研究所をつくりました。そして、1つでも多くの病気をなくすため、研究者を育てることに力を注ぎました。

ワクスマンが微生物(びせいぶつ)の研究をしていたころ、第二次世界大戦が始まろうとしていました。
戦争が始まれば、多くの兵士がいろいろな感染症(かんせんしょう)にかかり命を落としてしまいます。きっと、感染症
(かんせんしょう)
に良く効(き)くくすりが必要になると考えたワクスマンは、ペニシリンよりも強力な物質を見つけだそうと、熱心に微生物(びせいぶつ)の研究をしていたそうです。
そうして結核(けっかく)に効果のある抗生物質(こうせいぶっしつ)・ストレプトマイシンを発見したワクスマンは、その功績が認(みと)められて、1952年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
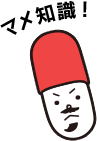

ペニシリンは、パンなどに生えるアオカビという身近なものからつくられています。そこでワクスマンは、「まだ他にも発見されていない物質が身近なところにあるはずだ」と考え、土の中の微生物(びせいぶつ)の研究を始めました。