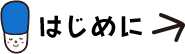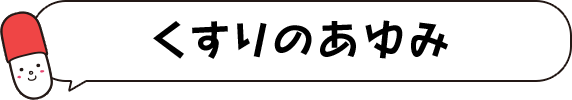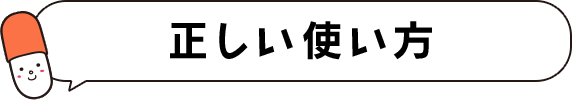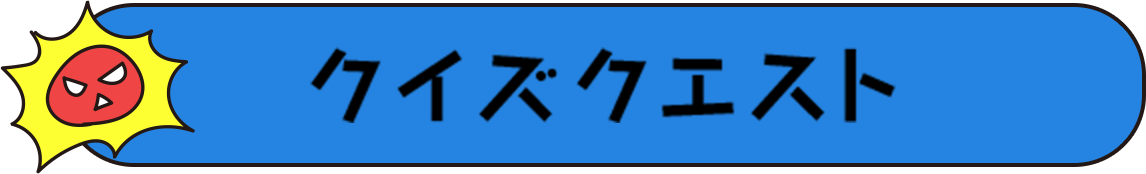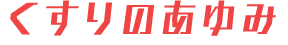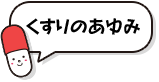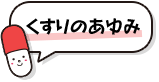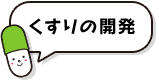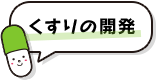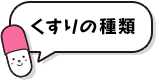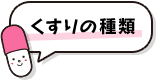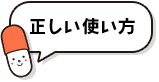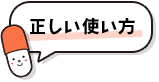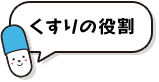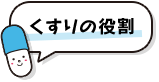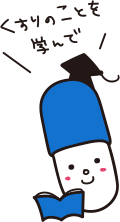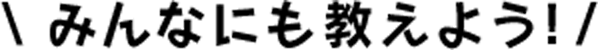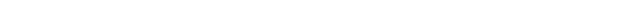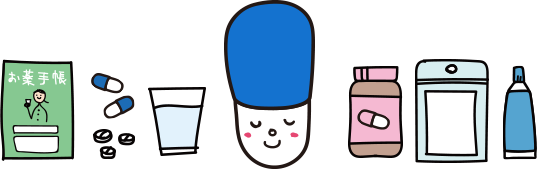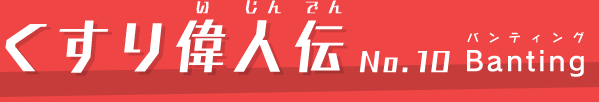

世界中の糖尿病患者(とうにょうびょうかんじゃ)を救った「インスリン」を発見したカナダの医学者。

糖尿病(とうにょうびょう)と深い関わりのある「インスリン」を発見
糖尿病(とうにょうびょう)は血液中の糖(とう)(血糖値(けっとうち))が増えてしまう病気で、昔は絶対に治すことのできない病気とされていました。
バンティングは、糖尿病(とうにょうびょう)は体内でつくられるはずの物質が不足していることが原因であると考えました。そして熱心に研究を続け、糖尿病 (とうにょうびょう)の原因と、治療(ちりょう)に効(き)く物質「インスリン」を見つけだすことに成功したのです。
バンティングの発見のおかげで、何百万人もの糖尿病患者(とうにょうびょうかんじゃ)が命を救われました。


グラント・
バンティング
(Frederick Grant Banting)
1891~1941、カナダ
生理学者・医学者
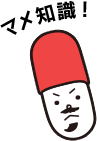

血糖値(けっとうち)を下げる物質としてインスリンが発見されたことは、当時の医学で最大の進歩のひとつとされ、1、2年のうちに大量生産されるようになりました。
そして、インスリンの研究開発では5人もの研究者がその功績(こうせき)を認(みと)められ、ノーベル賞を受賞しています。

大学で助手をしていたバンティングは、ある日、授業の準備のために調べ物をしていました。そのとき、雑誌(ざっし)にのっている研究資料が目にとまったのです。
そこには、「すい臓(ぞう)の管がつまると消化液がでなくなってしまう」と書かれていました。これを読んだバンティングは、消化液のでないすい臓(ぞう)からなら、糖尿病(とうにょうびょう)を治す「未知の物質」を取りだせるかもしれないと思いました。
そしてバンティングは研究と実験をすすめ、すい臓(ぞう)から未知の物質・インスリンを取りだす方法を考えだしたのです。
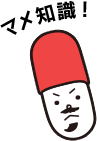

そこでバンティングは、すい臓(ぞう)と十二指腸をつなぐ管をしばり、すい臓(ぞう)から消化液がでないようにしました。このアイデアによって、見事に未知の物質・インスリンが発見されました。

たくさんの糖尿病患者(とうにょうびょうかんじゃ)を救い、ノーベル賞も受賞したバンティング。しかし、インスリンを発見する前のバンティングは、十分な収入(しゅうにゅう)
がなかったので、北極で石油を掘(ほ)る調査隊に医師として同行し、働くことになっていました。
ところが、さまざまな事情により、調査隊へ同行する必要がなくなってしまったのです。そのため、同じ時期にもう1つの道として考えていた大学で研究を選ぶことにしました。
もしもバンティングが調査隊に同行していたら、インスリンの発見はなかったかもしれません。
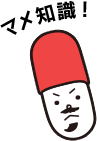

どちらの道を選ぶか迷ったバンティングは、コインを投げて表がでたら「研究」、裏(うら)なら「北極」にいくことにしました。結果は裏(うら)で「北極」。
しかし、北極同行の話がなくなってしまい、バンティングは研究員の道を進むことになりました。