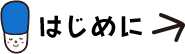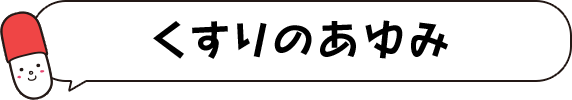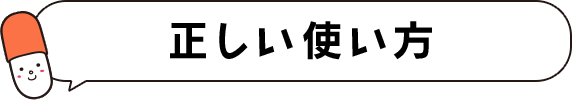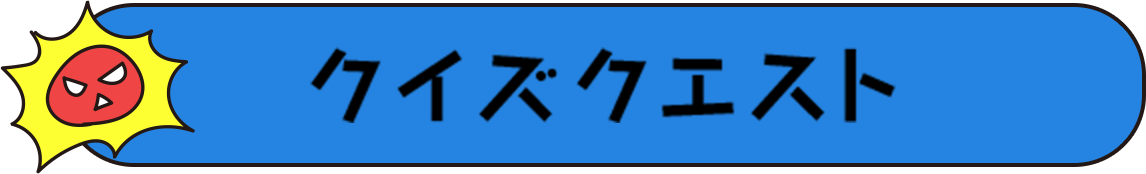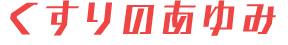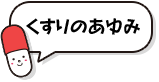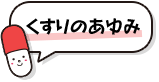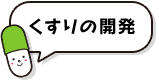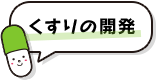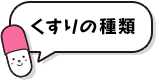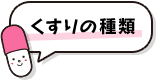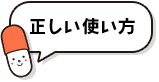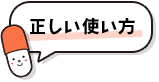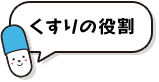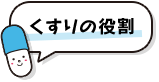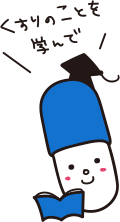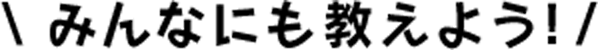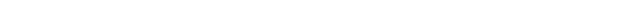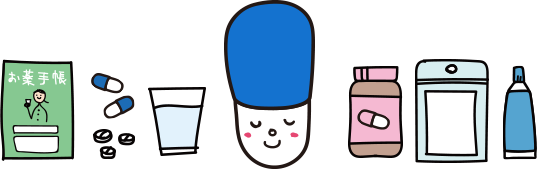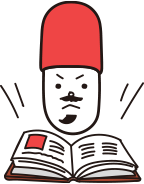


昔の人たちは、木や植物、鉱物など自然の中にあるものから、
くすりをつくり出していたのじゃ。

くすりとは、人の体に用いることで、病気を予防したり、治す手助けをしてくれたりするものです。くすりの歴史はとても古く、人類がたどってきた歴史と重なると言われています。
人類は、動物、植物、鉱物など自然界のあらゆるものから、ケガや病気に効(き)くものを探(さが)しだし、それをくすりとして用いて治療(ちりょう)をおこなってきました。
くすりに関する最も古い記録は、メソポタミア、エジプト、中国にみられ、日本では1万数千年前の縄文人(じょうもんじん)の住居のあとから、くすりに使ったと思われる植物が発見されています。

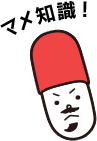

日本では、国(厚生労働大臣や都道府県知事)が品質、有効性、安全性に関する審査(しんさ)をおこない、合格したものだけが販売(はんばい)されています。
厳(きび)しく管理されているからこそ、皆(みな)さんが良いくすりを安心して使うことができるのです。
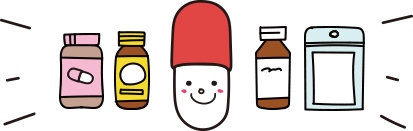

日本のとても古い書物『古事記(こじき)』の中に、くすりにまつわる話が記されています。中でも有名なのは、大国主命(おおくにぬしのみこと)と因幡(いなば) の白ウサギの話です。
ある日、大国主命はサメに皮をはがされて泣いていたウサギと出会い、「真水で体を洗(あら)ってから、蒲(がま) の花粉を体にまぶしなさい」と教えてあげました。するとウサギに毛が生えてきて、もとのすがたにもどることができた、という話です。
話の中にでてくる蒲(がま)の花粉には、血を止めて、痛(いた)みをやわらげる作用があるとされています。


日本に現在のくすりとほぼ同じような本格的なくすりがやってきたのは、6世紀ごろのこと。くすりの材料となる植物が朝鮮半島(ちょうせんはんとう)からとどけられ、聖徳太子(しょうとくたいし)が大事に育てて増やしました。その植物でくすりを製造・調合し、病人や貧しい人に分け与(あた)えていたと言われています。
昔のくすりは、植物を材料としたものが中心でした。例えば、現代でも1月7日に食べる七草がゆがその1つです。七草がゆに入れる春の七草も、昔はかぜや胃のくすりとして利用されていたのです。

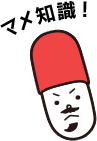

印籠(いんろう)は、もとは印(いん)かんを入れておくものでしたが、江戸時代(えどじだい)のころから携帯(けいたい)しやすいサイズのものがつくられるようになり、くすりを入れて持ち歩くようになったと言われています。