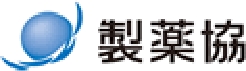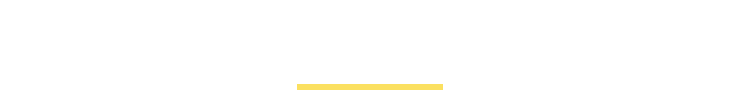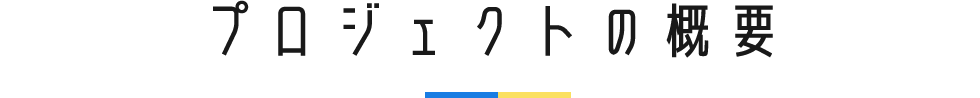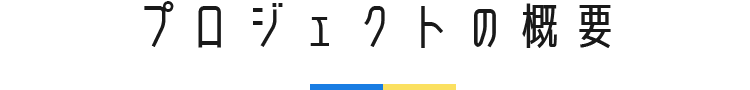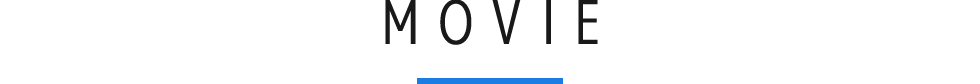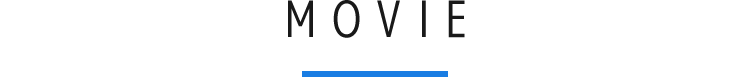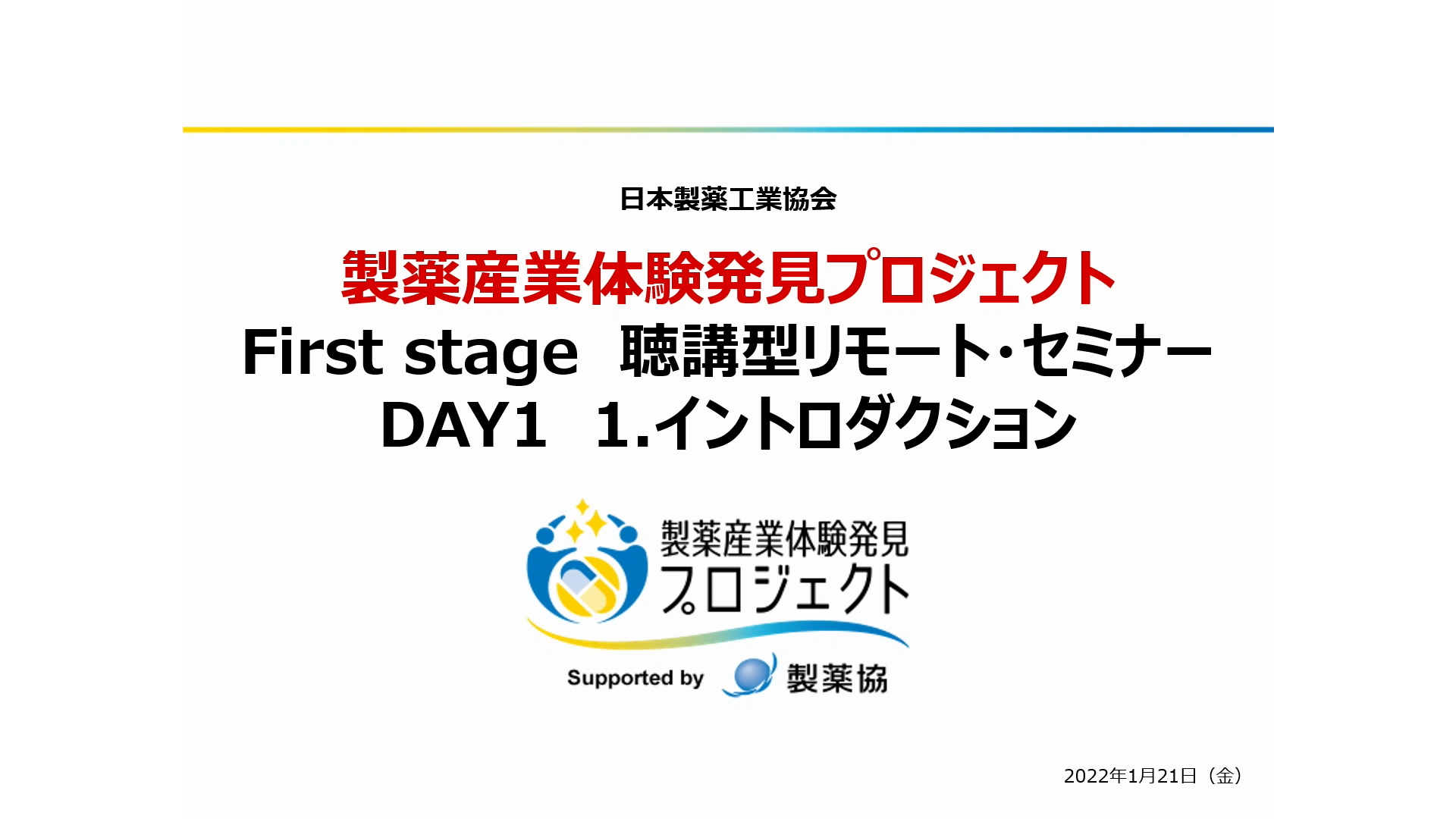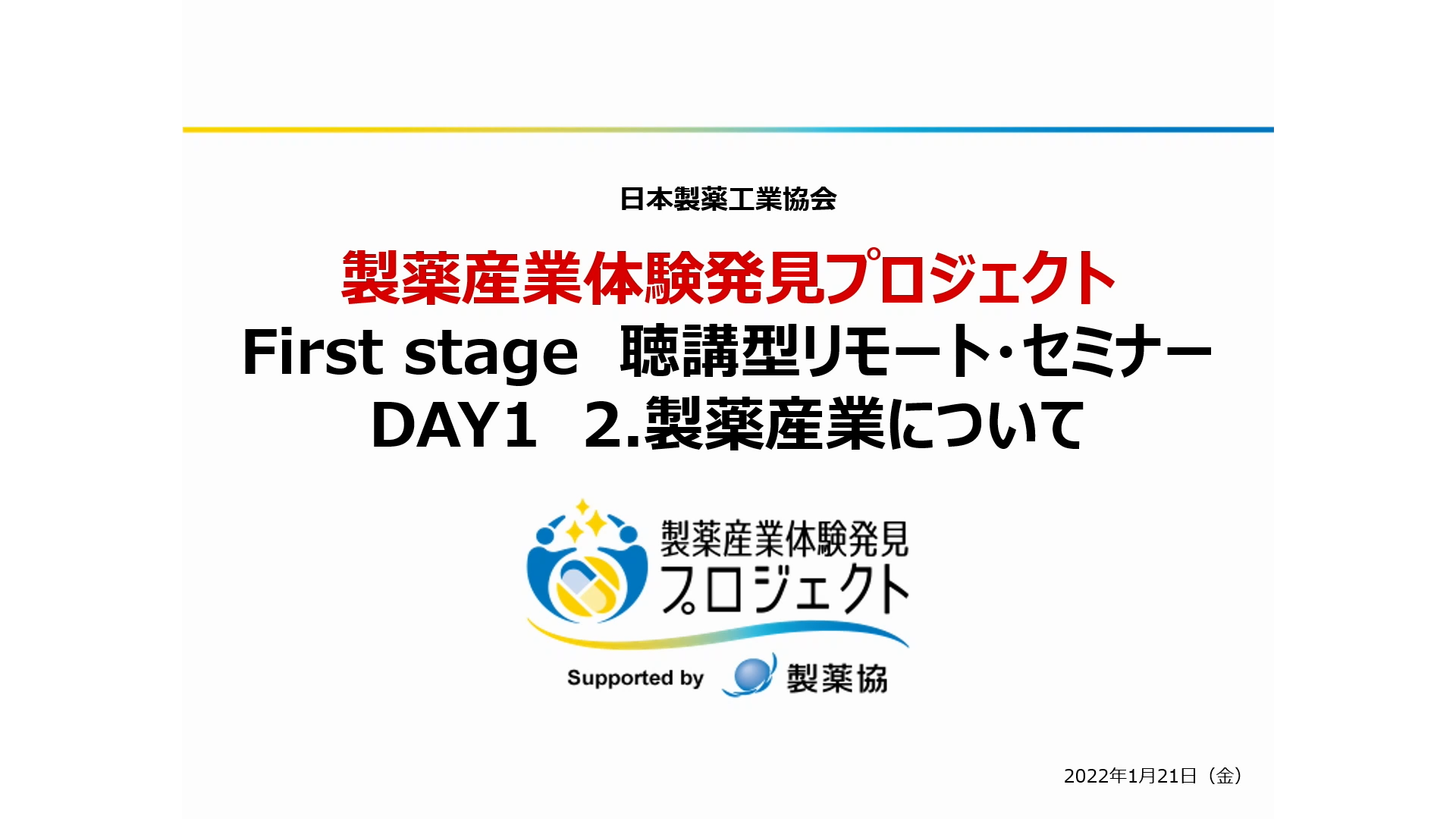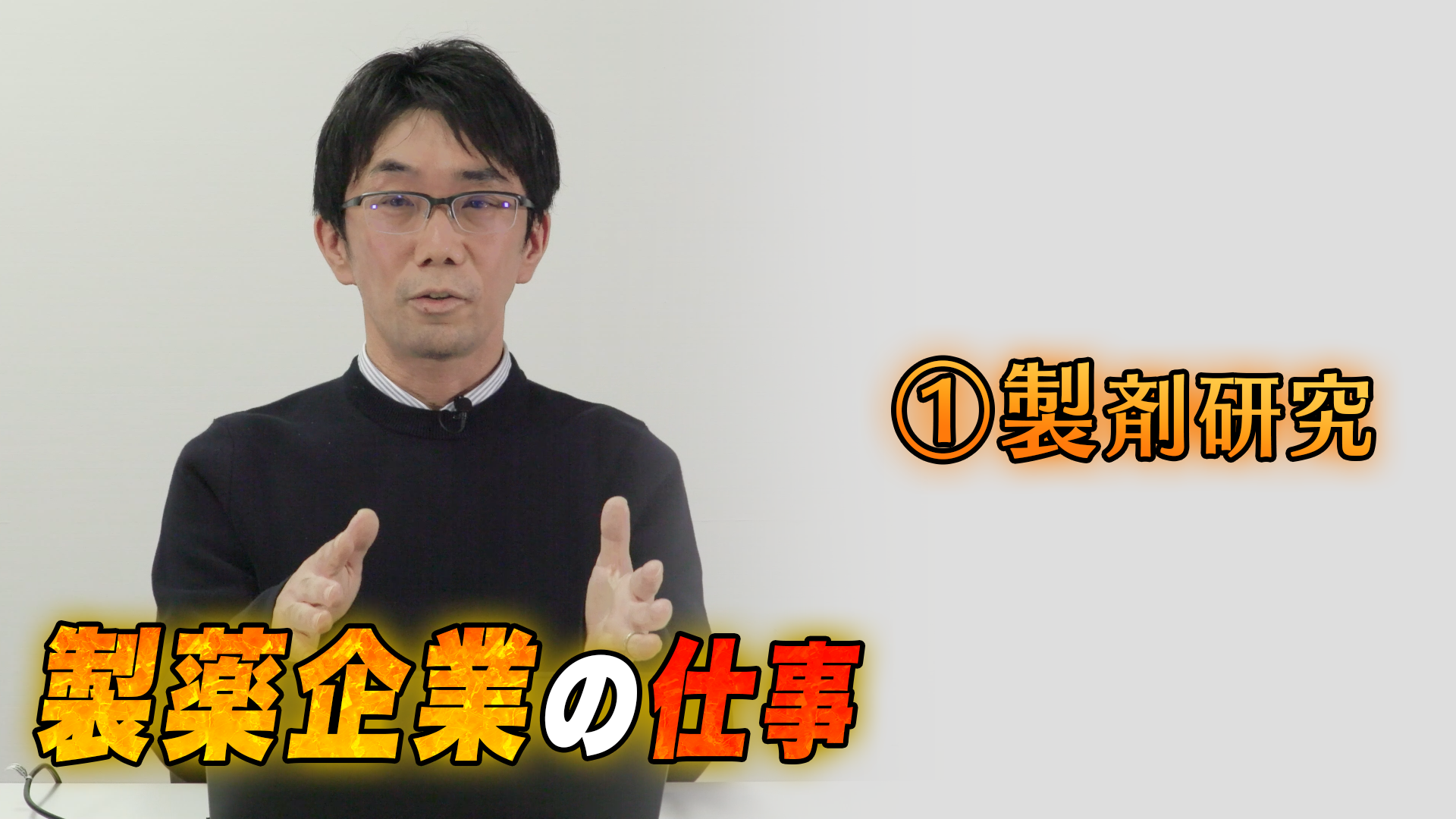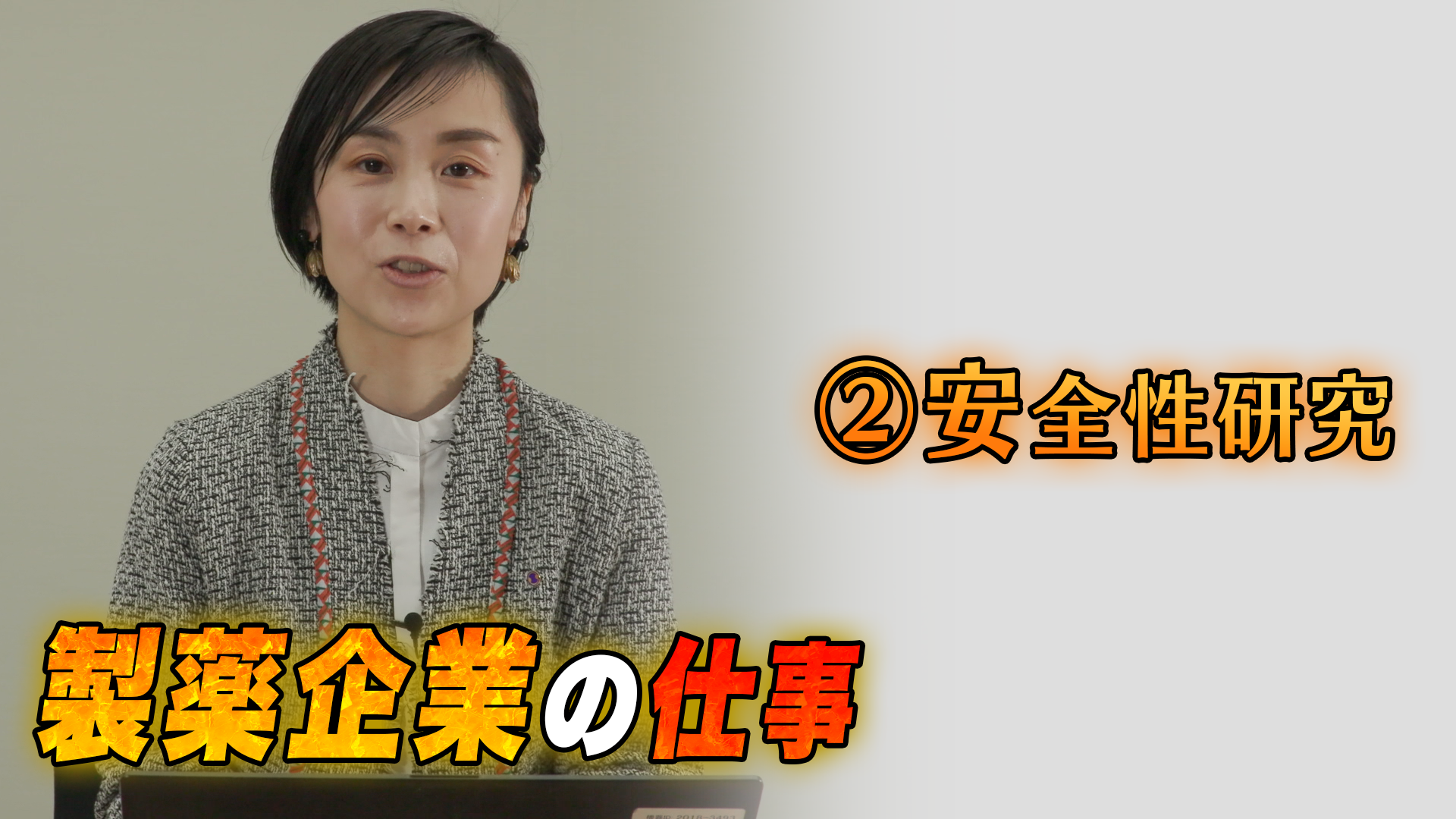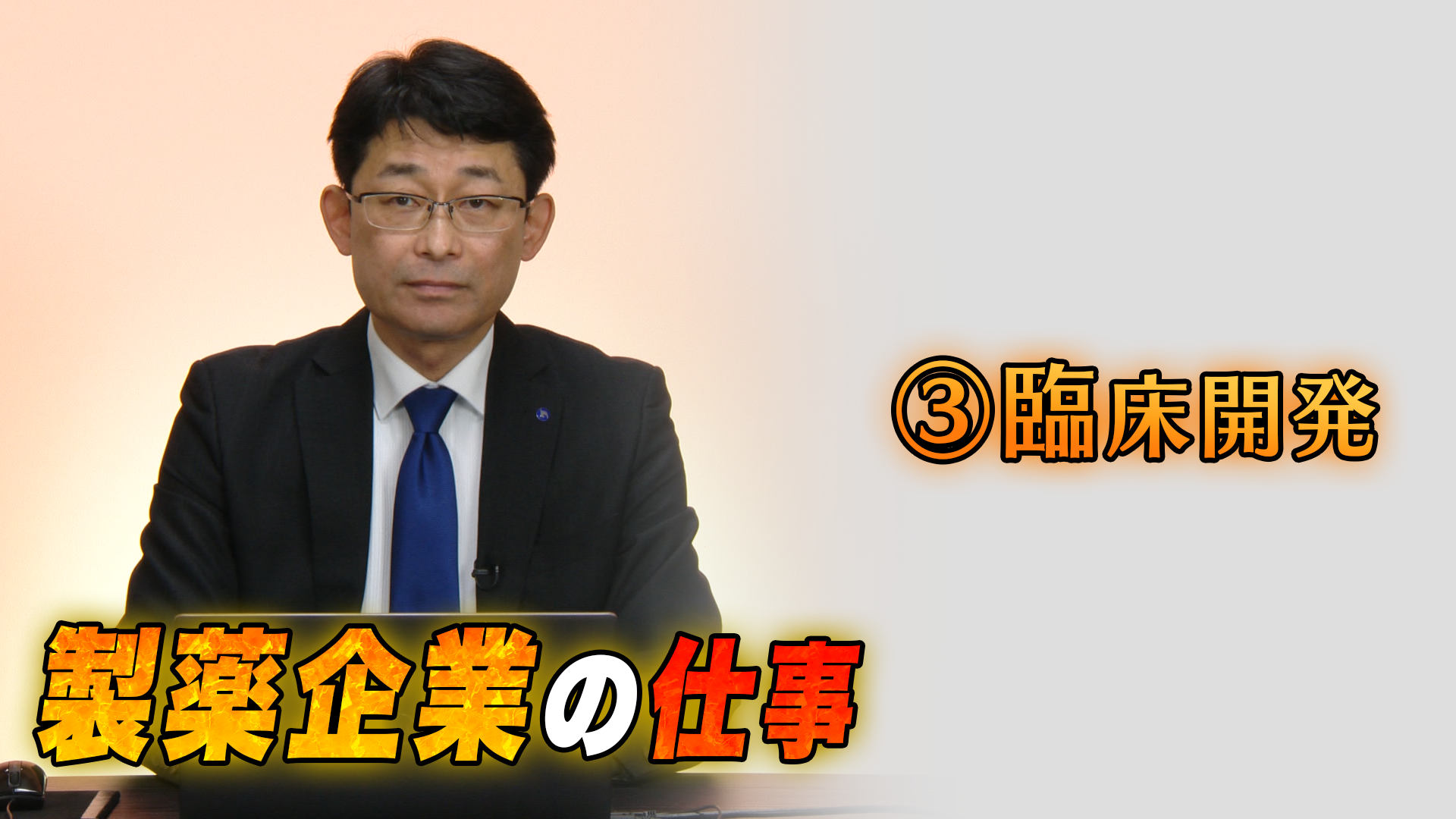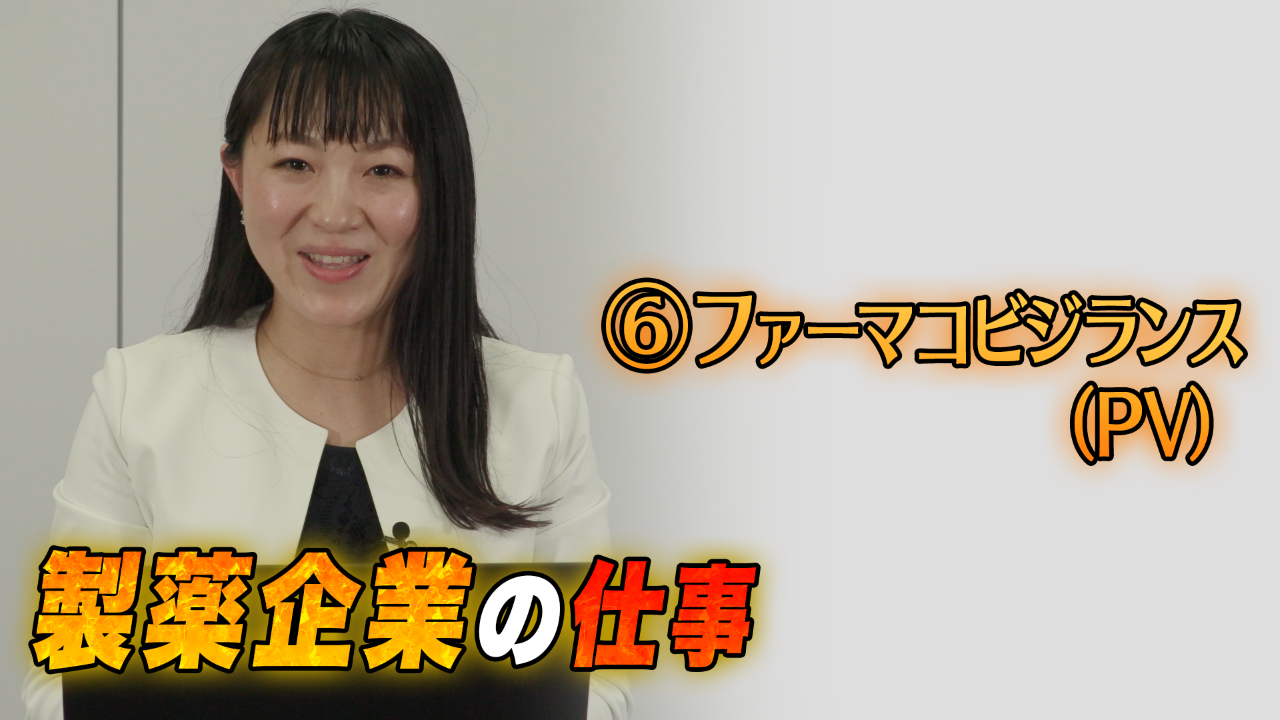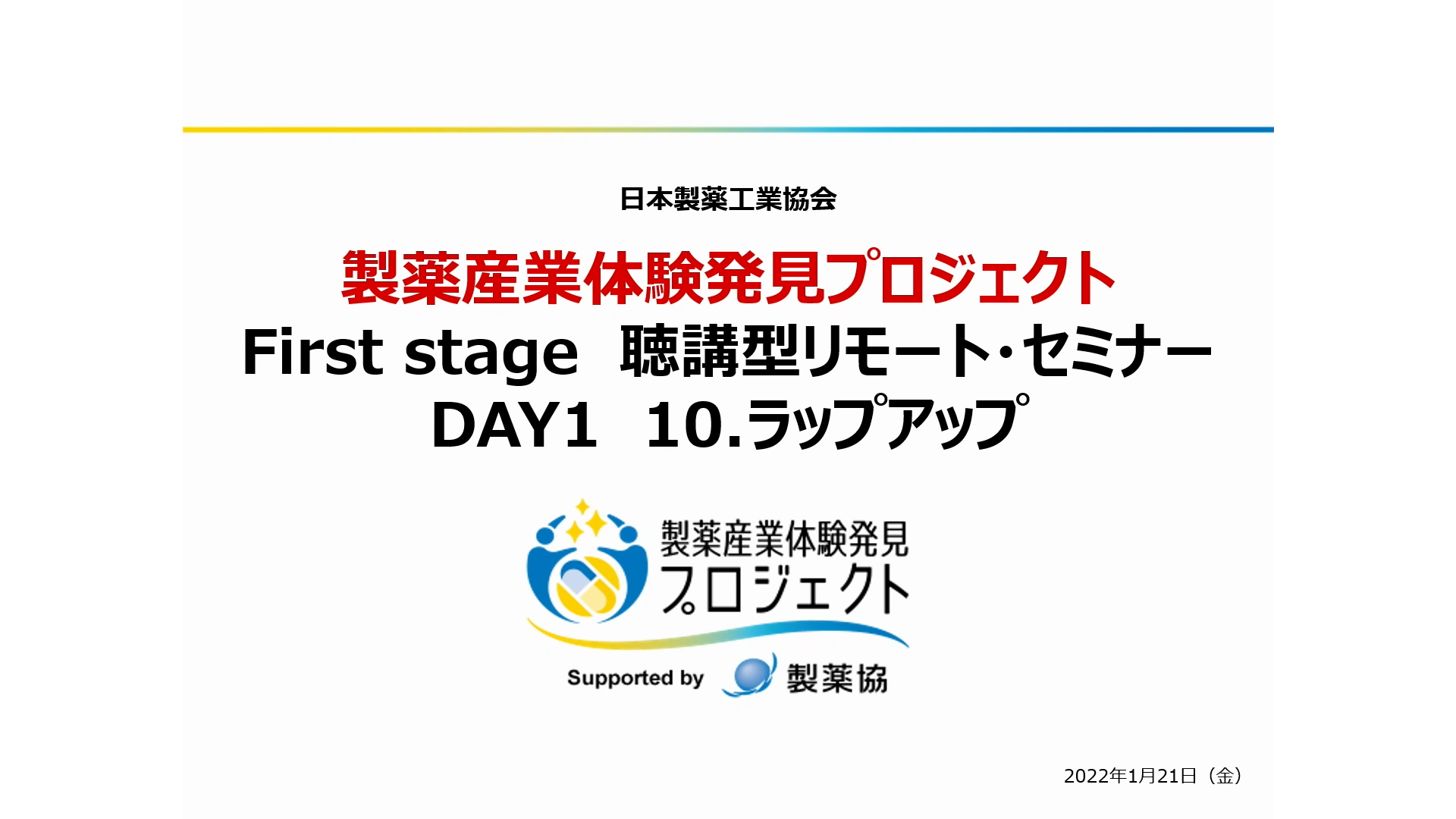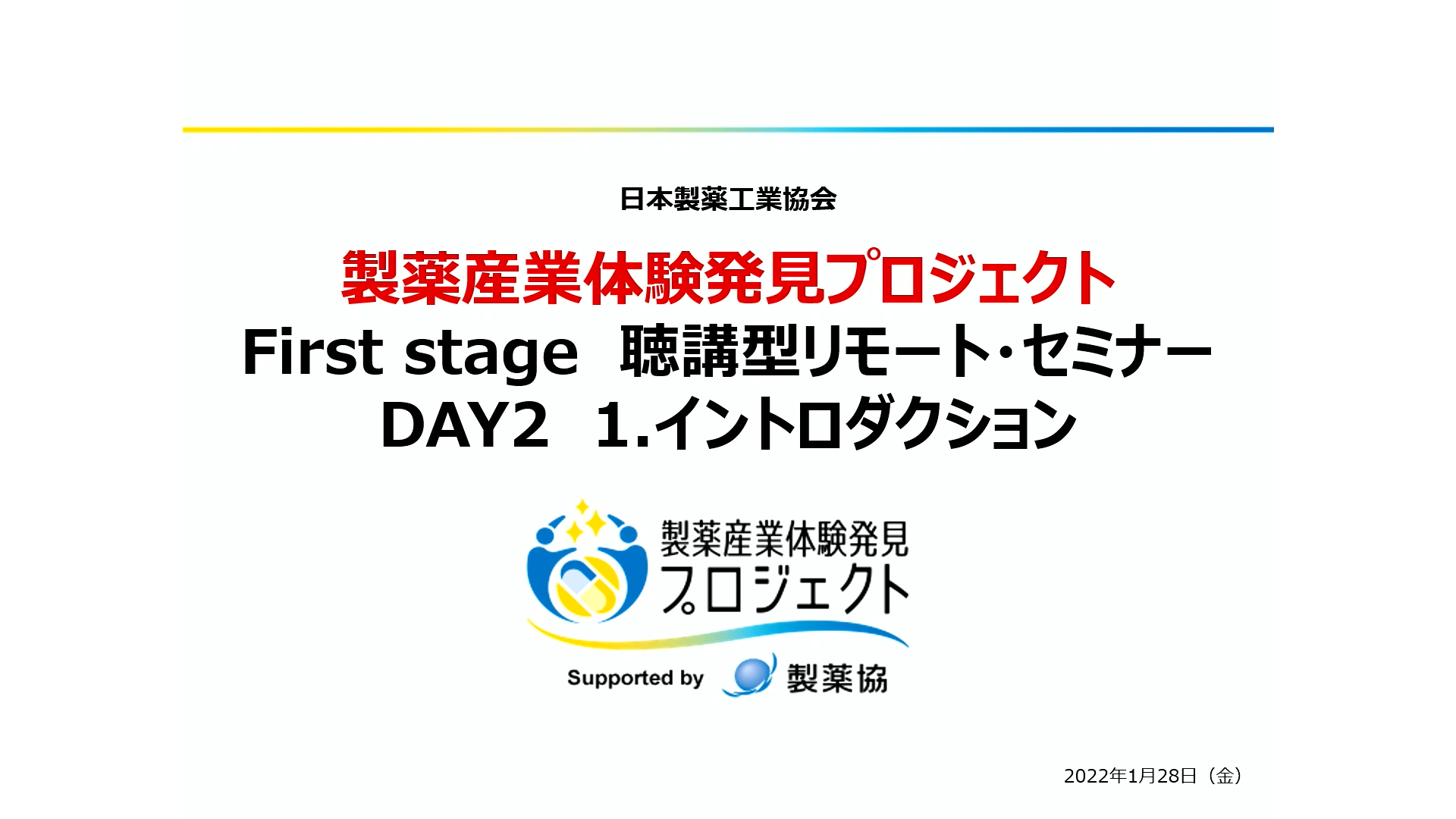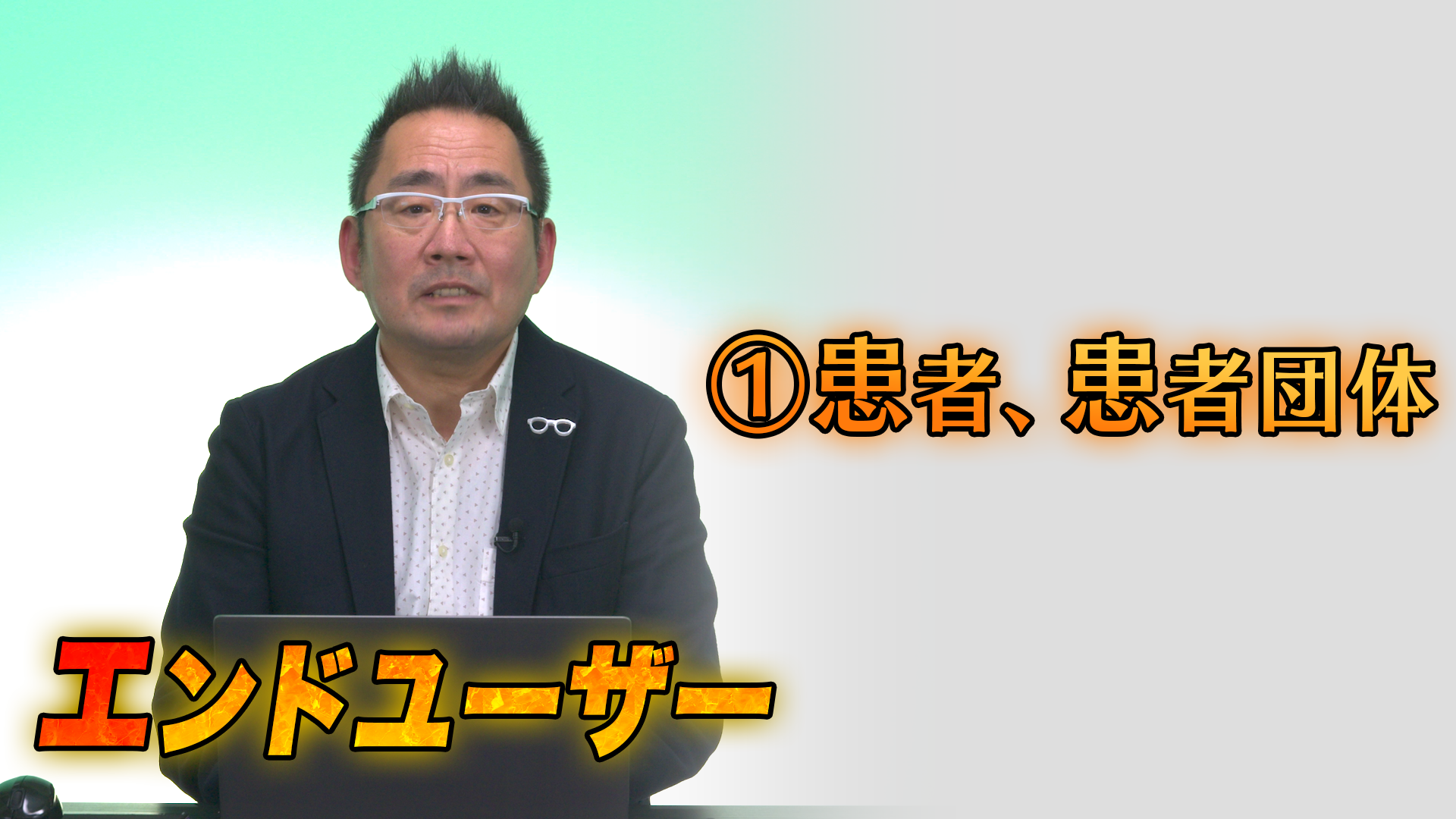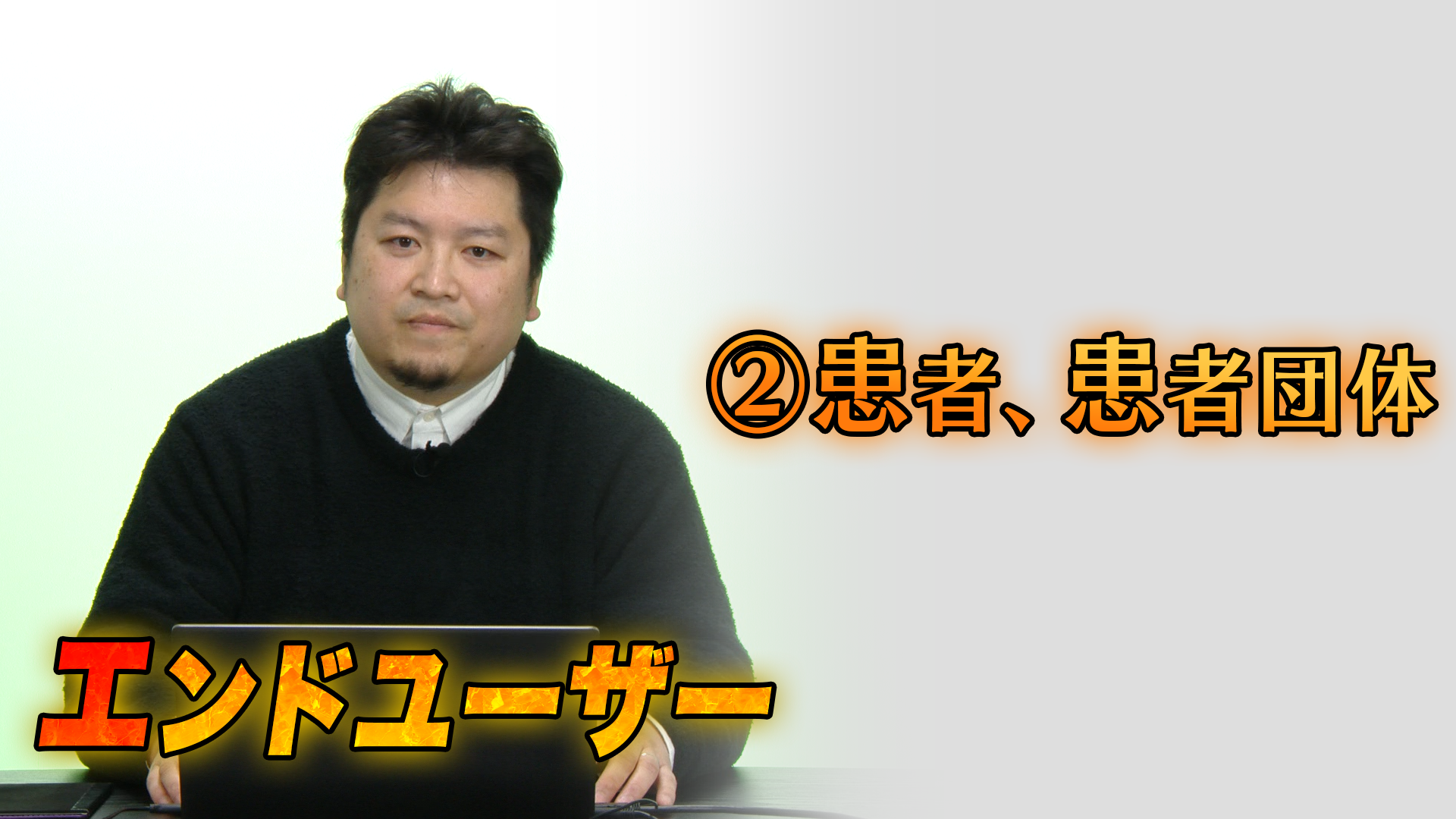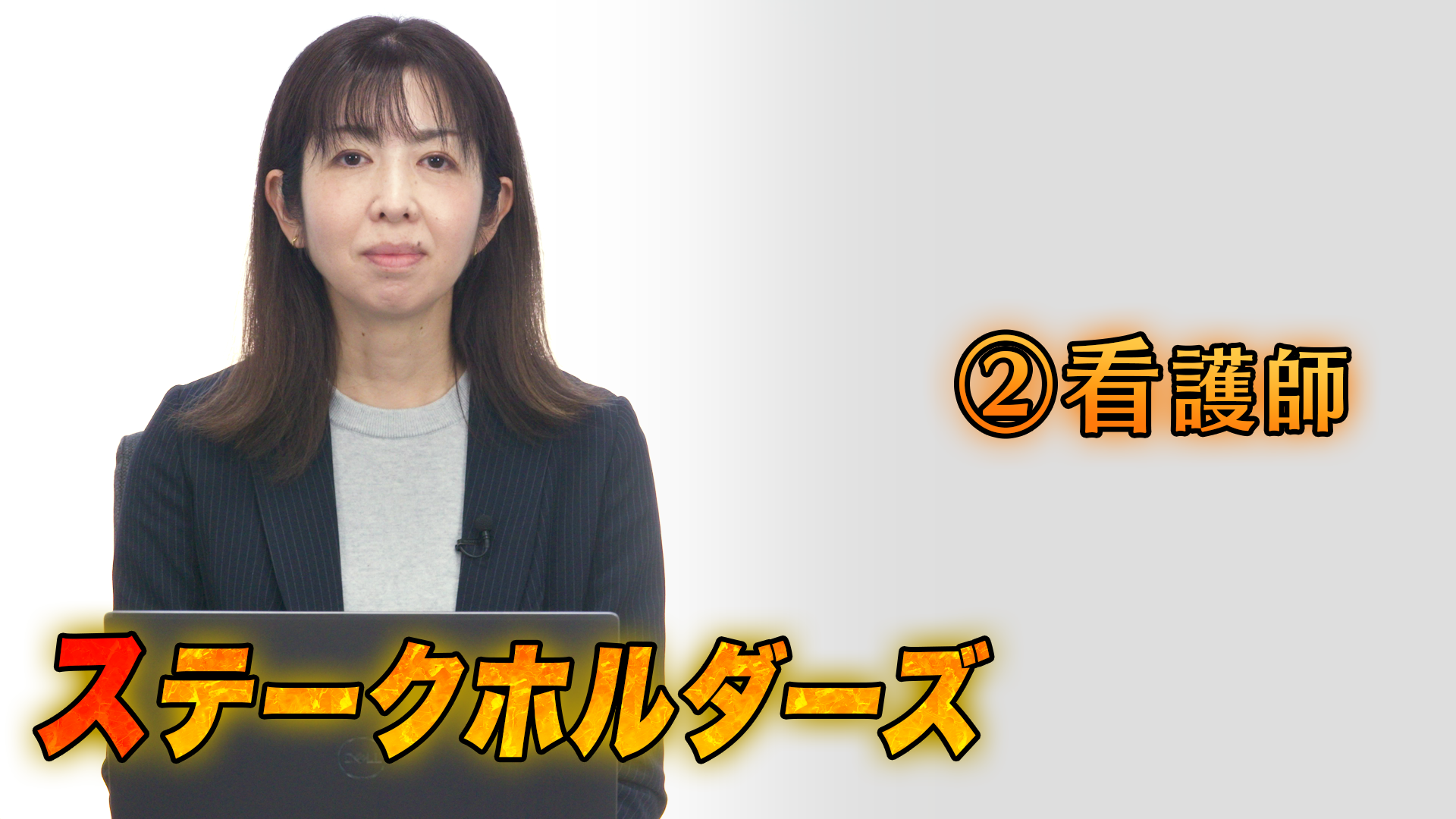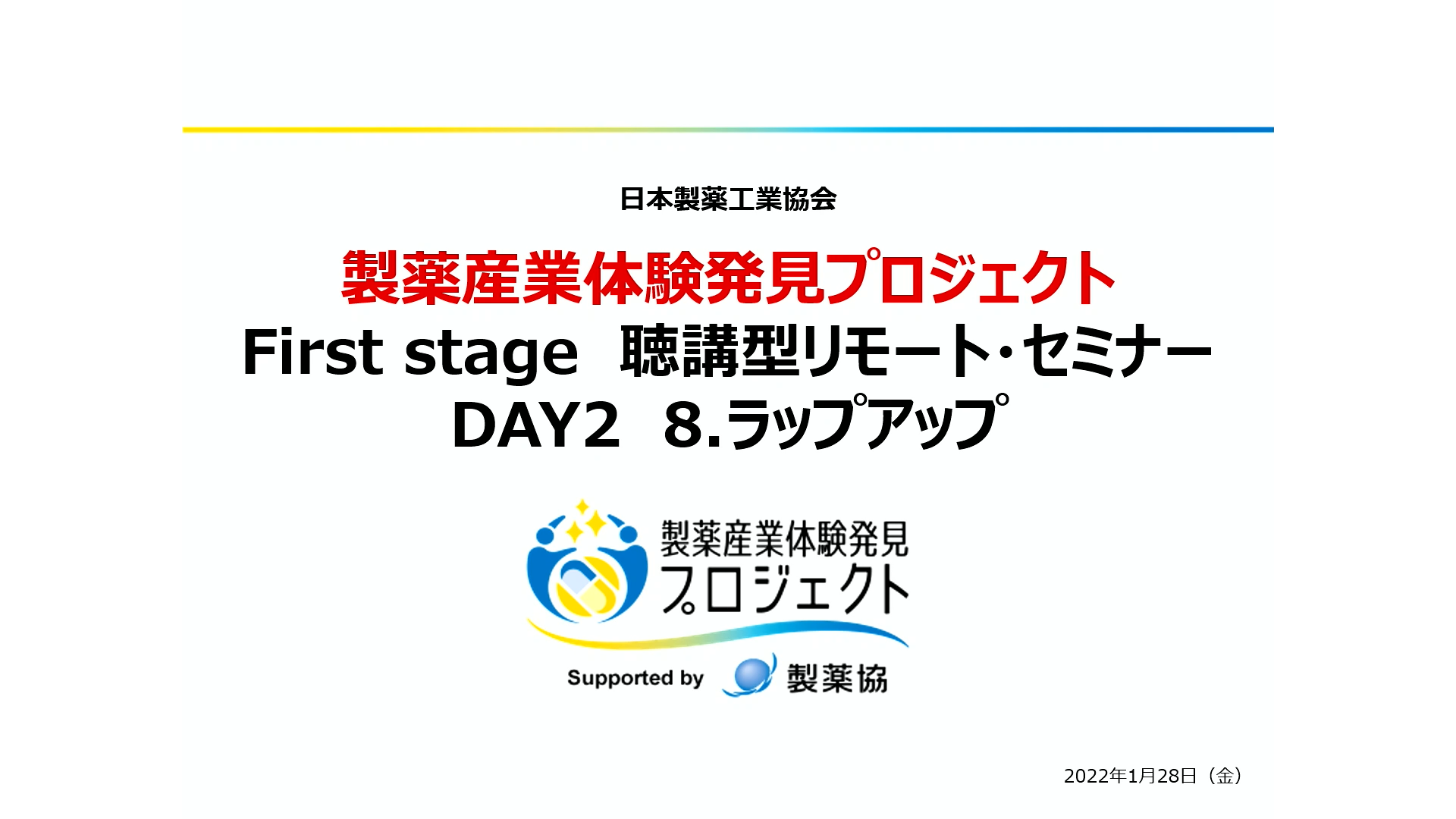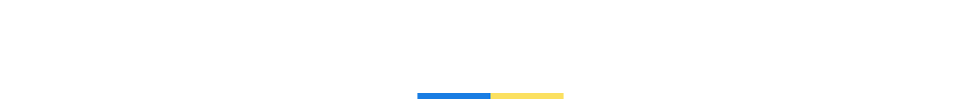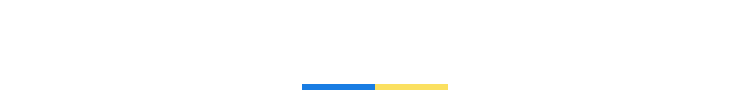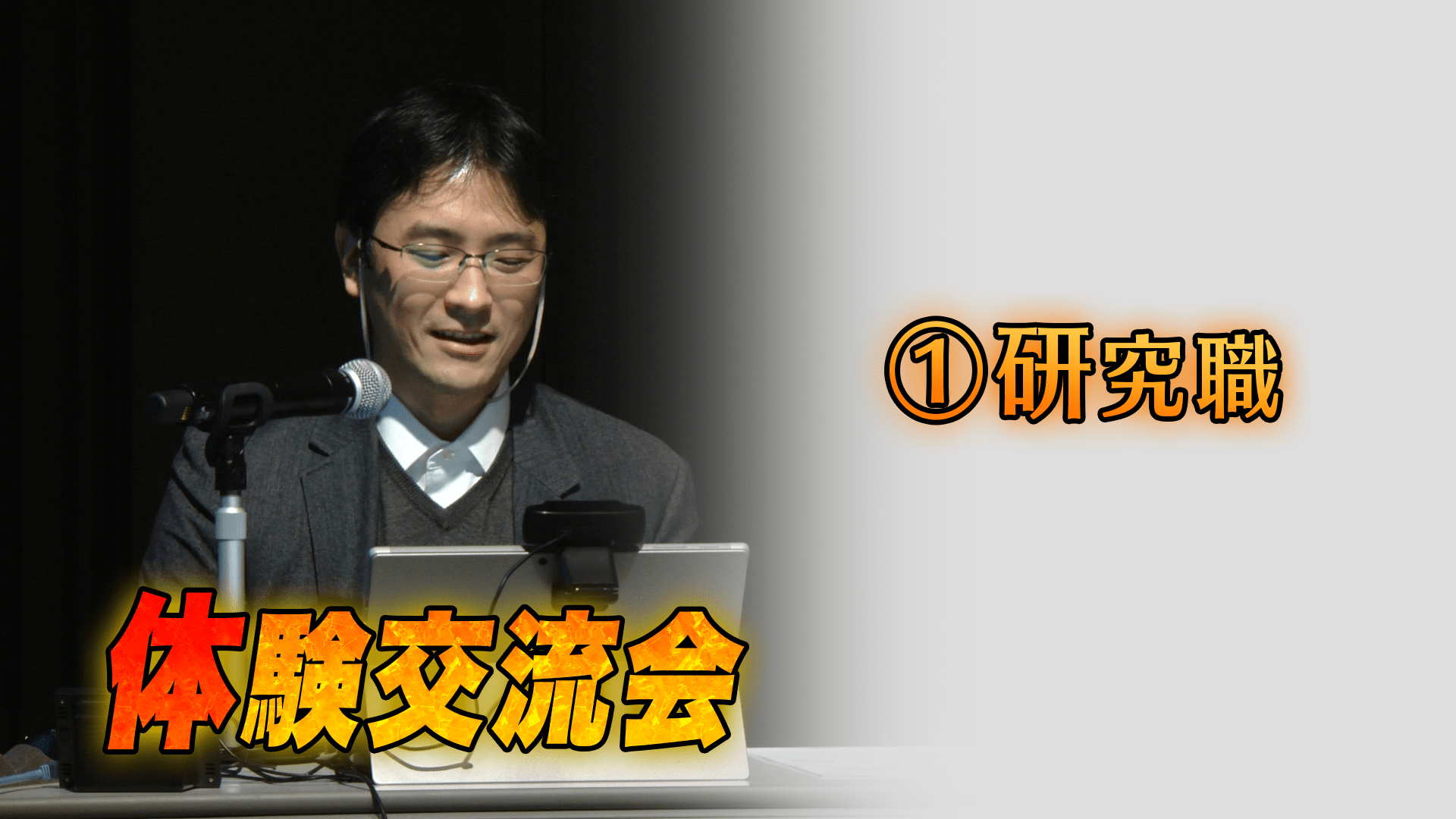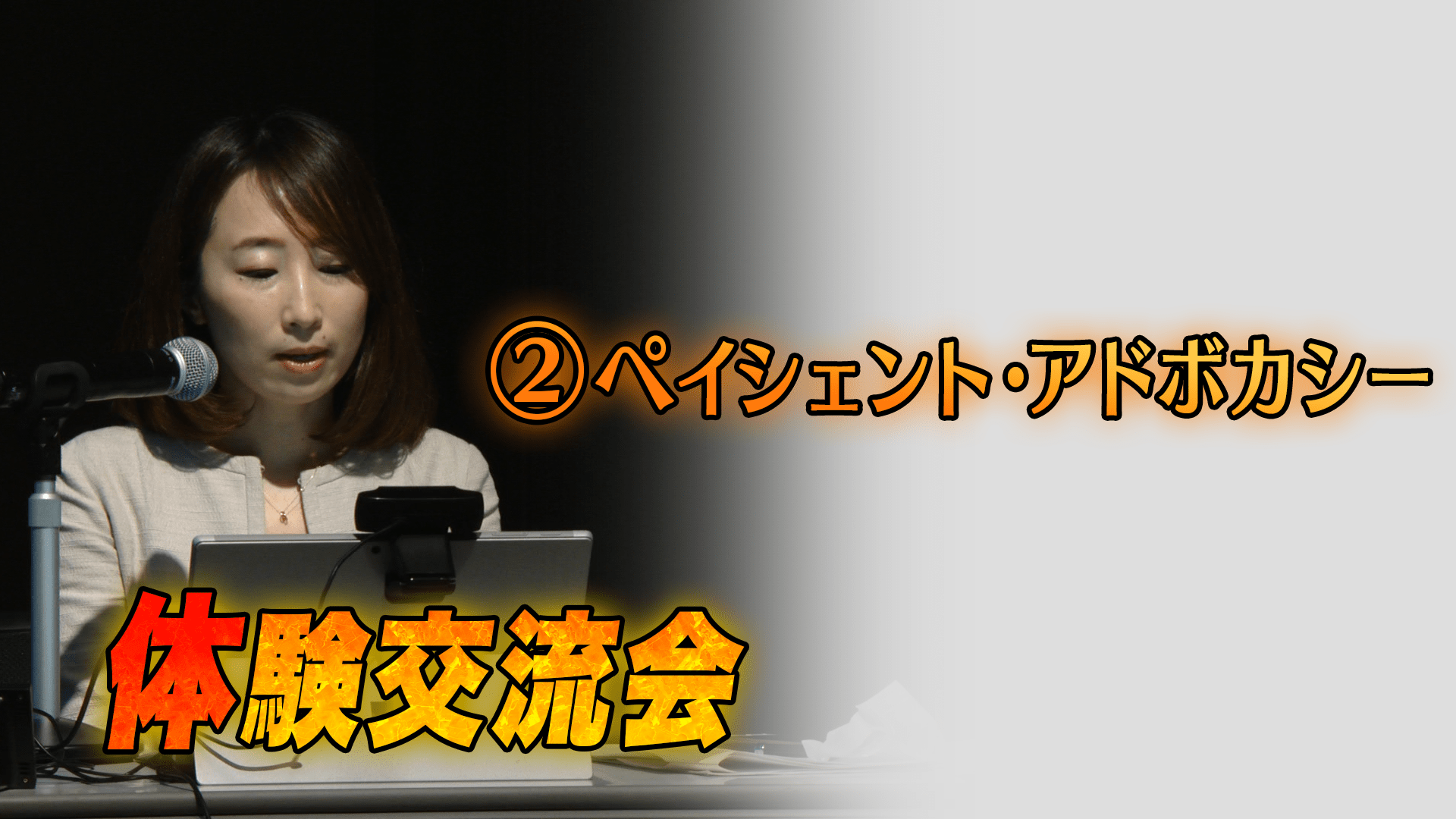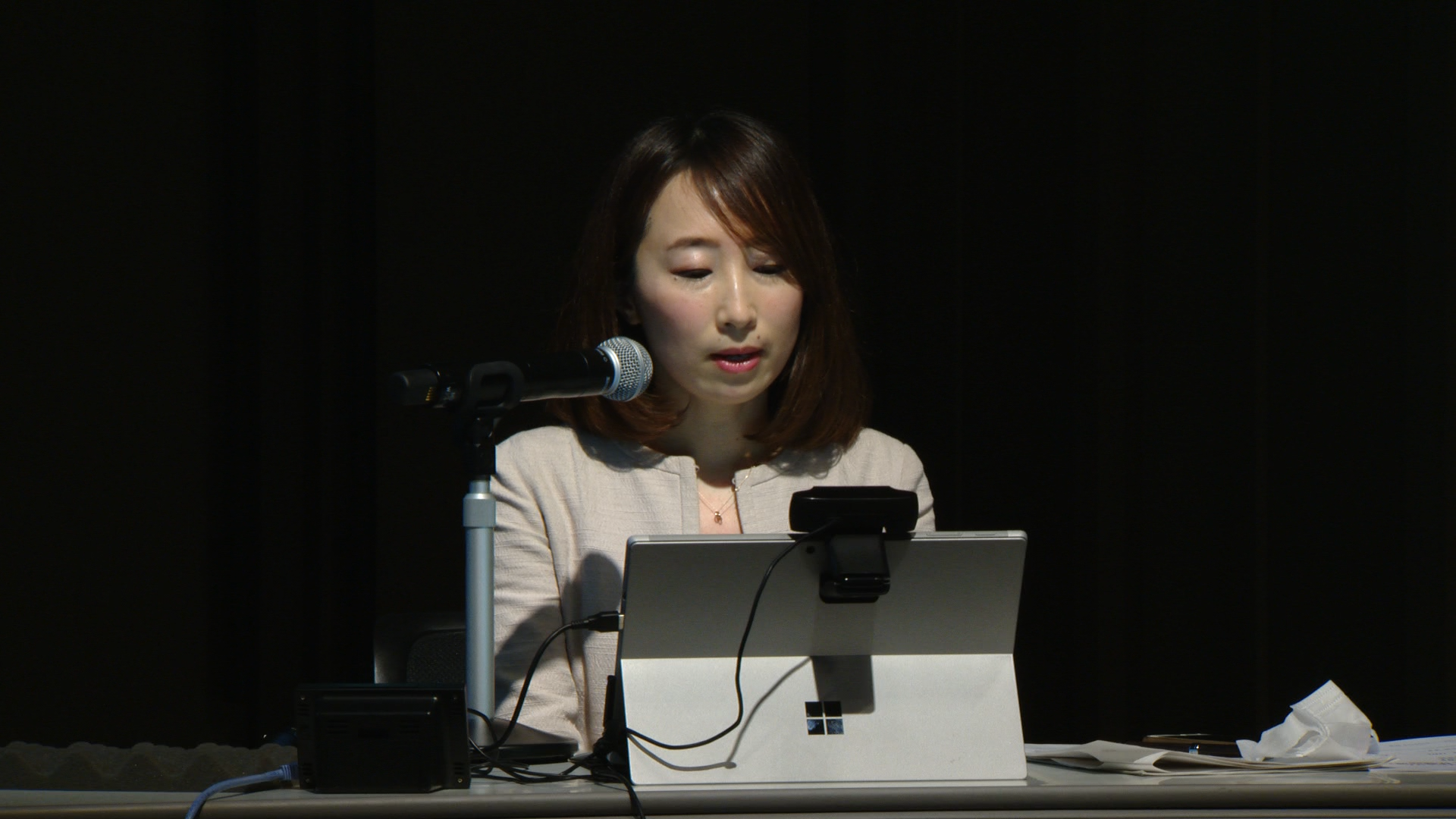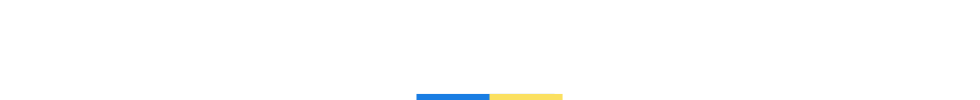- First stage
- 聴講型セミナー
- Second stage
- 体験交流会
- Final stage
- グループワーク体験報告会
このプロジェクトは、若い世代に、聴講型セミナーと製薬企業との交流体験会を組み合わせた
プログラムに参加いただくことにより、製薬産業への理解を深めるとともに、将来の産業従事への意識醸成をはかることを目的に、日本製薬工業協会(以下、製薬協)が企画致しました。
ライフサイエンス分野に挑戦する若い層が一人でも多く現れることを願っています。

RIKEJO CAFEは、理系⼥⼦⼤学⽣・院⽣のための学⽣参加型コミュニティです。
学年1年⽣から参加できるイベントや企業取材などを開催し、企業や社会⼈と接することで、 理系⼥⼦学⽣にキャリアについて考える機会を提供し、理系職種(技術者・研究職)への憧れや理解を得てもらいたいと考え活動しています。
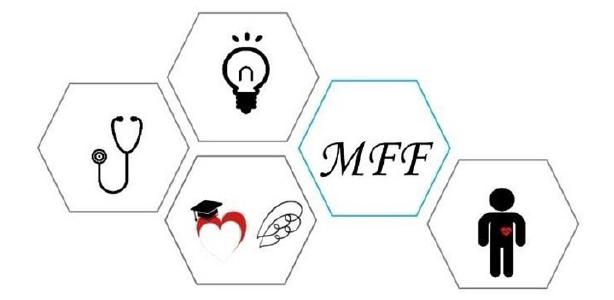
「医療系学⽣団体MFF」では、医師や看護師、薬剤師だけでなく、救急救命⼠や臨床⼯学技⼠、⾔語聴覚⼠など、将来、医療にかかわる様々な学⽣が幅広く参加できる学際的なイベントを開催しています。
セミナーや交流会などを通して学部学科を超えた新たな学びや出会いができます。
意欲あるあなたのご参加をお待ちしています!

「若者の⼒でいのちを守る社会を創る。」私たちInochi WAKAZO プロジェクトは、東⼤・京⼤・慶⼤・阪⼤の医学⽣を中⼼とした次世代イノベーター集団です。
産官学⺠若が⼀体となっていのちを守る未来社会を、私たち若者から実現します。
First stage
DAY1:2022年1月21日(金)
DAY2:2022年1月28日(金)
2日とも、13:00~配信

製薬産業、製薬企業の仕事について知る、学ぶ
「聴講型リモート・セミナー」
製薬産業に関わる実務家や顧客である医師を始めとする医療従事者、患者からのレクチャー
Ex.
・製薬産業について
・製薬企業の仕事
「製剤研究」「安全研究」「臨床開発」「生産/品質」
「MR/MSL」「PV/市場調査」「その他(国際/薬事等)」
・製薬企業の顧客 ①専門医②臨床医
・エンドユーザー ①患者中間団体②患者
Second stage
2022年2月18日(金)
13:00-16:00
オンライン開催

製薬産業で働く人との交流を通して、仕事への想いや実態を理解
「体験交流会」
製薬協の加盟製薬企業の研究職をはじめ様々な職種の業務担当者からの体験談や質疑応答などの体験交流機会
Ex.
・動画による製薬企業の実務紹介
・製薬企業の実職務紹介(体験談スピーチ・ある1日の紹介など)
・交流会 ①質問会 ②交流会
Final stage
2022年3月18日(金)
13:00-17:00
会場+オンラインの同時開催

学んだ成果と今後の可能性をグループワークでまとめ、発表
「報告体験会」
当日のグループワーク、その結果発表をチームごとに実施。
結果を審査・表彰
※First Stage、Second Stageを継続受講した方のみ参加可能
Ex.
・グループワーク
・プレゼンテーション発表
・審査発表
速報‼
製薬産業体験発見プロジェクト「セカンドステージ開催!」
2022年2月18日(金)13時-16時
製薬産業で働く人との交流を通して、仕事への想いや実態を理解する-「製薬産業体験発見プロジェクト」セカンドステージは2022年2月18日にオンラインで開催されました。
参加者の方々には、先ず、はじめに製薬産業理解のための動画3本をご視聴いただき、質疑応答を経て、製薬企業実務経験者3名による業務の個人体験談紹介、個別の質問会、交流会と16時までの3時間に亘り、製薬産業に従事することのやりがいや喜び・志等を熱く語り合う交流会となりました。
体験談紹介
「研究職」
発表者:日本ケミファ株式会社 創薬研究所 創薬第二研究室室長
今井 利安さん
京都府出身、大学院時代は研究三昧、ひたすら実験ばかりしていた今井さん。大学3年までバイトと部活の毎日だった今井さんが、なぜ薬学博士号を取得し、創薬開発をしているのか。体験談をお話いただきました。
「ペイシェント・アドボカシー」
発表者:協和キリン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
PRグループ(ペイシェント・アドボカシー担当)
豊泉 夏紀さん
100社以上の会社説明会に参加し、受けた会社も70社以上。ただし製薬会社の説明会は1度も行かなかった豊泉さんは、なぜ製薬会社でペイシェント・アドボカシーを担当することになったのか。体験談をお話いただきました。
交流会
ついにフィナーレ!
「製薬産業体験発見プロジェクト」ファイナルステージ体験発表会3月18日開催
1月21日、28日のファーストステージでの聴講型セミナー、2月18日のセカンドステージでのリモート交流会を経て、3月18日、ファイナルステージが開催されました。
当初はオフライン開催を予定していたファイナルステージですが、東京都における、まん延防止等重点措置の延長という事態を鑑み、オンライン開催となりました。
開催当日は、30名を越える学生の皆さんにご参加いただき、グループワークを経て、6グループによるプレゼンテーションが実施されました。
「製薬産業体験発見プロジェクト」ファイナルステージダイジェスト
グループワークの冒頭は、各グループのネーミング決定、リーダー、書記の選定などのチームビルディングを経て、グループディスカッション→プレゼンテーション→審査発表と4時間のイベント風景をダイジェストでご紹介します。
課題テーマスライド
事前に製薬協より提示されていた課題テーマ「学生さんの皆さんに製薬産業・製薬企業の仕事や役割を知ってもらう方法とは?」に対して、6グループそれぞれが火花を散らしたプレゼンテーションを行いました。
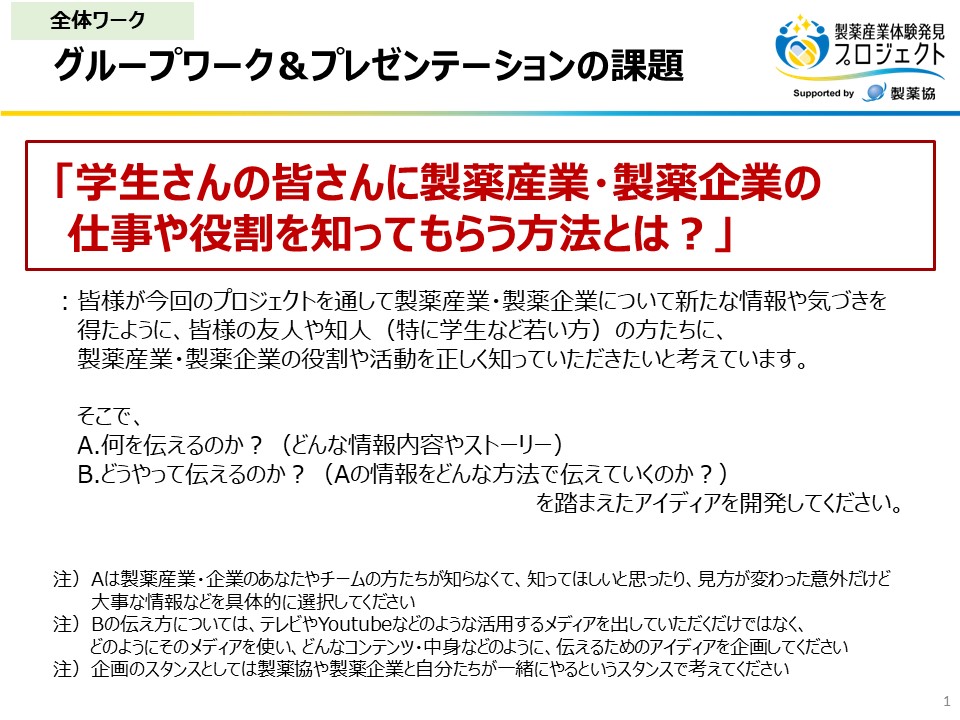
製薬協からの課題は、学生の皆さんが今回のプロジェクトを通して製薬産業・製薬企業について新たな情報や気づきを得たように、皆さんの友人や知人(特に学生など若い方)の方たちに、製薬産業・製薬企業の役割や活動を正しく知っていただく、その内容と方法です。
つまり、
A.何を伝えるのか?(どんな情報内容やストーリー)
B.どうやって伝えるのか?(Aの情報をどんな方法で伝えていくのか?)
を踏まえたアイデアを開発してください。
というものです。
グループ別体験発表会
ファイナルステージ参加者は、6つのグループに分けられ、最終課題となっているテーマについて、それぞれのグループ毎にソリューションを開発し発表、製薬協の厳正な審査の結果、最優秀賞1グループ、特別賞1グループが選出され、更にそれ以外の参加者全員に参加賞が贈呈されました。

審査発表
6グループから提示されたアイデアは、製薬協の広報委員会メンバーによって審査され、特に今後、年齢層の若い方々に対するコミュニケーションを考える上での参考にさせていただきます。
また、特に優れたものに「最優秀賞」、審査委員の心を掴んだものには「特別賞」を、それぞれ授与させていただきました。
最後に
「製薬産業体験発見プロジェクト」参加者の皆さん、本当にありがとうございました。
ファーストステージからファイナルステージまでご参加いただいた方、また諸般の事情でファーストステージのみ聴講された方、セカンドステージのみご参加された方も、今回のプロジェクトに積極的にご参画いただき、ありがとうございました。
皆さんからいただきました数々のプランを基に、来年からの製薬協のコミュケーションプランを検討し、更に実りあるものにしていく活動を今後も続けていきたいと存じます。
この活動により、製薬産業をより身近に感じていただき、日本の製薬産業が発信する画期的な情報の数々に触れていただく機会が増えることを期待します。
本日はありがとうございました。
日本製薬工業協会


「inochi Pharma Campaign Program~中高校生と考える、次世代の製薬産業の在り方~」と題した、日本製薬工業協会(以下、製薬協)とinochi WAKAZO プロジェクト(以下、inochi)の共催イベントが3月21日に、室町三井ホール&カンファレンスにて開催されました。
このプログラムは2021年開始された製薬協提供による「製薬産業体験発見プロジェクト」の第2弾として、若年層、特に中高校生向けのレクチャーと交流によって、製薬産業に関する理解を深めてもらうことを目的にしています。
※参加者の肩書、役職等はイベント開催時点のものとなります。
イントロダクション
「inochi Pharma Campaign Program~中高校生と考える、次世代の製薬産業の在り方~」は、全体が3部構成からなるイベントです。第1部は外部講師による講演会、第2部は外部講師に加えて、製薬協のメンバーも参加した専門家4名のパネルディスカッション、そして第3部は中高校生の参加者をメインにinochiの大学生も入ったリフレクションタイムとなります。第1部、第2部のプログラムで知り得た製薬産業に関する「学び」を踏まえて、参加者皆での振り返りを行い、製薬産業に関する理解を深めてもらいます。
第1部 講師講演会

講演タイトル「脳をAIで治療する」
講師:東京大学 薬学部 教授
池谷 裕二 氏

第1部の講演会では、東京大学薬学部の教授である脳科学者の池谷裕二先生と、株式会社エクサウィザーズの代表取締役であるAI起業家の石山洸氏を講師としてお招きし、産学の両方の立場から、最新の知見を含むAIの実用化について講演が行われました。中高校生が参加する会場での講演に加え、オンラインでも約150人が視聴し、医療とAIに関する学習の機会となりました。
池谷先生は、「脳をAIで治療する」というテーマのもと、AIがどのように創薬に貢献しているかを様々な事例を交えて具体的に説明しました。また、AIにおける「ディープラーニング」の重要性から、将来的にヘルスケア分野における可能性にも触れ、医療分野におけるAIによる画像診断から始まり、ウエラブル端末による健康管理、医療用コンタクトレンズによるリアルタイムの眼圧モニター、そして人工知能によるカウンセリングまで、医療分野がAIの活用によって大きく変革していることが紹介されました。
最後に池谷先生からは、講演に参加した中高校生に向け、「私たちからバトンを受け取り、若い方々がこの分野へ挑戦してくれることを期待しています」とエールが送られました。

講演タイトル「スタートアップ視点の創薬ビジネス」
講師:株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長
石山 洸 氏

次に、石山洸氏が「スタートアップ視点の創薬ビジネス」というタイトルで講演を行いました。石山氏はスタートアップに相応しい形で、自身の個性的な起業家プロフィールを笑い話を交えながら紹介しました。また、中高校生にとってビジネスシーンがあまり馴染みのないことを踏まえ、ビジネスにおけるAIの可能性について分かりやすく解説しました。
その話題はAIに限らず、ベンチャー企業におけるリーダーシップの重要性や、最近話題の「Chat GPT」についても触れました。今回の講演内容を準備する際に「Chat GPT」に質問してみたところ、かなり素晴らしい回答が得られたことを、会場を笑わせながら語りました。
更に大谷選手を例に挙げ、AIと創薬の「二刀流」で起業家精神を発揮し、最終的にはユーザーにきちんとモノを届けることの重要性を力説しました。
第2部 パネルディスカッション
モデレーター
日本製薬工業協会 専務理事 森 和彦 氏
パネリスト
日本製薬工業協会副会長
塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長CEO
手代木 功 氏
東京大学 薬学部 教授
池谷 裕二 氏
株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長
石山 洸 氏
第2部は、「創薬の未来~日本の製薬産業はどこに向かうべきか?」をテーマに、パネルディスカッションが行われました。モデレーターの製薬協の森氏はオープニングトークで、「AIで作られた医薬品を使用したいですか?」や「医薬品の研究や仕事に関心がありますか?」などの質問を会場に投げかけて、最近の世界的な製薬産業の成果について紹介しました。
塩野義製薬の手代木氏は製薬会社を代表して、「創薬の未来をどのように考えているか?」という製薬協の森氏の問いかけに対し、ベンチャーやアカデミアと協力して、開発期間を劇的に短縮することが製薬会社に求められていると語りました。
池谷先生は、「創薬」の「創」はクリエイティブな意味があり、多くの技術、テクノロジー、そして経験の集大成であることを述べました。特に、日本は世界で最初に高齢化社会に直面しており、高齢者をターゲットにした人知+AIによる新しいアプローチによって創薬のチャンスがあると話しました。
石山氏はAIベンチャーがよく問われる「AIに社会的な価値はあるのか?」という問いかけを引き合いに出し、AIにとって「創薬」は一丁目一番地。AIが創薬に活用できなければ、AIに社会的な価値があるとは言えないと述べました。また、AIは社会的な価値とサイエンスの面白さの両方を持った分野であると主張しました。
1時間以上にわたるエキサイティングなディスカッションの内容は、Youtube動画でご覧いただけます。
第3部 リフレクションタイム(抜粋)
第1部の講演会、第2部のパネルディスカッションを聴講した学生達が、自らが思ったこと、感じたことを共有し合い、自分達のものにする時間を設けました。
リフレクションタイムは、inochiの大学生がファシリテーターとなることで、講師と受講者という関係ではなく、学生同士が目線を合わせて議論の交流をする貴重な機会となりました。
当日は会場参加、リモートを含めて中高校生を中心に200名を超える参加者を迎え、製薬産業に従事している産学のトップリーダーによる講演、パネルディスカッション、リフレクションタイムと盛り沢山の内容となりました。
特に冬休みの中高校生にとっては、普段は話をする機会のない方々との交流は、製薬産業に対するより深い知見を得る機会になったのではないかと思います。
今後もさまざまな機会を創り、製薬産業の担い手となる若い方々に、有意義な情報を発信していきます。
日本製薬工業協会